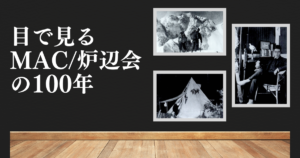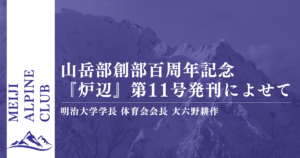明治大学体育会山岳部(MAC)は昨年、お陰様で創部百周年を迎えることができました。100年という大きな節目の年だけに、記念誌の発行や記念登山、記念祝賀会などを企画しておりましたが、折からのコロナ禍のため、全て順延せざるを得ませんでした。幸い本年に入って状況が好転し、5月14日、めでたく祝賀会を開催し、皆様のお手元に『炉辺』第11号:創部百周年記念号をお届けできる運びとなりました。
日本における近代登山の魁は、1905(明治38)年の日本山岳会(JAC)の創立と言えるでしょうが、そのJACは間もなく創立120周年を迎えます。この近代登山120年の歴史の中に、我がMACも様々な足跡を残してきましたが、100年の間には、悲喜こもごもの歴史が刻まれております。それらを俯瞰し、記録と記憶をしっかりと後世に語り継ぐため、本書の構成について諸々検討を進めてまいりました。
ところが昨春、仙台在住の鳥山文蔵会員(昭和49年卒)から分厚いプリント・ファイルとともに1本のUSBメモリーが送られてきました。中を開けてみてびっくり、「第1部 明治大学山岳部/炉辺会100年の歩み」から始まって「第8部 資料編」まで、全ての原稿が整っておりました。それは駿河湾から富士山、いやいやベンガル湾からエベレストの頂上へ、一歩一歩営々と刻んでいくような膨大な作業量です。そのような次第でして、この『炉辺』11号は、まさに鳥山会員が独力でまとめ上げてくれた大変な労作であり、私はただ原稿整理と進行管理をしただけにすぎません。MAC並びに炉辺会会員を代表して、鳥山会員に衷心より御礼申し上げたいと思います。
8000m峰14座を登ることなどは、もちろん山岳部として一番大事なことですが、それに勝るとも劣らない大切な作業が、それらの活動を記録しておくことです。幸い私たちには部報『炉辺』があり、年3~4回の発行を継続してきた「炉辺通信」があります。特に「通信」の発行を決断し、刊行し続けてきた先人たちには、心から感謝したいと思います。そのベースがあり、鳥山会員のような地味な作業をコツコツとこなしてくれる貴重な存在があるからこそ、『炉辺』もスムーズにまとめることができました。
『炉辺』10号が創部90周年記念として2012(平成24)年に発行されていますので、その後の10年間の記録をパート2としてまとめてあります。21世紀に入ったころより登山界も大きく様変わりし、山登りの楽しみ方が多様化し、その裾野が広がっています。そのような状況下でMACは部員不足が慢性化し、活動がパワーダウンしています。100年の伝統を守ることも大切ですが、時代に合わせてMACも変わらざるを得ないのではないでしょうか。
胸膨らませて大学の門をくぐって来た若者たちに、山登りの魅力とクラブ活動の意義を伝えていくことが、私たちに課せられたミッションです。向後の「MACの山登り」はどうあるべきか、現役・OBが一体となって模索し実行していくことが、喫緊の課題と考えます。100年を反芻し、その先の100年を展望しながら、力強く101歩を踏み出していきましょう。
(編集委員会を代表して 節田重節)
◇『炉辺』11号編集委員会
委員長=節田重節、河野照行、鳥山文蔵、谷山宏典
*表紙のカット写真は、上田謙之助会員(大正14年卒)が大切に保存されていたMACの部員章の原型。山岳部創部の翌年、1923(大正12)年ごろに、誉田実会員(昭和2年卒、スケート部創部者)が東京美術学校(現・東京芸術大学)の友人に依頼して作ってもらったもの。
*本扉の「カウベル」のカットは、4号から8号まで使用されていたもので、作者は川島直昭氏。2号の扉に載せられた「山小屋」と題した1色刷りの絵に始まり、数々の挿画で『炉辺』を飾られた方である。
炉辺 第11号
発行日/2023年6月1日
発行者/明治大学体育会山岳部 炉辺会
東京都千代田区神田駿河台 1−1
印刷/前田印刷㈱