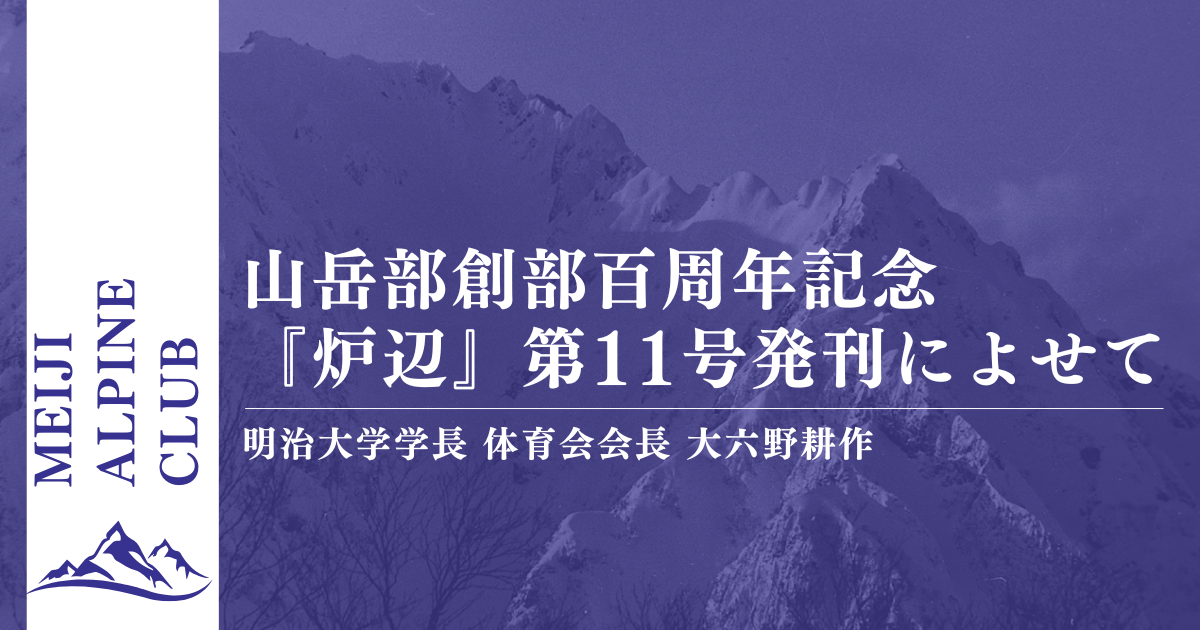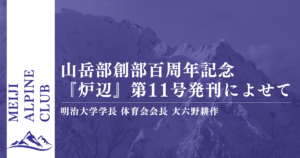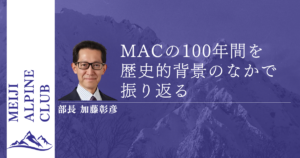本記事は、炉辺会の機関誌『炉辺11号』(発行日:2023年6月1日)に掲載されたものを、ウェブ版として再掲載したものです。

明治大学山岳部は創部百周年を迎えました。その大きな節目に当たる周年記念事業として『炉辺』第11号の発刊に至りました。『炉辺』は山岳部と炉辺会(OB会)の歩みをまとめた部報で、1924(大正13)年の創刊号以来11号を数えることになります、その100年に及ぶ記録は組織活動を継続させる基本となっています。
我が明治大学山岳部が積んだ最初のケルンは、100年前の1922(大正11)年 5 月23日、「馬場忠三郎、磯部照幸ノ両名、本学ニ山岳部ノナキヲ慨シテ、両名発起人トナリ、学長ニ許可ヲ申請セリ」という文言に始まります。同月 30日、「予科山岳会」として学長から設立許可を得、 6 月16日、米澤秀太郎、新田義朗らの「スキー倶楽部」と合体し、「明治大学山岳部」として学友会の補助部となっています。
故米澤秀太郎会員が筆を執った「山岳部設立趣意書」に ――《(略)翻って我国の山岳界を見るに、おしいかな我国には雪線を越える山や氷河を湛へたる山は有りませんが、近時其の隆盛は驚く許りで、特に都下の学校で山岳部のない所はない様な盛況であります》とあるように、この時代には、我が国初の「登山ブーム」が起こっていたのです。
日本の近代登山史は、1905(明治38)年の日本山岳会の創立を嚆矢とすると言われますが、やがて「大正デモクラシー」の勃興とともに、皇族や華族、上流社会の遊びであった登山が、大衆化の方向に舵を切り、昭和初期にかけての「第 1 次登山ブーム」へと盛り上がっていきます。その中心となったのが旧制高校や大学の山岳部で、まず “ナンバー高” に山岳部や旅行部が生まれ、続いて1915(大正 4 )年慶應義塾、19年学習院、20年早稲田、そして22年明治と、私学にも山岳部が続々と誕生していったのです。
爾来100年、「炉辺の子」である部員と会員の皆様が、連綿と情熱を注いできた登山活動の積み重ねにより、ここにめでたく創部百周年を迎えられることになりました。大きな節目の年を祝うとともに、これまでの歴史を紡いでこられた皆様のご尽力に対し、心より敬意を表します。この間の活動にご理解とご指導、ならびにご支援とご協力をいただいた多くの皆様に、心からお礼を申し上げます。
100年の歴史とは、まさに山あり谷ありの連続でした。創立後間もない第1 回夏山登山(燕岳~常念岳~槍ヶ岳、針ノ木峠越え~剱岳~白馬岳)から始まって、八方尾根山寮の建設、初の海外遠征となる台湾登山、戦後復興の象徴となった畳岩尾根から極地法による奥穂高岳登頂、 5 名の山仲間を失った白馬二重遭難、日本人初のマッキンリー(現・デナリ)登頂、初のヒマラヤ遠征でゴジュンバ・カンⅡ峰初登頂、故植村直己会員による日本人初のエベレスト登頂へと続きます。そして、最終的には33年もの長いタイムスパン(1970年エベレスト~ 2003年アンナプルナⅠ峰)の中で、単一の大学山岳部による8000m峰14座完登を成し遂げることができました。
一方、このような栄光の陰で、山で失った仲間たちのことを忘れてはなりません。残念ながら白馬二重遭難をはじめ、何件かの遭難事故がありました。 6 年余の歳月を懸けて『遭難の実態』(1964年、教育図書刊)を出版したのも、二度と遭難を起こしてはならないとの強い想いからです。負の歴史から学んだ教訓を決して風化させることなく、次世代に語り継いでいきたいものです。
さて、継続の道標ともなる周年記念登山を顧みますと、20年前の創部80周年(2003年)がアンナプルナⅠ峰、10年前の創部90周年(2011年)には、学生を中心にして北米最高峰・マッキンリーに登山隊を派遣し、半世紀前に先輩たちが登った因縁の山に、全員で登頂することができました。次に続く若者たちに、貴重な海外登山経験を積ませることができたと考えています。
そして、これに続く創部百周年の記念海外登山を実施すべく準備会を立ち上げ、記念登山に意欲的で経験豊富なOBたちが中心となって実施計画の検討を重ねましたが、長引くコロナ禍のために再検討を余儀なくされてきました。
最終的に目標の山は東ネパールの未踏峰アニデッシュチュリ(ホワイト・ウェイブ、6960m)とし、メンバーは学生 2 名にOB 2 名、実施時期は 2023年秋としました。この記念登山、記念誌の発刊などの記念事業の実施を通して部員と会員相互の絆を深め、より活性化させて、次なる100年に向けて登山活動を継続させていきたいと思います。
一昨年の春より未だに続くコロナ禍という未曾有の事態に直面し、人との接触を極力避けることが求められ、私たちの日常は様々な制約に晒されてきました。学生の授業は感染状況に応じてオンラインとなるなかで、山岳部活動では制約を受けながらも感染対策を施し、指導陣の参加のもと各山行を行ってきました。
それでもコロナ禍が長期にわたったこと、それに慢性化している部員不足が加速していることなどで部活動の力量不足が生じています。これらに対処するべく指導陣を含めたOBのサポートを継続させるとともに、部活動の要となる部員不足について、喫緊の課題として取り組んでいかなければなりません。
100年間にわたって「炉辺の子」たちは、国内外で精力的に数多くの登山を継続させてきました。連綿と刻まれてきたその歴史を振り返るに、私たちを魅了し続けてきたのは「山登りという文化と冒険的なスポーツ」の持つ奥深さではないか、と感じています。この奥深さを追求し、掘り起こして、創造性豊かな山登りを実践していきたいと考えております。さらなる高みを目指して、山岳部と炉辺会は「一歩前へ」歩み続けていきましょう。