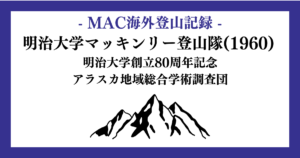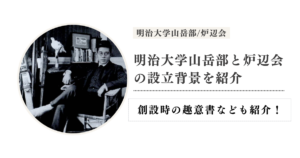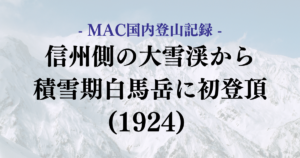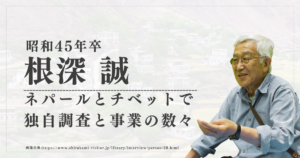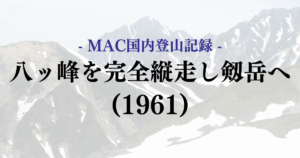本記事は、炉辺会の機関誌『炉辺11号』(発行日:2023年6月1日)に掲載されたものを、ウェブ版として再掲載したものです。

本年、明治大学体育会山岳部(Meiji Alpine Club/MAC)は創部100周年を迎え、『炉辺』第11号は100周年誌として刊行されることになりました。 MAC・炉辺会の過去100年間を日本の近現代史のなかで振り返ると、一つの歴史的サイクルが完結したという感慨に打たれます。
MACが誕生した1922年前後には、大学山岳部――京大(1915年)、慶応(1915年)、学習院(1919年)、早稲田(1920年)、立教(1922年)、東大(1923年)、法政(1924年)など――が相次いで設立され、20世紀初頭に生まれた若者たちが、日本アルプスのさまざまなルートを開拓し、トレースしていきました(MACも積雪期白馬岳周辺で成果を上げます)。
彼らは、人口増加が本格化するなかで生まれた世代です。若者人口の持続的増加によって若いエネルギーの蓄積が進んだことが、近代アルピニズムの扉を開きました。当時の世相は大正バブル経済を背景にした大正デモクラシーの時代。「成金」という言葉を生み出したバブルは経済学的には1920年に崩壊しましたが、自由主義的な風潮は関東大震災を経た1920年代後半まで続きました。
世界恐慌にも襲われて厳しい時代となった1930年代にも、大学山岳部の学生たちは日本アルプスでの初登攀ラッシュや積雪期の初縦走を繰り広げて、近代アルピニズムの理念を実践しました。極地法を取り入れて、朝鮮、台湾、満州、さらにはヒマラヤへの遠征を試みるようになったのもこの時代です。MACもまた前穂高岳・北尾根の明大ルート開拓や南アルプスの積雪期縦走、さらには台湾遠征(積雪期奇莱主山連峰)を実現しました。
戦後の登山史は、大学山岳部が大戦前に試みた極地法を国内の冬山で実践することで再開され、その勢いでヒマラヤ8000m峰14座初登頂競争――1950~60年に13座が初登頂された――に乗り出していきました。
周知のように 日本隊は1956年の第 3 次遠征でマナスル初登頂の栄冠を勝ち取りましたが、 MACも1947年に極地法で奥穂高岳に登頂し(畳岩尾根積雪期初登)、その際主将を務めた大塚博美(敬称略)が第 3 次マナスル登山隊で活躍しています。
マナスルを皮切りに、極地法を身につけた大学山岳部とそのOB山岳会は 世界の高峰に組織的な遠征登山隊を繰り出し、と同時に社会人山岳会は少人数で欧州アルプスの大岩壁に挑んで、日本人初登頂を競い合いました。
時は高度成長期。東京五輪から大阪万博、そして札幌五輪へと国際イベントが続くなかで、世界の高峰への冒険的挑戦が日本の成長・発展のわかりやすいシンボルとして人びとから賞賛された時代でした。
その主役たちは、戦時中に生まれ育った世代から敗戦直後に生まれた団塊の世代です。この1930年から 49年出生の世代は、乳幼児死亡率が低下した直後に生まれたために、戦前よりもさらに巨大な、同世代で熾烈な競争を繰り広げる若者集団へと成長しました。
MACがマッキンリー(現・デナリ)に登頂し(1960年、日本人初)、ヒマラヤのゴジュンバ・カンⅡ峰に初登頂し(1965年)、植村直己がエベレスト登頂に成功して(1970年、日本人初)、その勢いで 5 大陸最高峰初登頂者の栄誉に輝いたのは、そんな時代でした。
植村は北極へと転進して、文字通りにグローバルな冒険家「世界のウエムラ」として活躍していきます。もっとも、こうした強烈な光は同時に深い影をともないました。都会の若者たちは安保闘争から全共闘運動へと猛進して多数の死者を出し、山では大量の遭難死が発生して、MACでも死亡事故が相次ぎました。
高度成長期におけるMAC・炉辺会のヒマラヤでの経験は、1980~ 90年代に大輪の花を咲かせていきます。1982年のダウラギリⅠ峰から1996年のK 2まで、1970年のエベレストを含め8000m峰14座のうち 9 座が会員によって登られ、その成果は1997年のオール明治隊によるマナスル登頂に結実しました。
その際活躍した若手――団塊ジュニア世代/1970年代生まれ――のエネルギーが「ドリーム・プロジェクト」による残り 4 座の登頂、すなわち 1 つの団体による14座完登という大収穫をもたらしました。
この成果は、単に MAC・炉辺会の達成というだけでなく、日本登山史においては、1930年代に大学山岳部が取り入れた極地法の実践がその可能性の頂点を極めた、という歴史的意義を持つように思います。極地法は、その人材育成の面も含めて、溢れ出る若者集団のエネルギーを組織化・集約する優れた方法でした。
MAC・炉辺会の歴史は、日本近現代史のなかに位置づけることもできま す。日本人の平均年齢(総人口の年齢中央値)は、大正から戦後10年までは 20代前半、高度成長期は20代後半、1980年から1990年代末は30代でした。14座完登を成し遂げた2000年代初頭は41歳、まさに社会全体が成熟を遂げた時期に当たります。しかし、成熟は老いの始まり。2010年以降、日本人の平均年齢は40代後半となり、2020年代に入りついに50代に突入しています。リスクをともなう登山や冒険がますます危険視されるようになり、高校山岳部のハイキング部化が進んだ結果、大学山岳部一般が慢性的な部員不足に悩むようになったのは、日本全体の老いの表れと言ってもよいでしょう。
このような時代に、我々は次の100年に向けて、どのような方向を目指せばよいのでしょうか。歴史を振り返ると、MAC・炉辺会の活動の基軸は常にアルパイン・クライミングであったように思います。北極で大冒険を繰り広げた植村も最終目標には南極横断とともに最高峰ヴィンソン・マシフがあり続け、その準備として冬期マッキンリー単独初登頂がありました。
また、アルパイン・クライミングは、ワンダーフォーゲル部やウォーキング部とは異なる山岳部の専売特許でもあります。ならば、21世紀のMACには、アルパイン・クライミングのもう一つの方法、すなわちアルパイン・スタイルの可能性を、その人材育成の側面も含め、積極的に追求するという方向性があり得るでしょう。
実際2000年代後半以降、「ピオレ・ドール」(金のピッケル賞)を受賞する会員、プロの山岳ガイドやテレビ・ディレクターとして、エベレストやマナスルに登頂する会員が現れています。もちろんこれらは14座完登を成し遂げたMACのもう一つの成果とも言えますが、同時にプロフェッショナルなエリート・クライマーを育てるという21世紀の方向性を示唆しているようにも感じます。その理念を旗印として示せば「MACからMACC(Meiji Alpine Climbing Club)へ」と表現できるでしょうか。
具体的には、スポーツクライミングの素養のある高校生や大学新入生をリクルートして、アルパイン・クライマーに育て上げる、といった方向性です。そのためには、山岳でのクライミング技術習得を先行させ、挑戦すべきルートの目標を与えて動機づけながら、これに必要な体力・忍耐力を強化していくような、育成法上の工夫と柔軟性も必要でしょう。21世紀生まれの子どもたちのヒーローは、スポーツクライミングやアドベンチャーレースのアスリートたちなのですから。
「Meiji Alpine Climbing Club」と表現できるような理念の実際・実践を詳らかにすることは、私の能力を超えています。ぜひこの100周年の機会に、過去のMACの登山を振り返りながら、これらを、最新装備を使って最先端のアルパイン・スタイルで成し遂げるとしたら、どのような形があり得るのか、現役部員・炉辺会員とともに考えていければ、と願っております。
(文中、敬称略)