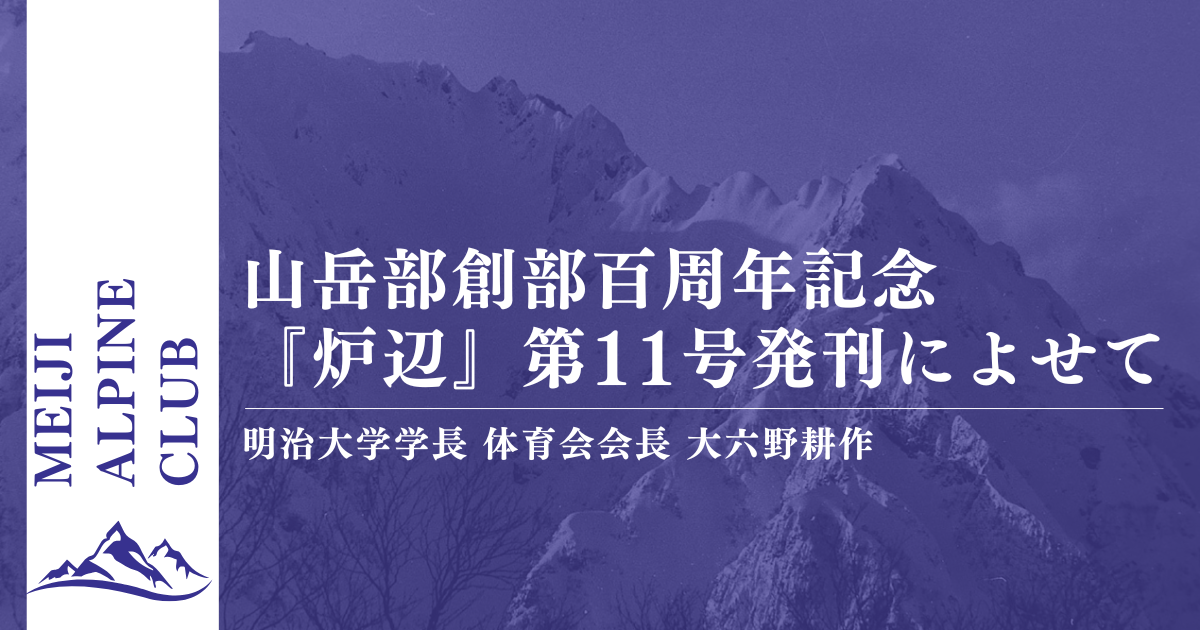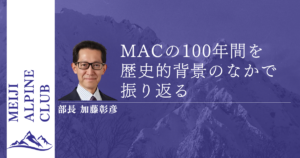本記事は、炉辺会の機関誌『炉辺11号』(発行日:2023年6月1日)に掲載されたものを、ウェブ版として再掲載したものです。

このたび、明治大学体育会山岳部が創部百周年を迎えられましたこと、誠に慶賀に存じます。この記念すべき節目にあたり、明治大学を代表して関係者の皆さまに一言お祝いを申し上げます。
1922(大正11)年に誕生した山岳部は、昨年、創立140周年を迎えた本学とともに、その栄光の歴史を刻んで来られました。この間、大正・昭和・平成・令和の時代を跨いで、その時々の困難をOB・OG・現役学生の強い絆によって克服されて来られました。明治大学長として、また、体育会会長として皆様のご努力に心より敬意を表したいと存じます。
明治大学山岳部の歴史は、日本山岳会の歴史そのものと言っても言い過ぎではありません。戦前には、今にその名を残す前穂高岳・北尾根Ⅳ峰の南東壁「明大ルート」を小国達雄さんと人見卯八郎さんが切り拓かれました。戦後は大塚博美さんが日本山岳会マナスル登山隊に参加し、日本人初の8000m峰初登頂ルートを開拓しました。また、本学が誇る世界的な冒険家である植村直己さんによる、日本人初のエベレスト登頂・世界初の 5 大陸最高峰登頂・北極点への犬橇単独到達など数々の輝かしい業績は、今でも世界中の人々の心に残る快挙でした。
植村さんは次のような言葉を遺されています――
・不安な時は小さなことでもいい、今できる行動を起こすこと。始まるのを待ってはいけない。自分で何かやるからこそ何かが起こるのだ。
・いいかい、君たちはやろうと思えば何でもできる。僕と別れた後もその事を思い出してほしい。やろうと思えば何でもできるのだ。
・いつも前進があるだけだった。
・必ず壁はあるんです。それを乗り越えたとき、パッとまた新しい世界がある。だから厳しく自分を鞭打ってやってきたときは、振り返ってみたとき実にさわやかです。
これらの言葉は、紛れもなく明治大学の精神を象徴するものであり、また、私の自身の思いとも重なります。
植村さんの後年の活動は北極圏を中心としたものでしたので、エベレストへの登頂を除けば、植村さんが8000m峰の頂に立つことはありませんでした。
しかし、山岳部と炉辺会は8000m峰への挑戦を続け、2003年にはアンナプルナⅠ峰登頂に成功し、世界の8000m峰14座のすべての登頂に成功した世界唯一の団体となりました。平成20年には、天野和明さんが、世界の優秀な登山家に贈られる「ピオレ・ドール(金のピッケル賞)」(第17回)を日本人として初めて受賞するなど、栄光の歴史は脈々と受け継がれております。
今世界は、その発生から 2 年半余りを経過しても終息をみない新型コロナウイルス感染症のパンデミックに苦しんでいます。また、ロシアによるウクライナへの一方的な軍事侵攻は、深刻な人道危機をもたらすだけでなく、米ソ冷戦の終結によってもたらされるはずであった世界平和を崩壊の淵にまで追い込み、各国がそのイデオロギーや利害を超えて団結することの難しさが改めて浮き彫りになりました。逆に言えば、人間同士の温かい繋がりや絆といった無形の絆がいかに大切なものであるかを、我々は痛感しています。
私自身、長年にわたって体育会ラグビー部長を務めておりましたので、部員ひとりひとりが互いに相手を信頼し、その信頼を基礎に一致団結して目標達成に向けて努力する「強い個人」に育っていくところに大学スポーツの真価があると信じています。
自然に正面から向き合い、自然が繰り出す様々な難題に誠実に立ち向かい、それぞれの個人が自らの責任を確実に果たし仲間と連帯する。このことなしには成立しないのが山岳登山ではないかと思います。現役部員の皆さんには、尊敬に値する幾多の諸先輩の経験を継承いただき、さらなる改良を加え次の世代に引き渡す責任があります。これからも、自然の前に謙虚であり、仲間を尊重し認め合う「強い個人」になって欲しいと切望しています。
結びになりますが、これまで山岳部の発展に陰に日向に貢献いただいた関係者の皆様に改めて御礼申し上げますとともに、今後も変わらぬご指導とご尽力を賜りますようお願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。