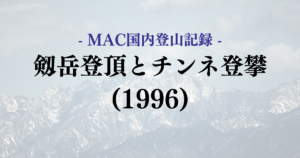シャハーンドク初登頂などヒマラヤ遠征で活躍した根深誠は、ネパールやチベットを舞台に、独自の調査や研究で異才を放っている。そこで彼が手掛けた幅広い調査と研究、そして事業をテーマごとに紹介する。
ヒマラヤの河川でイワナ・ヤマメの移植放流事業
根深誠は青森と秋田の県境にある白神山地をこよなく愛し、若いときから白神の渓流釣りに親しんだ。やがてヒマラヤに遠征する機会が増えると、ヒマラヤの渓流に棲息する魚に興味を持ち、パキスタン、インド、ネパール、シッキム、チベット、ブータンなどヒマラヤ各地を釣り歩いた。ヒマラヤの上流域には冷水を好むサケ、マスの仲間が棲息していない。この空白地帯に日本のイワナ・ヤマメを移植放流する事業に根深は参加した。事業の発案者は、「棲み分け理論」を提唱した生物学者の今西錦司氏である。
1975(昭和50)年から「日本淡水魚保護協会」(木村英造会長)と「ヒマラヤ保全協会」(川喜田二郎会長)は、共同でヤマメの移植放流事業に着手する。その年の秋、6万8000粒のヤマメ発眼卵をカトマンズ郊外のゴダワリ養魚場へ空輸し、孵化飼育を行い、翌年スン・コシ川源流部に放流する。その後、アマゴは懸念された雨季の増水期を乗り越え、成長したことを確認できたが、なぜか繁殖しなかった。
1981(同56)年のエベレスト遠征の帰途、根深は期待に胸膨らませスン・コシ川源流部で追跡調査を行った。しかし、ヤマメの姿を認めることができず、スン・コシ川放流は失敗したと悟る。
そこで翌1982(同57)年、放流に適する川はないかと、わざわざ雨季という悪条件を選び、敢えて透明な川を探すことにした。根深は過去二度訪ねたことのあるダランディ・コーラに狙いを付ける。ダランディ・コーラ上流や、ほかにもいろいろな川で水温、濁度、水生昆虫、PHなどを測定した結果、放流に適する川を数本見付けることができた。
後日、ネパール水産局を訪ね放流計画を説明すると、役人たちは「日本のイワナ、ヤマメがヒマラヤの渓流に放流されると地元の魚が駆逐され、食害を受ける。さらに生態系の破壊につながる」との懸念から、拒絶反応を露わにした。根深が地元の河川の上流域に魚類が棲息していないことをいくら説明しても納得してもらえず、結局、放流許可を入手することは叶わなかった。
その後も根深は移植放流の夢を追い求めて各地の河川を踏査し、2019年、チベットからの帰途、ネパールに立ち寄った際に、湧き水のある場所を見付けて夢の実現を画策している。
河口慧海のチベット潜入路検証
根深誠は明治時代、仏典を求めてヒマラヤを越え、チベットに潜入した禅僧・河口慧海に強く心を惹かれるようになる。現地を歩いてその足跡を調べる切っ掛けとなったのは、ムスタン入域の解禁であった。これによりトルボ(ドルポ)地方に入る許可がもらえれば、河口慧海が越えた峠を探ることができる、と期待に胸は膨らんだ。
1992(平成4)年、その想いを果たすべく実行に移す。この計画を支えたのが当炉辺会会員で(株)山と渓谷社の節田重節(昭和40年卒)と米山芳樹(昭和58年卒)である。ネパールの山奥、カリ・ガンダキ谷の奥ローマンタンや、辺境の地トルボの荒涼とした風景の中、慧海の足跡を追い求める旅を続けた。
それまで外国人の入域が禁じられていたトルボに、根深はネパール政府の特段の配慮で入域した。このトルボに入るルートは、いずれも5000m級の峠を越えねばならず、厳しい峡谷も通過しなければならない難ルートであった。想定されるチベット国境越えのルートに関して、根深はいろいろな人から情報を集め、また、河口慧海の著書『チベット旅行記』に記されたチベット側の湖をも検証した。
この調査行から12年後の2004(平成16)年暮れ、根深の働き掛けによって河口慧海が残した日記が公表され、根深は再度、現地調査に踏み切る。2005(同17)年夏、日本山岳会創立百周年を記念して実施された、河口慧海の足どりをたどるトレッキング・ツアーに講師として参加する。
彼は慧海の日記のコピーを持参し、クン・ラとゴヤ・ゴンパについて、日記の記述と照らし合わせながら検証した。また、2日間ツアーから離れ、若い僧侶と馬に乗って、ゲロン・リンポチェと慧海が会った白巌窟と思われるガルツァンという岩窟へ向かう。川岸の草地にテントを張り、根深は周辺の地形や慧海の日記、そして現地情報などを今一度思い巡らせて推考を重ね、白巌窟の場所を確認する。
さらに最後の踏査を2007(平成19)年と2008(平成20)年に計画したが、折しも北京オリンピックの開催に伴い当該地域への入域が困難となり、計画は頓挫してしまう。それから7年後、当該地域への入域が可能となり、翌2016(平成28)年に最終調査(白岩窟付近の調査と、そこから先、マナサロワール湖付近とその西側までの踏査)を計画する。しかし、調査費用の捻出が実らず、計画は断念せざるを得なくなる。
こうして、河口慧海に想いを馳せて43年、実際に踏査を開始して以来24年、「歩いて旅すること自体が論証」という根深は、数々の新事実を明らかにした。しかし、慧海の越境を探る旅は資金に乏しく、決して恵まれたものではなかった。まさに河口慧海の苦闘に劣らず、様々な苦難を乗り越えてたどる長い道のりであった。2019年にチベット側を踏査した。河口慧海のチベット潜入経路の解明は「自分で蒔いた種だから、自分で刈り取る」と言って、根深誠は納得するまで続行するつもりだ。併せて映像化も企てている。
ちなみに、NHKのアナウンサーとして活躍した宮田輝氏は河口慧海の姪婿で、明治大学校友同志という不思議な縁があった。
著書 – 遥かなるチベット~河口慧海の足跡を追って
- 『遥かなるチベット~河口慧海の足跡を追って』(山と溪谷社、1994年10月発行)
この本により根深は1995年、「第4回JTB紀行文学大賞」を受賞する。
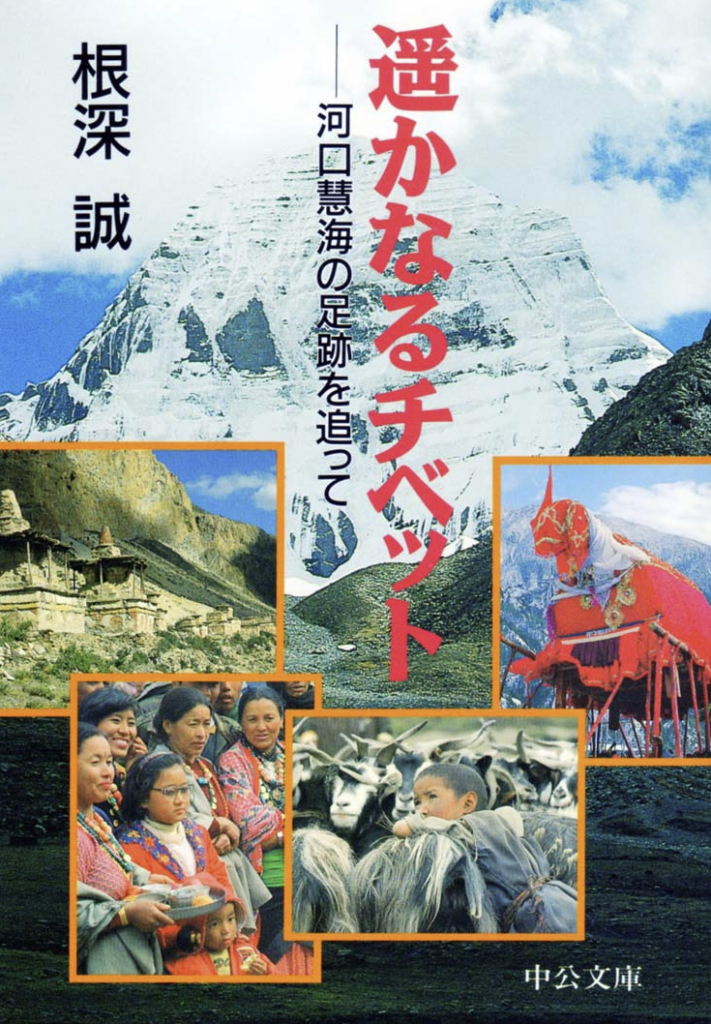
ヒマラヤ登山をサポートしたシェルパ民族の研究
ネパールに何度も足を運んだ根深誠は、人懐こい性格もあり、サポートしてくれるシェルパと胸襟を開いて付き合った。1994(平成6)年暮れ、ダージリンに行った根深は、「ダキ・バブ」の愛称で親しまれる老シェルパのアン・ツェリンと出会う。彼は初期のヒマラヤ登山に従事し、1924(大正13)年にイギリスの第3次エベレスト隊に雇われ、それから10年後の1934(昭和9)年にはドイツのナンガ・パルバット隊に参加し、遭難から奇跡的に生還したただ1人のシェルパであった。1923年、エベレスト山頂へ向かうマロリーとアービンの姿を、最後に見届けたシェルパでもあった。数々のドラマチックな体験をした彼から話を聞くに及び、“シェルパ”という民族に心惹かれ、彼らのルーツに興味を抱くようになる。
シェルパは“東の民”と呼ばれ、ネパール北東部の高地が故郷の、チベット系少数民族の一つである。20世紀に入り欧米隊のヒマラヤ登山が始まると、高地に順応した身体能力を買われ、高所ポーターとして雇われていった。その後、登山技術を磨いた彼らは案内人としても頭角を現わし、登山隊やトレッキングのガイドとして重要な役割を担った。1930年代から50年代にかけ、ヨーロッパの各国がヒマラヤ高峰の初登頂に国家の威信を懸け競い合う時代になると、その登山史に名を残す初期シェルパたちが大いに活躍する。
そこで根深は、登山隊の裏方として数々の活躍を見せ、また、悲運にも遭難や事故で命を落とした彼らの立場や境遇からそのルーツを探った。世界の登山史に数々の足跡を残すシェルパたちの実生活は、寒冷な高地では農業が厳しいため、貧しさを補う現金収入を求め、生命の危険を懸けて辛いポーターやシェルパの仕事に従事した。その一方で、不安を抱えながら夫や父、息子の帰りを待つ家族たちの暮らしにも目を配った。ネパールで取材、調査を重ねながら、シェルパにとってヒマラヤ登山はなんだったのか、彼らのヒューマン・ヒストリーを追い求めた。
こうしてヒマラヤ登山に関わったシェルパを4年かけ取材し、ヒマラヤ登山の黄金時代における光と影、さらに登山形態が多様化する時代を懸命に生きる姿を自著に綴った。
著書 – シェルパ~ヒマラヤの栄光と死
- 『シェルパ~ヒマラヤの栄光と死』(山と溪谷社、1998年9月発行)
謎の雪男(イエティ)の正体を求めて
老シェルパのダキ・バブと会ったとき、イギリスの第1回雪男探検隊に参加した際、「こういう奴を探してくれ」と渡されたハガキ大の用紙を見せてくれた。ポストカードのようなものに、毛むくじゃらのキングコングのような二足歩行の生き物の姿が描かれていた。根深誠は、エベレストに挑んだイギリスが本気で探そうとした“雪男の正体”に強く心を惹かれた。
1999(平成11)年4月、彼はシェルパのアヌー(1975年チューレン・ヒマール登山隊と1981年エベレスト西稜登山隊のサーダー)と2人で、雪男調査のためランモチェ谷に入り、村人たちから雪男にまつわる伝承や目撃証言などの聞き取りを開始した。
それから3年後の2002(平成14)年夏、解禁になったガウグリ峰の登山許可を取得、根深を隊長にシェルパ1名、コック1名、馬方1名から成る「根深誠・雪男探検隊」は、ムスタンの奥地にあるダモダールクンドに入域する。通過する村々で河口慧海にまつわる情報のほか、雪男に関する資料や言い伝えなどを精力的に取材して歩いた。また、無名峰にも登っている。
根深の調査によると“雪男”と言われてきた動物は、シェルパ語では「イエティ」と言うが、国や地域によって異なっていた。ブータンやシッキムでは「メギュ」、チベットのラサやチャンタンでは「テモ」、東チベットでは「メテ」、ネパールでもムスタンやトルボでは「メテ」と、呼称はまちまちであった。ゴーキョに行く途中にあるマチャルマ谷の放牧地で、少女時代にイエティに襲われたという、クムジュン在住の婦人にインタビューを試みる。また、チベットから移住したラマ(高僧)に聞いたり、クーンブ地方の古老の間で伝わる噂話などの聞き取りも続けた。
その結果、根深はイエティ(雪男)をヒマラヤン・ブラウンベア(チベット・ヒグマ)の仲間の動物と結論付けた。WWF(世界自然保護基金)ネパール委員会も認知し、このヒグマの足指は5つに分かれ人間の足にも似ており、マーモットを餌にしていることが分かった。どんなテーマでも、その深層まで探ろうとする根深誠の“現場主義”には頭が下がる。「登って、読んで、書く」この三拍子揃うことが登山者としての神髄であり、現役時代に明治の山岳部で培われた、と根深は話す。
著書 – イエティ~ヒマラヤ最後の謎 “雪男”の真実
- 『イエティ~ヒマラヤ最後の謎 “雪男”の真実』(山と溪谷社、2012年7月発行)
ヒマラヤ奥地での架橋事業
研究・調査というテーマから逸脱するが、根深誠が取り組んだ事業として紹介する。ネパールの北西地方に、辺境の地として知られるトルボ地方がある。さらにその奥地の標高4300mにツァルカという村があり、河口慧海の調査でたびたび訪れた根深は、簡素な木橋が増水のたびに流失し、毎年のように死者が出たりするので「頑丈な橋が欲しい」という村人たちの悲願を知る。そこで村人の安全な生活のため、橋を架ける事業に乗り出した。
2002(平成14)年から架橋プロジェクトが動き出す。翌年3月、発注した鉄橋ができ上がったものの、橋本体の重量は約5t、橋脚を造るセメントや鉄骨など資材が約5tで総重量が10tとなり、どうやって工事現場まで運ぶかが大きな問題となる。当初、陸路での輸送を考えたが、最大の難所は峠越えで、鉄材が峡谷の険路につかえて転落の危険があった。しかし、空輸による費用は600万円と高額になることから、考えにはなかった。
故郷・青森の支援者から780万円の資金を提供してもらったものの、資材の空輸までは想定せず、窮地に追い込まれる。このときネパールの日本大使館(神長善次・特命全権大使)が強い関心を寄せていた。あるとき大使館から根深に「草の根・人間の安全保障無償資金協力」(草の根レベルの、住民に直接裨益する比較的小規模な事業に必要な資金を供与するもの。以下「草の根無償」)援助の申し出があった。一度この申し出を断ったが、資材の空輸で資金不足に陥り、背に腹は替えられないと申請した。
日本大使館と幾度か協議を重ね、ネパール側の代表を交えて「ツァルカ村橋梁建設委員会」を組織する。結果、危険が伴う陸路からの輸送をやめ、安全確実にヘリコプターで資材を空輸することに決めた。日本大使館は7月下旬、「草の根無償」の申請を受理、10月20日、資金供与が締結され、架橋プロジェクトに弾みが付いた。しかし、この年は輸送問題の解決に追われ、またも架橋計画は達成されなかった。
ツァルカ村での架橋計画が3年目に突入した2004年春、カトマンズの銀行に「ツァルカ村橋梁建設委員会」の名前で口座を開設する。やがて「草の根無償」の供与金2万4200$(当時のレートで約300万円)が振り込まれた。5月1日、カトマンズの工場で鉄橋を分解し、トラックに積み込んだ。この10tの荷物を200㎞離れたポカラまでトラックで輸送し、そこからネパールに1機しかないロシア製の大型ヘリコプターで、8回に分けて空輸した。ヘリコプターの着陸地点は、ツァルカ村の住人が「大川」と呼ぶ川の左岸にある河原で、そこから工事現場まで資材を運んだ。その後、村中の人々に組み立てを手伝ってもらい、6月末、ようやく架橋工事は完了した。

3年がかりでツァルカ村の川に架けた鉄橋は、長さ22mの橋である。根深誠の熱い想いで完成した小さな橋は、日本とネパールを結ぶ大きな“友情の架け橋”となった。
著書 – ヒマラヤにかける橋
- 『ヒマラヤにかける橋』(みすず書房、2007年4月発行)
(株)イブカ(IVCA)制作による同名の映像作品もある。
この記事を書いた人

鳥山 文蔵
- 昭和49年卒部
- 日本山岳会宮城支部 会報・編集出版委員会