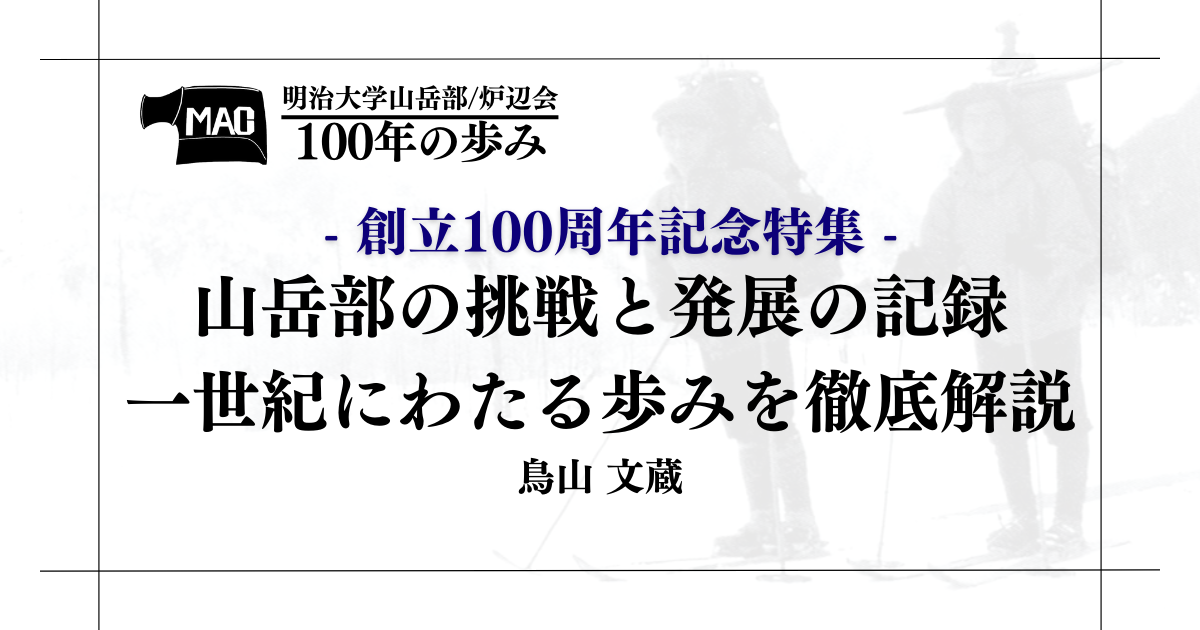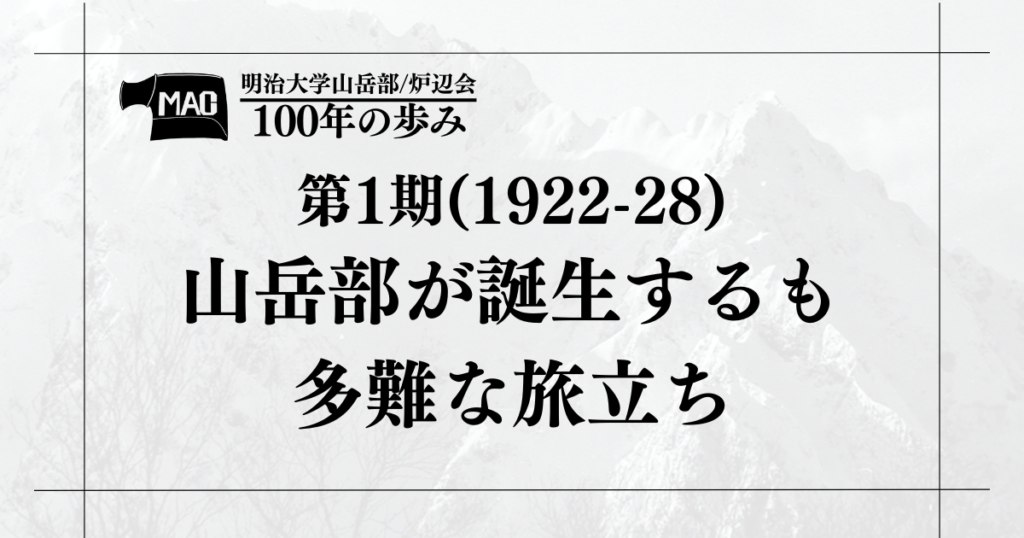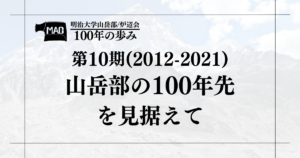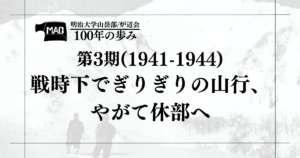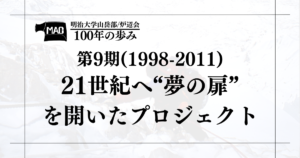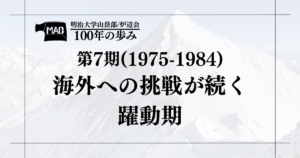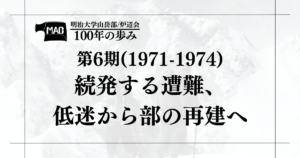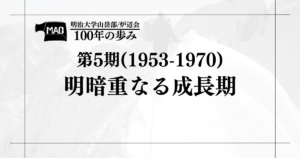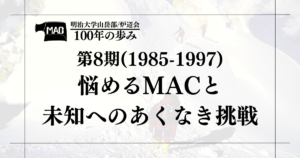この記事では、明治大学山岳部がどのようにして誕生し、発展してきたのか、その背景や出来事を詳しく解説します。創設期から現在に至るまで、山岳部が歩んできた軌跡を辿りながら、その魅力と挑戦の歴史に迫ります。明治大学山岳部の歴史を深く知りたい方にとって必見の内容です。
明治大学山岳部について
明治大学山岳部は、予科山岳会とスキー倶楽部の統合により、1922年(大正11年)に創設されました。創部当初から部員たちは目覚ましい活躍を見せ、白馬岳の積雪期初登頂や剱岳・八ッ峰の完登を達成しました。1936年(昭和11年)には、小国達雄と人見卯八郎が前穂高岳北尾根Ⅳ峰の東南壁に「明大ルート」を開拓し、戦前には輝かしい業績が数多く記録されています。また、1940年(昭和15年)には台湾での登山を実現し、初の海外遠征を成功させました。この時期には、スキー部とスケート部が山岳部から独立しています。
戦後は、大塚博美を中心に厳寒期の穂高連峰登山に挑みました。大塚は1954年と1956年、日本山岳会マナスル登山隊に参加し、8000m峰への登頂ルート開拓に貢献しました。しかし1957年(昭和32年)、白馬鑓ヶ岳で二重遭難事故が発生し、明大生3名と千葉大生2名が命を落としました。この悲劇を契機に、山岳部とOB会(炉辺会)は『遭難の実態』(1964年)を編纂し、遭難対策の強化に努めました。
1960年(昭和35年)には、明治大学創立80周年記念アラスカ遠征を行い、日本人として初めて北米大陸最高峰のマッキンリー(現デナリ、6190m)に登頂しました。1965年(昭和40年)には初のヒマラヤ遠征を実施し、ゴジュンバ・カンⅡ峰(7646m)に初登頂。さらに、植村直己がエベレスト登頂を果たしました。その後、植村は各大陸の最高峰に挑戦を続け、世界初の五大陸最高峰制覇を達成しました。
1970年代に入ると、若手OBがヒマラヤ遠征を活発化させ、1975年にチューレン・ヒマール(7371m)、1977年にヒマルチュリ(7893m)、1978年にはアンナプルナ南峰(7219m)への挑戦を次々に成功させました。同年、植村は北極点到達とグリーンランド縦断を成し遂げ、世界的な冒険家として名声を確立しました。1981年(昭和56年)には明治大学創立100周年を記念したエベレスト遠征を実施しましたが、頂上まであと98mの地点で断念しました。1984年(昭和59年)、植村が厳冬期のマッキンリー単独登頂に成功しましたが、その直後に遭難し、救援隊が派遣されるも発見には至りませんでした。
平成に入ると、部員数は減少傾向にありましたが、1999年(平成11年)には高橋和弘と大窪三恵が海外合宿を実施。インド・ヒマラヤのガングスタン(6162m)への登頂に成功しました。この成果を受け、2001年(平成13年)から創部80周年記念ドリーム・プロジェクトを始動。8000m峰14座の登頂を目標に掲げ、ガッシャーブルムⅠ峰(8068m)・Ⅱ峰(8035m)、ローツェ(8516m)、アンナプルナⅠ峰(8091m)の4座を登頂するという快挙を成し遂げました。
また、2008年(平成20年)には天野和明がインド・ヒマラヤのカランカ(6931m)北壁を登頂し、日本人初の「ピオレ・ドール(金のピッケル賞)」を受賞しました。
2022年(令和4年)には山岳部創立100周年を迎えましたが、部員数の減少が続く中、現役とOBが協力して活動を維持しています。今後も「炉辺の火」を絶やさぬよう、さらなる高みを目指し挑戦を続ける決意を新たにしています。
詳説 – 明治大学山岳部
以下の記事群は、機関誌『炉辺11号』の「明治大学山岳部/炉辺会100年の歩み」をウェブコンテンツとして掲載したものです。
-

第1期(1922-28年) 山岳部が誕生するも多難な旅立ち
関東大震災と設立者・米澤の急逝 1922(大正11)年6月16日、馬場忠三郎と磯部照幸が立ち上げた「予科山岳会」に、米澤秀太郎や北畠(旧姓:新田)義郎らの「スキー倶楽部」が合わさり、「明治大学山岳会」が誕生する。このとき学友会の委員であった米澤は、「山岳部設立趣意書」を執筆し、山岳部は学友会体育部の補助部として産声を上げた… -


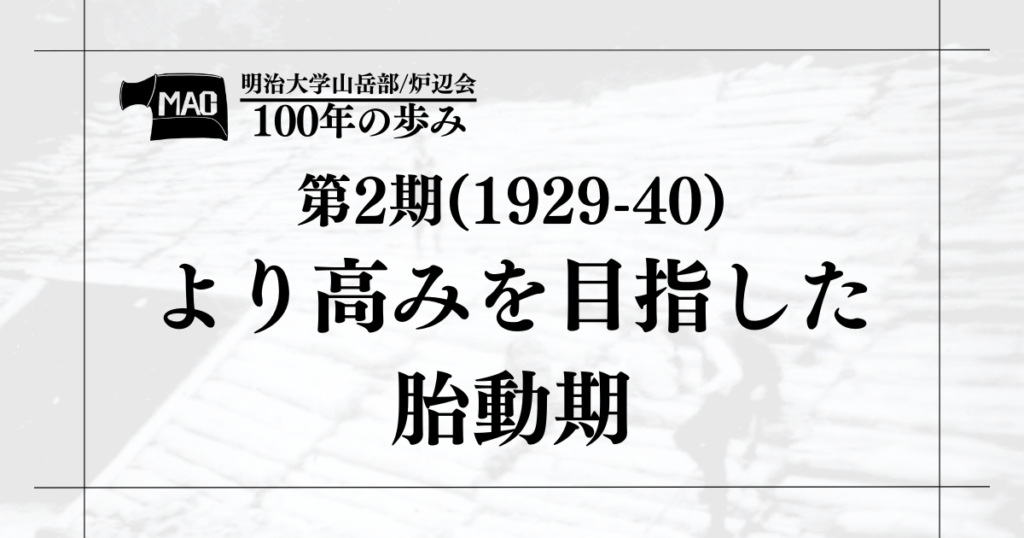
第2期(1929-40年) より高みを目指した胎動期
第2世代の登場で新たな挑戦 昭和初期までに北アルプスの主な峰々は踏破され、各大学山岳部はより厳しい積雪期および厳冬期登頂にしのぎを削り、さらに困難な縦走の挑戦へと切磋琢磨する時代に入った。こうした最中の1929(昭和4)年11月、明大、早大、法大、日大など29校が加盟する関東学生登山連盟が結成され、大学山岳部同士の連携が図ら… -


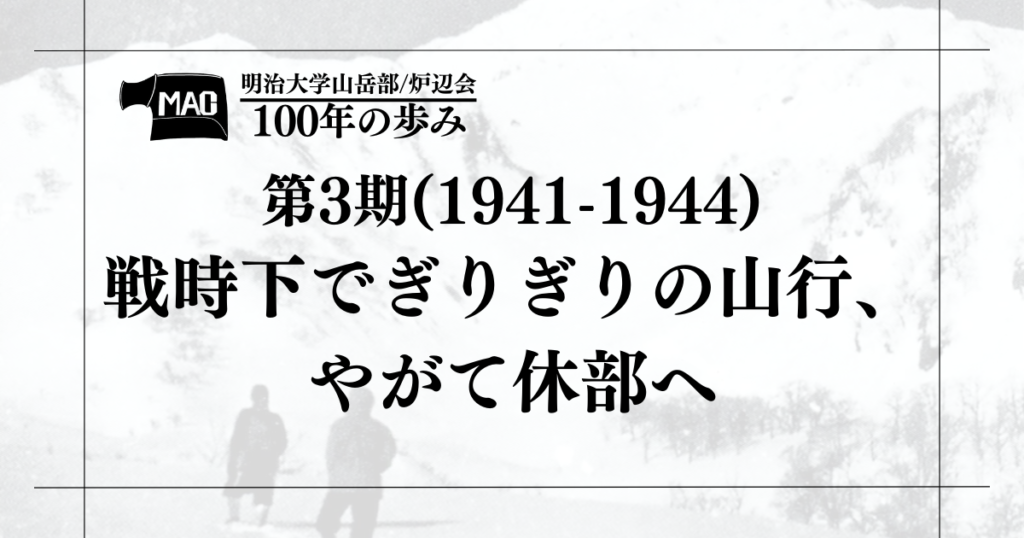
第3期(1941-1944年) 戦時下でぎりぎりの山行、やがて休部へ
戦場に散った山仲間たち 終戦から77年の歳月が流れ、悲惨な戦争体験を知る世代は鬼籍に入ってしまった。機関誌『炉辺』や会報「炉辺通信」に、多くの先輩たちが戦時下の山岳部について原稿を残している。1941(昭和16)年から終戦(1945年)までの5年間は、暗い谷間の時代となる。 41年を迎えた3月、松永豊をリーダーに部員13名は、八方尾根… -


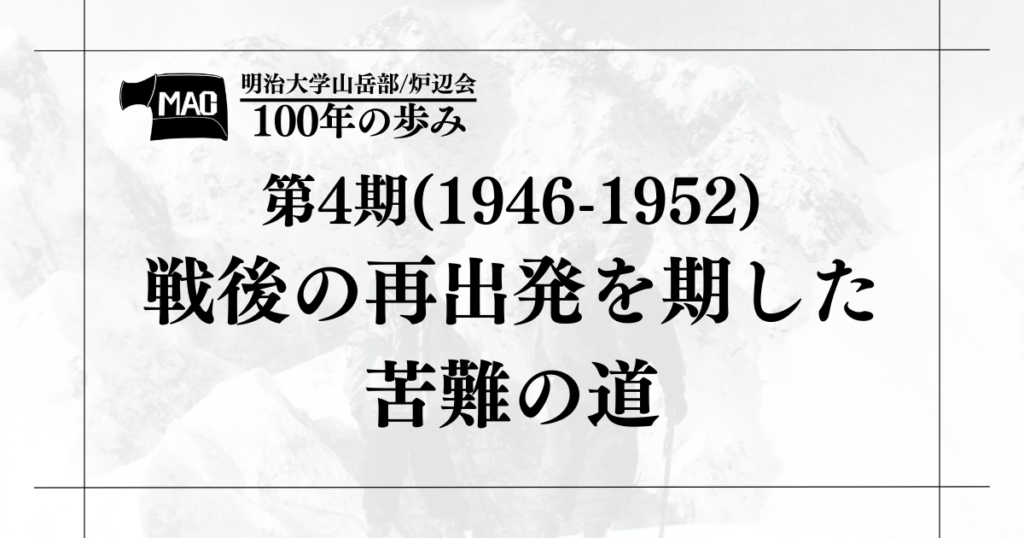
第4期(1946-1952年) 戦後の再出発を期した苦難の道
終戦を経て山岳部再建へ 1945(昭和20)年8月15日、長い戦争がようやく終わった。しかし、授業は再開できる状態ではなく、戦地から、また勤労動員先から軍服姿の学生が戻ってくるだけだった。在京部員の中には空襲で家もなくなり、ひと握りの米とひと袋のイモを求めて生活するのが精一杯という有り様だった。やがて少しずつ部員が部室に集ま… -


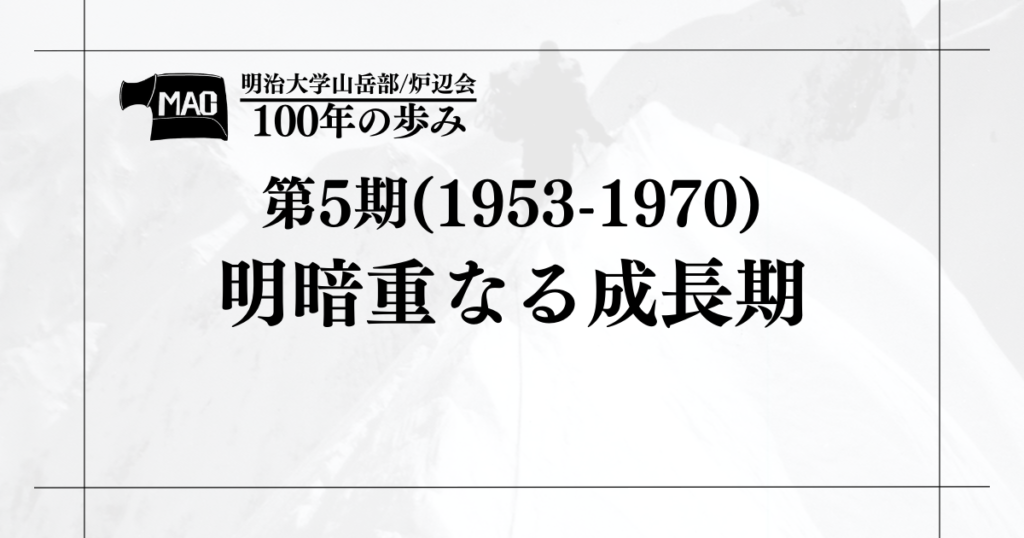
第5期(1953-1970年) 明暗重なる成長期
未曾有の白馬二重遭難、続く1年生の死亡事故 世の中が落ち着きを見せ始めた1953(昭和28)年4月、第10代の山岳部長として三潴信吾先生が着任する。この年の主将・中村雅保は極地法一辺倒から新たな目標を模索する。冬山合宿は横尾尾根からの極地法に加え、滝谷はじめ北鎌尾根・独標往復など岩稜登攀に挑んだ。 そのころ、日本人の目は世界… -



第6期(1971-1974年) 続発する遭難、低迷から部の再建へ
活動方針に揺れる山岳部と連続遭難 1960年代半ばから大学紛争でキャンパス封鎖が頻繁になり、部室での合宿準備ができない状況となる。そのころ日本の登山界では社会人山岳会の台頭が著しく、大学山岳部は沈滞化を余儀なくされていた。こうした風潮を打破すべく、MACは1966(昭和41)年度から「団体から個人へ」のスローガンの下、個々の力を伸… -


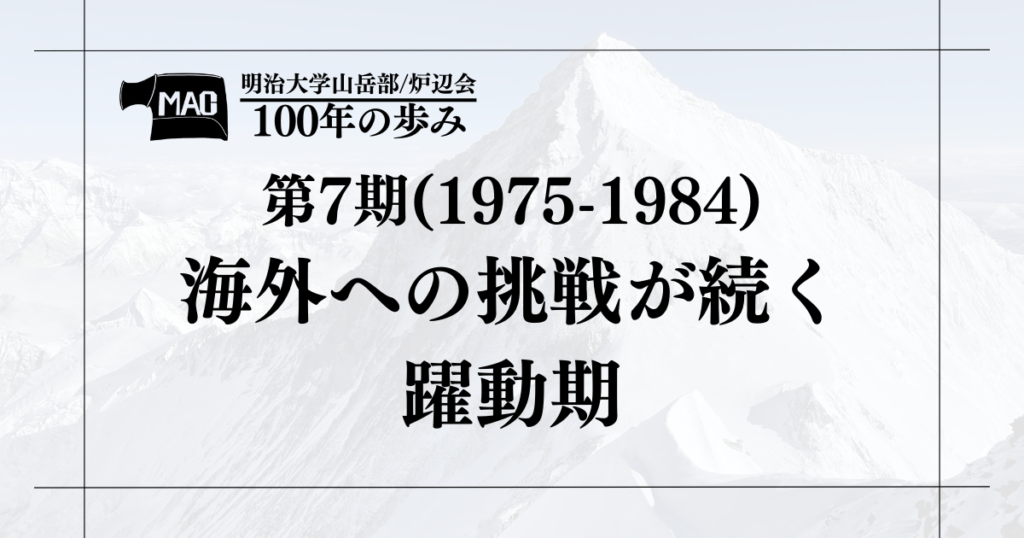
第7期(1975-1984年) 海外への挑戦が続く躍動期
大学創立100周年記念事業で「3M作戦」 1975(昭和50)年は、ゴジュンバ・カン遠征以来10年ぶりのヒマラヤ遠征で幕を開ける。それは世界最高峰のエベレストに向けての起点ともなった。 最大の鍵は、大学創立100周年事業となる世界最高峰エベレストの登山許可である。炉辺会はネパール政府に1980(昭和55)年のエベレスト登山許可を申請しよう… -


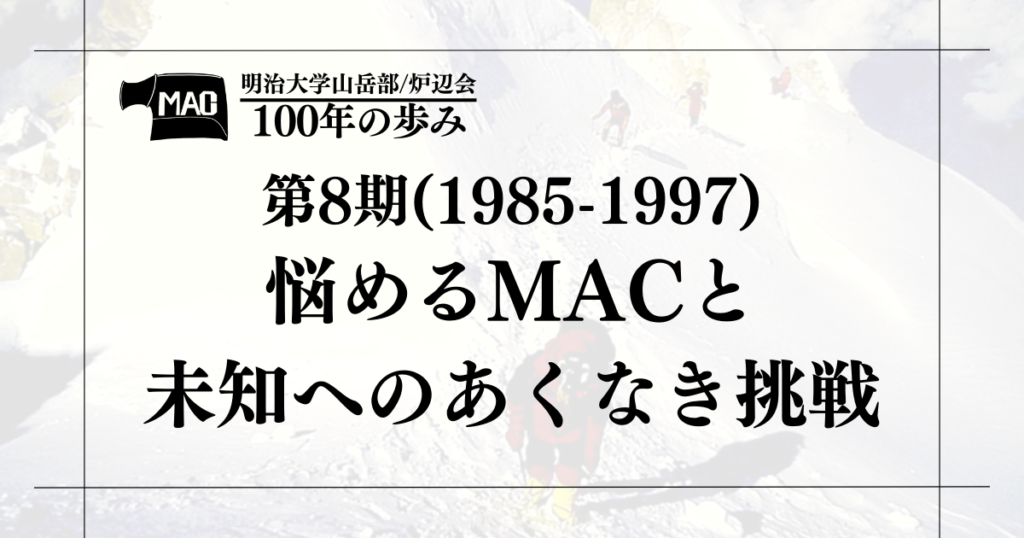
第8期(1985-1997年) 悩めるMACと未知へのあくなき挑戦
部員減少で学年断絶 昭和60年代に入っても慢性的な部員不足が続き、山岳部の前途には光明が見えないまま推移した。1985年(昭和60年)度の主将・山本篤は、自覚を促す活気あるクラブ作りに取り組んだ。明るい話題としては、11月に日本山岳会学生部のマラソン大会で団体戦と個人戦の双方で優勝を飾り、重苦しい雰囲気を吹き飛ばした。 続… -


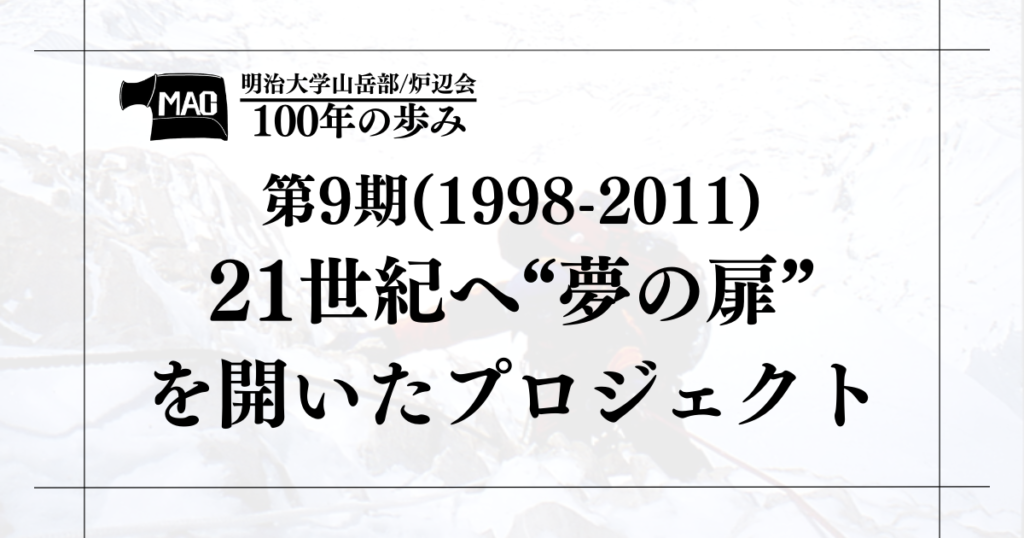
第9期(1998-2011年) 21世紀へ“夢の扉”を開いたプロジェクト
夢を育み、風を起こした「ドリーム・プロジェクト」 1998年(平成10年)4月、第9代炉辺会長に平野眞市が就く。明大マナスル遠征から2年が過ぎた1999年夏、早川敦隊長、加藤慶信、森章一の明治大学インド・ヒマラヤ登山隊は、未踏峰ナンガール・チョティ(6094m)を目指した。しかし、大きな雪庇が張り出す稜線に苦しみ、北峰手前の6000m地… -


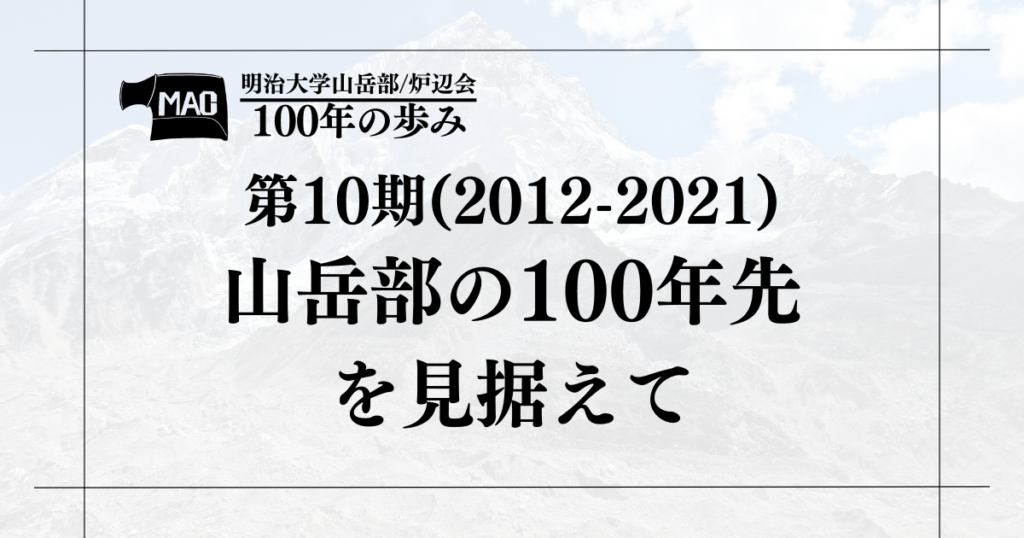
第10期(2012-2021年) 山岳部の100年先を見据えて
少数精鋭で踏ん張る山岳部と炉辺会の世代交代 2012(平成24)年5月、駿河台リバティタワーで創部90周年記念祝賀会が開かれた。 この年、主将の宮津はスケジュール管理を徹底し、合宿の合間に“準合宿”を挟み、目的別のきめ細かい山行で集中力を切らさなかった。これが新人の残留につながる要因の一つとなった。 2013(平成25)年度は新人4名…
この記事を書いた人


鳥山 文蔵
- 昭和49年卒部
- 日本山岳会宮城支部 会報・編集出版委員会