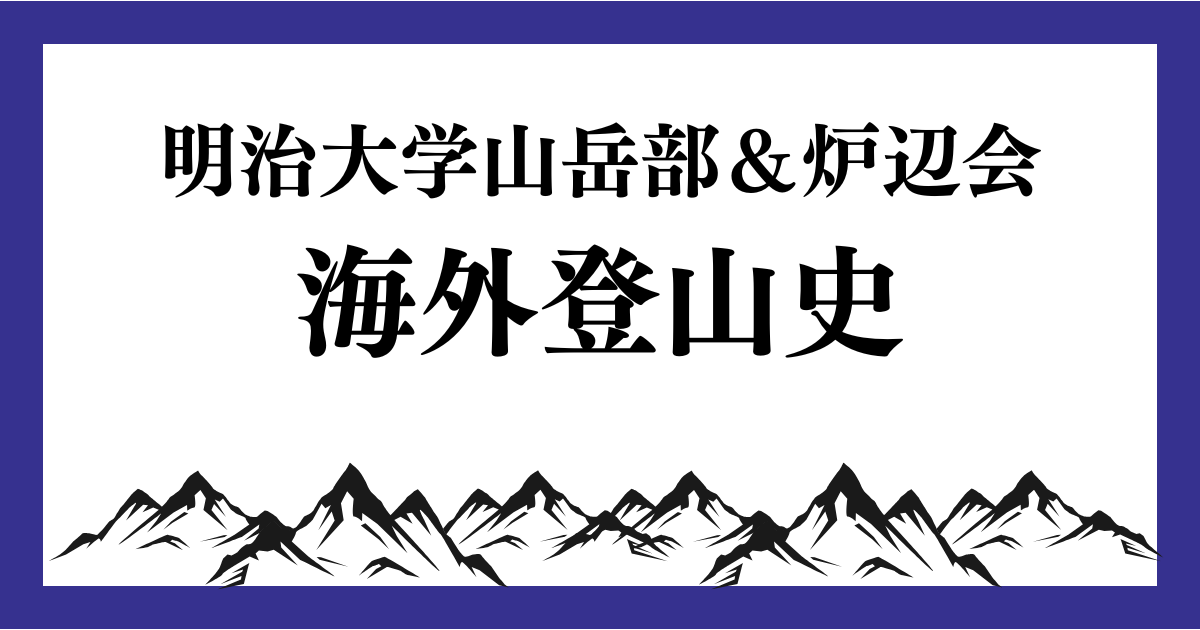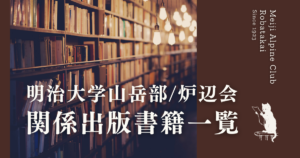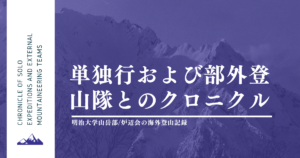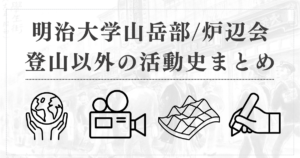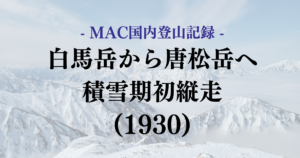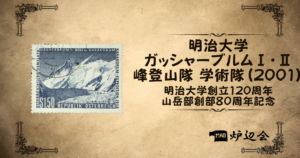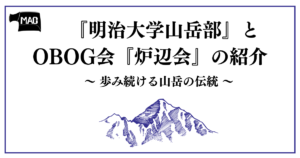海外遠征の足跡を振り返ると、20世紀と21世紀にそれぞれ大きな山場があった。一つは本学創立100周年に向け、世界最高峰エベレストに単一大学として初めて挑んだ「 3 M作戦」。もう一つは21世紀の初頭を飾った「ドリーム・プロジェクト」で、いずれも“オール明治”の底力をいかんなく発揮した。
また、学生主体の海外合宿をはじめ、日本山岳会やほかの登山隊に数多くの学生やOBが参加、数々の輝かしい記録を残している。そうした中、異国の山で近藤芳春、植村直己、大西宏、加藤慶信という、 4 名もの尊い命が失われたことを忘れることはできない。ここに明治大学隊として海外の高峰に挑んだ足跡をたどってみる。
山岳部及び炉辺会による海外遠征の記録
明治大学創立60周年記念
【台湾遠征偵察隊】
期間:1939(昭和14)年7月〜8月
概要:1939年夏、山崎善郎ら3名が、翌年の積雪期登山に備えて台湾で偵察を行った。イザワ山から次高山、新高山、合歓山などを縦走し、地形や気象、人夫の状況を調査した。
【台湾遠征本隊】
期間:1940(昭和15)年3月〜4月
概要:6名編成で台湾中部の山岳地帯における積雪期登山を実施した。前年の偵察を基に計画され、新高山(玉山)など主要峰の登頂に成功した。本隊は厳しい気象と複雑な地形に対応し、積雪期の台湾登山の可能性を示した。この遠征は明大山岳部初の海外積雪期登山であり、その後の海外遠征の礎となった。
100年後の海外登山は、MACの若者たちによって、どんな挑戦が続けられていくのだろうか。これからは少人数、短期間によるアルパインスタイルが主流となり、より困難なバリエーション・クライムへと進化を遂げていくことだろう。より高いレベルの登攀が求められる時代、厳しい登攀に立ち向かった先人たちの姿を想い起こし、新たな一歩を踏み出し、自らの夢に向かって欲しいと願って止まない。
この記事を書いた人

鳥山 文蔵
- 昭和49年卒部
- 日本山岳会宮城支部 会報・編集出版委員会