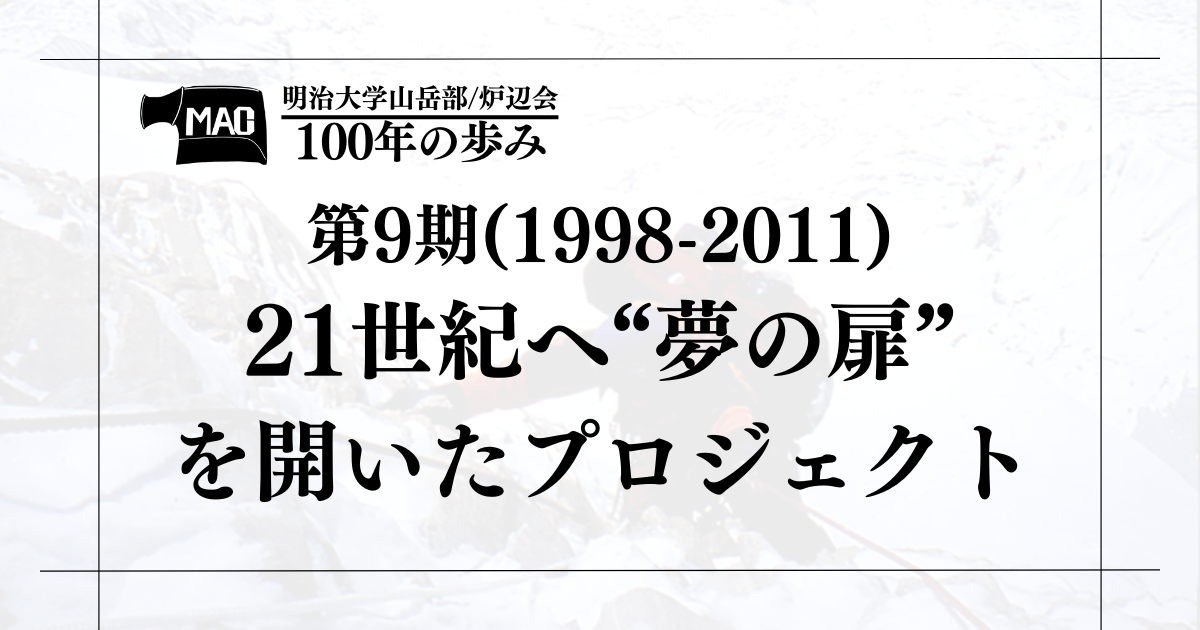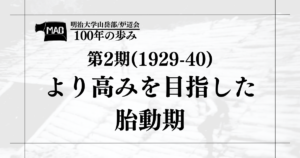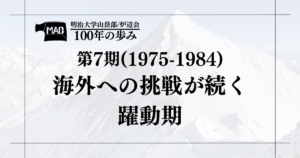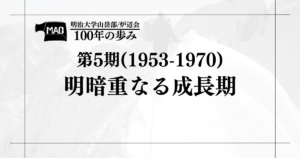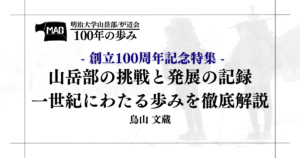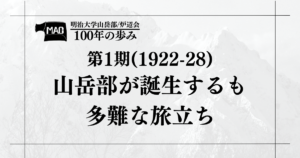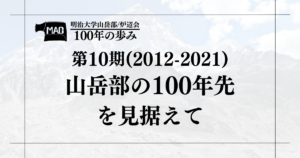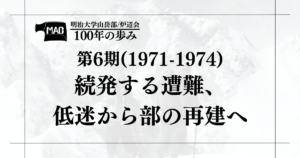夢を育み、風を起こした「ドリーム・プロジェクト」
1998年(平成10年)4月、第9代炉辺会長に平野眞市が就く。明大マナスル遠征から2年が過ぎた1999年夏、早川敦隊長、加藤慶信、森章一の明治大学インド・ヒマラヤ登山隊は、未踏峰ナンガール・チョティ(6094m)を目指した。しかし、大きな雪庇が張り出す稜線に苦しみ、北峰手前の6000m地点で無念の撤退となった。
20世紀が終わろうとするころ、新たな挑戦が生まれた。ガングスタンに登頂した高橋和弘ら若手OBから、「炉辺会員がまだ登っていないガッシャーブルムⅠ峰(8068m)とⅡ峰(8035m)に挑戦したい」と、平野会長に直訴があった。
当時、海外登山担当理事の三谷統一郎は、「ガッシャーブルムⅠ・Ⅱ峰に挑戦するなら、その勢いに乗じてローツェとアンナプルナⅠ峰の2座にも挑み、炉辺会として8000m峰14座完登を目指せるのではないか」と考えた。
1970年(昭和45年)に植村直己が日本人として初めて登ったエベレストを皮切りに、1997年(平成9年)の明大隊によるマナスル登頂までの27年間で、山岳部員およびOBが登頂した8000m峰は10座となっていた。
まだ登頂されていないのは4座であった。これを受け、海外登山委員会は残る8000m峰4座への挑戦計画を理事会に提案し、創部80周年記念事業「ドリーム・プロジェクト」として承認された。
ファースト・ステージとなる明治大学ガッシャーブルムⅠ・Ⅱ峰登山隊は、2001年(平成13年)7月10日、高橋和弘隊長、早川敦、森章一、加藤慶信、天野和明、谷川宏典の6名全員がガッシャーブルムⅠ峰の頂に立つ。
さらに、8月13日には6人揃ってガッシャーブルムⅡ峰にも登頂し、8000m峰の連続登頂に成功した。この成果は「ドリーム・プロジェクト」の幸先良いスタートとなった。

セカンド・ステージとなる明治大学ローツェ登山隊(三谷統一郎隊長)は、2002年10月3日に第1次隊の高橋和弘、森章一、加藤慶信が、続いて8日に第2次隊の三谷統一郎、天野和明、松本浩が登頂を果たし、全員がローツェ(8516m)のピークに立つ快挙を成し遂げた。
中でも天野の無酸素登頂は日本人初の快挙となり、松本は現役学生として8000m峰に登頂するという意地を見せた。登山終了後、高橋、森、加藤、天野に、チョー・オユーから合流した大窪(後姓・岩堀)三恵を加えた5名は、アンナプルナⅠ峰(8091m)の南壁ルートを偵察した。
いよいよラスト・ステージとなる2003年(平成15年)春、最後の1座であるアンナプルナⅠ峰に明治大学アンナプルナⅠ峰登山隊(山本篤隊長)が挑んだ。全員が8000m峰サミッターという最強のメンバーは、核心部であるフラット・アイロンを突破し、山本篤、高橋和弘、早川敦、加藤慶信、天野和明の5名が12時間に及ぶ激闘の末、念願のピークに立った。
個人で全座完登する時代、団体で達成する価値はあるのかという批判もあった。しかし、MACで同じ釜の飯を食った一人一人が自らの限界に挑戦し、積み重ねた結果である。これで8000m峰14座のピークに立ったのは53人となる。
なお、「ドリーム・プロジェクト」の足跡は、谷川宏典が『登頂8000メートル 明治大学山岳部14座完全登頂の軌跡』(山と渓谷社刊)として出版した。この計画で、8000m峰14座に登った隊員は24名を数える。新世紀の扉を開いた「ドリーム・プロジェクト」は、“オール明治”で掴んだ“ヒマラヤン・ドリーム”となった。

夢の先へ、アフター・ドリーム
「ドリーム・プロジェクト」以降、ガイド登山隊や公募登山隊、チームパーティ、番組取材など、さまざまな遠征に数多くのOBが参加し、「第3次ヒマラヤ黄金時代」を迎えた。
特にドリーム・プロジェクト世代とその次の世代の台頭は顕著で、少人数によるアルパイン・スタイルが主流となる「ネオ・ヒマラヤ時代」に突入した。 1999年から2011年(平成23年)までの13年間では、世界最高峰への挑戦も活発に行われた。
2005年(平成17年)春、加藤慶信は中国側から無酸素でチョモランマ(8848m)に登頂し、日本人として23年ぶりの無酸素登頂を果たした。
その3年後の2008年(平成20年)春、山本篤が隊長を務めるガイド登山隊に加藤が加わり、南東稜からエベレストに立ち、加藤は南北両ルートから世界最高峰を制覇する偉業を成し遂げた。
また、2011年春、NHKテレビ撮影班を率いた廣瀬学が南東稜からエベレストの頂に立った。
エベレスト以外の8000m峰でも、数々の挑戦が続いた。2002年夏、日中友好女子登山隊に参加した大窪三恵が南西稜から世界第6位のチョ・オユー(8201m)に登頂し、明大女性として初めて8000m峰のサミッターとなった。
2006年(平成18年)、加藤慶信と天野和明は無酸素、シェルパレスのアルパイン・スタイルでバリエーション・ルートから2つの8000m峰に挑んだ。チョ・オユーの南西壁は落石が頻発し断念したものの、西稜から登頂を果たし、さらにBCに下山して休養後、シシャ・パンマ(8027m)に向かい、北壁から頂稜に抜けて登頂した(明治大学チョー・オユー、シシャパンマ登山隊)。
また、同年山本篤と加藤は公募隊員を引率してマナスル(8163m)に登頂した。
その他の高峰にも勇敢な挑戦が続いた。2006年、天野はアマ・ダブラム(6812m)の南西稜から頂上を踏破し、翌年には三谷統一郎が平均年齢57歳のシルバー隊を率いて、パミール高原にあるムスターグ・アタ(7546m)に登頂。
同年秋には中国チベット自治区のクーラカンリ主峰(7538m)を目指す登山隊に、高橋和弘が隊長、加藤が登攀隊長として参加し、三戸呂拓也も隊員として加わった。しかし、加藤、有村哲史(早大OB)、中村進(日大OB)の3名は雪崩に遭い、還らぬ人となった(岳友たちの墓銘碑 – 加藤慶信)。
一方で、果敢なクライミングが世界から注目を集めた。天野を含むGIRIGIRI BOYS隊の3人は、2006年9月にインド・ヒマラヤのカランカ(6931m)の北壁にアルパイン・スタイルで挑み、デリケートな登攀を経て頂に立った。
この功績により、2008年「ピオレドール(黄金のピッケル)・アジア賞」、翌年に「第17回ピオレドール賞」が授与された。翌年もGIRIGIRI BOYS隊はカラコルムのスパンティーク(7027m)に北西壁のゴールデン・ピラーから挑み、3日間のビバークを経て登頂した。
こうして「ドリーム・プロジェクト」が幕を下ろした後も、個々が「マイ・ドリーム」を掲げ、ヒマラヤの高峰や未踏峰、そして難ルートに挑戦を続けていった。
21世紀に向けた山岳部と炉辺会の動き
存亡の危機を迎えた山岳部は、1995年(平成7年)度に12年ぶりに4学年が揃い、その後も学年の欠員を出すことなく部活動を続けた。しかし、平坦な道は短く、再び谷あり山ありの“茨の道”が始まった。
1998年度には、4年生1人の田中隆が主将となり、その下に3年生2名、2年生2名の上級生5名と1年生4名を加えた計9名の布陣となったが、前年の半分に減少した。この年も毎年部員が入れ替わるという大学クラブの宿命を改めて突き付けられた。
同年9月、1930年(昭和5年)から70年間使用された部室に別れを告げる会が催された。体育館地下の会場には多くのOBをはじめとする歴代の部員が集まり、部室の思い出を語り合った。
1999年度は、一度沈みかけた流れを再び取り戻す年となった。主将の天野和明は、全員縦走を目標に掲げた。春山決算合宿では、日本海の親不知から白馬岳までの積雪期縦走を実施し、1年生を含めた全員で完全踏破を果たした(栂海新道から白馬岳登頂)。
この年、明るいニュースも飛び込んできた。日本山岳会の第20代会長に大塚博美が就任。明大山岳部出身者として初めて日本登山界のトップに登り詰めたのである。
しかし、翌2000年(平成12年)度には一転して暗いトンネルに入った。この年は退部者が相次いだため、2年生の育成に重点を置く方針が取られた。それでも退部が続き、4年生が卒業すると部に残るのは2年生2人だけという危機的状況となった。監督やコーチ陣は、この状況をこれ以上見過ごすことはできないと、重い責任を受け止めた。

21世紀を迎えた01年度から、山岳部監督の若返りを図るべく高野剛が就く。しかし、就任したばかりの新監督・高野に部員数減少という難題が立ちはだかる。この年度の入部者はゼロで、3年部員の松本浩と佐々木拓磨の2人だけという、風前の灯となってしまった。
こうした深刻な事態に直面した高野監督はコーチ陣と話し合い、山岳部長の小疇尚先生にも相談。これまでのやり方では限界と、「スポーツ推薦特別入学制度」導入に踏み切る。結果、スポーツ推薦入学制度の適用が決まり、03年度から3名の推薦枠が認められた。
創部80周年を迎えた2002年、『明治大学山岳部創部80年誌~MAC・炉辺会80年の歩み』が記念誌として発行された。また、創部80周年を記念する「ドリーム・プロジェクト」が炉辺会を中心に大きな盛り上がりを見せた。
しかし、その華やかさとは裏腹に、山岳部では部員不足という暗い影が付きまとっていた。この状況を打開するため、山岳部のホームページを活用し部員募集を掲載するなど、PR活動に力を入れた。この対策が功を奏し、10名の新入部員を迎えることができた。
4年生の松本と佐々木が上級生としての役割を全て担う状況となり、コーチ陣が2人の負担軽減のためサポートに回った。2人は必死に1年生の残留に努め、なんとか4名が残留し、クラブ存続の基盤を築いた。
2003年度は、前年度とは一転して2年生が全ての役割を担うこととなった。この年、初めてスポーツ推薦入学者2名が入部し、主将の小久保裕介は年度末に「基礎の習得」を掲げ、登山の土台作りに尽力した。
2005年度には、山岳部と炉辺会のトップに人事の動きがあった。山岳部監督に海外遠征の経験豊富な山本宗彦が就任し、四半世紀にわたり山岳部を支えた小疇尚先生が退任。
第15代山岳部長に飯田年穂先生が着任した。また、5月には第10代炉辺会長に尾高剛夫が就任し、課題を抱える山岳部と炉辺会の支援に向き合った。
2006年度には8年ぶりに4学年が揃い、部内に活気が戻った。この年以降、学年欠けの状況はなくなった。2007年度は、年度計画通りの合宿を概ね実施し、年度主将の川村雄太は4学年が揃ったことを機に、長期ビジョン「剱岳周辺3カ年計画」を立案した。
しかし、実力不足でチーム力が伸びず、計画を完遂することはできなかった。この年、第11代炉辺会長に節田重節が就任。山岳部支援に尽力するとともに、創部90周年記念事業と機関誌『炉辺』第10号発刊という大きなテーマに取り組んだ。
本学創立130周年・山岳部創部90周年を記念して派遣された明治大学マッキンリー登山隊(三谷統一郎隊長)は、三戸呂拓也と川村雄太をリーダーに、学生の佐々木理人(主将)、宮津洸太郎、小林雅章、玉川翔が参加。植村直己先輩が消息を絶ったデナリ(6194m)に全員が登頂を果たした。

ここにきて、スポーツ入試への応募者がいないという陰りが見え始める。最も頼りにしてきたスポーツ入試が曲がり角に差し掛かったのか、山岳部を希望する学生が減り、新たな問題を抱えることになる。
この記事を書いた人

鳥山 文蔵
- 昭和49年卒部
- 日本山岳会宮城支部 会報・編集出版委員会