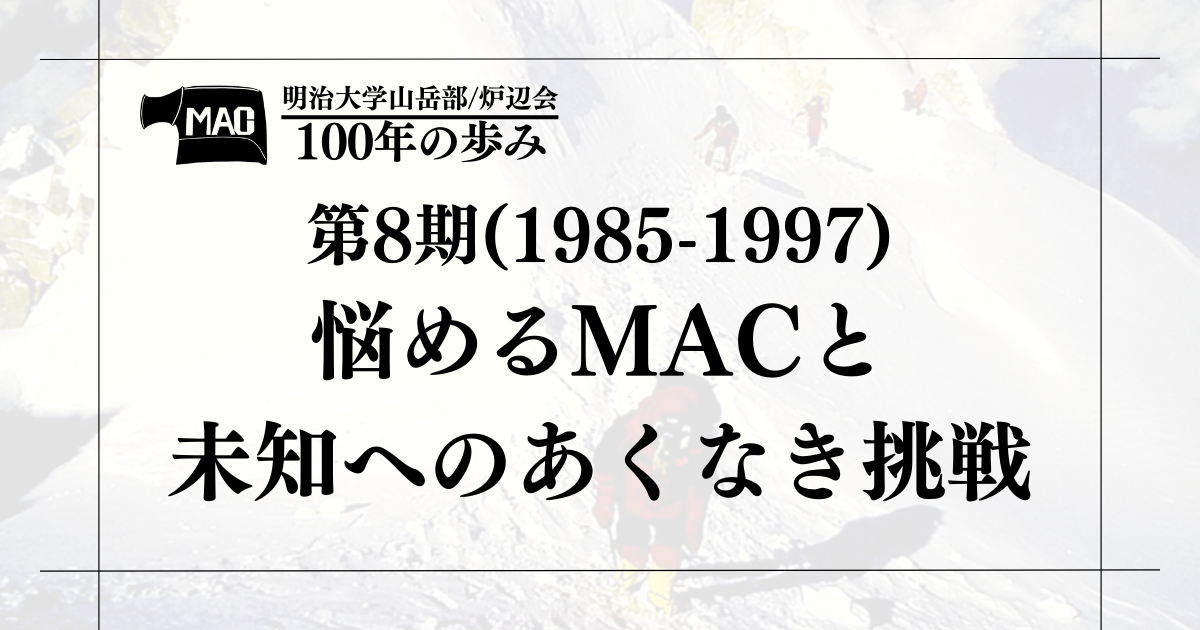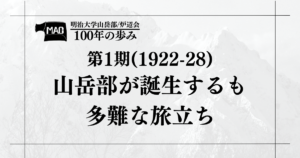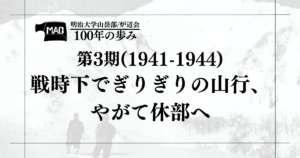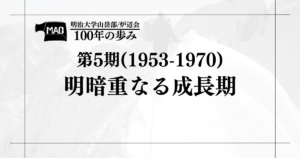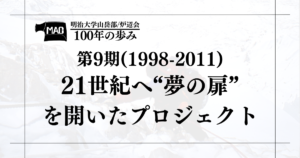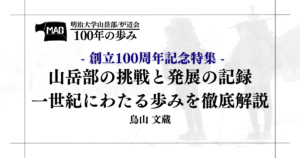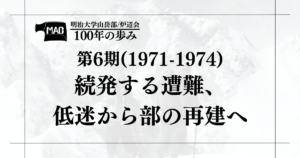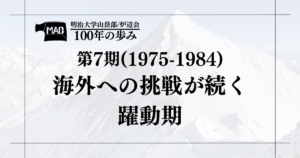部員減少で学年断絶
昭和60年代に入っても慢性的な部員不足が続き、山岳部の前途には光明が見えないまま推移した。1985年(昭和60年)度の主将・山本篤は、自覚を促す活気あるクラブ作りに取り組んだ。明るい話題としては、11月に日本山岳会学生部のマラソン大会で団体戦と個人戦の双方で優勝を飾り、重苦しい雰囲気を吹き飛ばした。
続く1986年(昭和61年)度、竹村政哉が主将を務めた年は、1年生の育成に重点を置き、新入部員9名中7名が残る成果を上げた。1987年(昭和62年)度には、4年生と3年生の2学年が断絶し、部員構成が2年生5名と新人のみとなった。そのため、主将の佐野哲也は3年間にわたり主将を務めることとなる。
この年の夏山合宿では、南アルプスの全山縦走と北岳バットレスを登攀し、基礎体力と登攀技術の習得に励んだ(南アルプス縦走と北岳バットレス登攀)。昭和最後の1988年(昭和63年)度も上級生1名が退部し、波乱の1年となった。
時代が平成に変わっても、山岳部に明るい兆しは見えなかった。佐野は主将として最後の3年目を迎え、厳冬期の剱岳登頂を念頭に部全体の底上げを図った。この年の決算合宿では、赤谷尾根縦走隊と早月尾根往復の本隊に分かれて臨み、天候にも恵まれ有終の美を飾ることができた。
1990年(平成2年)度は、リーダーとなるべき4年生が欠け、3年生2名、2年生4名、1年生4名という布陣でスタートした。主将の冨田大は、明確な目標に向かって切磋琢磨することがチーム登山の本質であると捉え、「利尻岳冬期登頂2ケ年計画」を立案。
この年、上級生は130日、1年生は80日におよぶ山行日数を達成し、近年にない積極的な活動を展開した。暗い話題が多かった中で、明るい展望が見え始める年となった。
利尻山遭難後、部の存続へ必死の努力
1991年(平成3年)度は、10年ぶりに明治大学チョモランマ峰登山隊が派遣される年となった。この年度は新入部員がゼロで、当初4名いた2年部員が相次いで退部したため、南稜からの利尻山登頂計画を東稜に変更せざるを得なくなった。
4年生と3年生4名の上級生は、利尻山での冬山合宿に向かった。入山7日目の12月28日、利尻山・東稜の鬼脇山付近で足元の雪庇が崩落し、3年部員の染矢浄志がヤムナイ沢に転落、行方不明となる(岳友たちの墓銘碑 – 染矢浄志)。
利尻山遭難後の1992年(平成4年)度は、染矢捜索の日々となった。部員は4年生の小杉秀夫と高柳昌央の2名に、新人の高橋和弘と大窪三恵を加えた4名だけとなり、3年生と2年生が不在という存亡の危機を迎えた。この状況下、通常の合宿は控え、“準備山行”という名目で細々と登山が続けられた。
翌1993年(平成5年)度には、4年生2名が卒業し、2年生2名だけが残るという創部以来最大のピンチに直面した。そこで高橋和弘と大窪三恵の2名は、必死に新人を勧誘し、8名の新入部員を迎えることに成功した。また、経験の少ない主将である高橋は、2名だけでの運営を支えるために上級生会とコーチ会を一体化し、コーチ陣には上級生の立場を担うよう協力を求めた。
合宿を進めるうちに1年生の退部が相次ぎ、最終的に3名が残るのみとなった。高橋は、部員の確保には目標となるビジョンが必要だと痛感し、2年後の夏に学生主体で海外合宿を実施するという目標を立てた。主将2年目を迎えた高橋は、インド・ヒマラヤのガングスタン(6162m)への登山申請と準備を開始。この活動により、部内に活気が戻り、久々に明るい雰囲気に包まれた。
学生の海外合宿で明るい展望
1995(平成7)年度は4年2名、3年3名、2年4名に新人4名が入部し、12年ぶりに4学年が揃った。高橋隊長率いる明治大学山岳部インド・ヒマラヤ登山隊は、部員7名にOB2名が付き添い、夏休み期間中にガングスタンに向かった。
隊員たちは8月28日と30日の2日間にわたり、ガングスタンに全員登頂を果たす。この海外合宿は、暗いトンネルが続く山岳部に明るい展望をもたらす快挙となり、参加した部員たちは21世紀初頭を飾る「ドリーム・プロジェクト」の主力メンバーに育っていった。
翌1996(平成8)年度の主将・豊嶋匡明は、日本山岳会青年部K2登山隊から帰国後、部活動に復帰。決算合宿は全員が早月尾根から剱岳に登頂し、4年2名は厳冬期のチンネ登攀に成功する(剱岳登頂とチンネ登攀)。
この年は上級生合宿を含め8合宿を実施し、合宿だけの山行日数は年間104日、個人山行と偵察山行を加えると多い部員で130日となり、全盛期に匹敵する日数となった。
1997(平成9)年度は、個性豊かな森章一、加藤慶信、関裕一の4年生が牽引する。夏山終了後、8月下旬から加藤と関がマナスル遠征に参加するため、主将の森は合宿強行を避け、個人山行に切り替えた。
こうして各年度の主将たちは、部員確保に頭を痛めながらも部全体のレベル維持、向上に全精力を傾注していった。
若手クライマーが台頭、海外での活躍続く
1985年から1997年の8000m峰マナスル登頂までの13年間は、若手OBが次から次へと世界の高峰に挑み、MACと炉辺会の底力を見せつける「第2次ヒマラヤ黄金時代」となった。この期間に8000m峰登頂者は23名、7000m峰登頂者は9名、6000m峰には14名が立ち、併せて46名ものOB・学生がファイナル・ピークに立った。中でも8000m峰は7座を制覇し、21世紀明けの「ドリーム・プロジェクト」へ大きな弾みとなった。
内訳として、エベレスト(チョモランマ、8848m)には4名(三谷統一郎、山本宗彦、山本篤、大西宏)、世界第2位のK2(8611m)には2名(山本篤、高橋和弘)、第5位のマカルー(8463m)には3名(山本宗彦、山本篤、大西宏)、第6位のチョー・オユー(8201m)には4名(三谷統一郎、中西紀夫、北村貢、山本篤)、第8位のマナスル(8163m)には8名(三谷統一郎、山本篤、廣瀬学、原田暁之、高橋和弘、豊嶋匡明、加藤慶信、関裕一)、第12位のブロード・ピーク(8051m)には1名(山本宗彦)、第14位のシシャ・パンマ(8027m)には1名(山本篤)が登頂を果たした。まさに怒涛のラッシュとなる。
その結果、8000m峰のサミッター(登頂者)になったのは、山本篤が6座、三谷統一郎と山本宗彦がそれぞれ3座、大西宏と高橋和弘がそれぞれ2座と、若手OBの活躍が目立った。
次に7000m峰では、1985年に北西稜からマッシャーブルム(7821m)に山本宗彦が登頂。1992年にはナムチャ・バルワ(7782m)に三谷統一郎と山本篤が登頂。1990年にはパミール高原のレーニン峰(7139m)に佐野哲也、コルジェネフスカヤ峰(7105m)には佐野と廣瀬学がそれぞれ登頂した。
1987年の明治大学カラコルム登山隊(山本宗彦隊長、山本篤、大西宏)は、フンザにそびえるラカポシを目指したが、ラカポシ東峰(7010m)で断念する。
翌1988年、世界最高峰を南北から交差縦走する日本山岳会の「中国・日本・ネパール チョモランマ/サガルマタ友好登山隊」に、大塚博美が副隊長、橋本清が北側(中国)隊長として参加。北側隊に三谷統一郎、山本宗彦、山本篤が、南側(ネパール)隊に北村貢、高野剛、報道班として大西宏が加わった。
1988年5月5日、北側から南側へ縦走する山田昇氏をサポートした山本宗彦は、北稜から苦しい登高を続け、チョモランマ(8848m)の頂に立った。
また、先輩植村直己の跡を追うように極点を目指す大西は、1989年、7か国による国際アイスウォーク隊に日本代表として参加。5月に北極点に到達し、植村に次ぐ日本人2人目の快挙となる。
同年10月、カトマンズ・クラブ隊に参加した三谷、山本篤、大西の3名は、南東稜から念願のエベレスト頂上に立った。
さらに続いた高みへの挑戦
炉辺会では、本学創立110周年を迎える1990年に再び世界最高峰への挑戦を行おうという機運が高まった。1991年春、明治大学チョモランマ峰登山隊は、東壁に残された最後の未踏ルートに挑んだ。カンシュン氷河から延びる悪絶なナイフリッジの下部稜線を抜け、6400mまで到達したものの、上部はあまりにも複雑で難しく、撤退を余儀なくされた。
同年、大西宏、山本篤、廣瀬学の3名は日本山岳会のナムチャ・バルワ日中合同隊に参加した。しかし、ナイプン峰(7043m)下のC4予定地へ偵察に向かった際、大西は6250m付近で雪崩に遭い、還らぬ人となった。植村直己に続き、“地球の3極”最後の南極を目前にしての悲劇であった(岳友たちの墓銘碑 – 大西宏)。
故大西宏の想いを果たすべく、佐野哲也はアンターティック・ウォーク南極探検隊に参加。1992年11月に南極大陸のパトリオット・ヒルを出発し、ティール山脈基部を経由して68日目の翌1993年1月、南極点に到達した。佐野は故大西先輩に南極点到達を報告し、その偉業を讃えた。
1997年になると、6年ぶりにオール明治による8000m峰計画が始動した。明治大学マナスル登山隊(三谷統一郎隊長、隊員7名)は、北東面からマナスル(8163m)に挑み、10月8日と9日の2日間にわたり全員が登頂を果たした。この成功により、本学OBによる8000m峰の登頂は10座目となり、「ドリーム・プロジェクト」へのプロローグとなった。

1997(平成9)年のポスト・モンスーン、10月9日、マナスル山頂へ向かう第2次アタック隊。純粋にMACメンバーだけによる初の8000m峰登山だった。
マナスル遠征後、山本篤を隊長に高橋和弘、豊嶋匡明の3名はアンナプルナⅠ峰(8091m)へ向かった。3人はアルパイン・スタイルで北面鎌ルートから挑んだが、多量の降雪と隊員の不調が重なり、6000m地点で敗退する。
数多くのOBが世界の高峰や極地に挑み、まさにMAC、炉辺会の底力と層の厚さを見せつける13年間となった。そして、来る21世紀の“夢のプロジェクト”に突き進んでいく。
この記事を書いた人

鳥山 文蔵
- 昭和49年卒部
- 日本山岳会宮城支部 会報・編集出版委員会