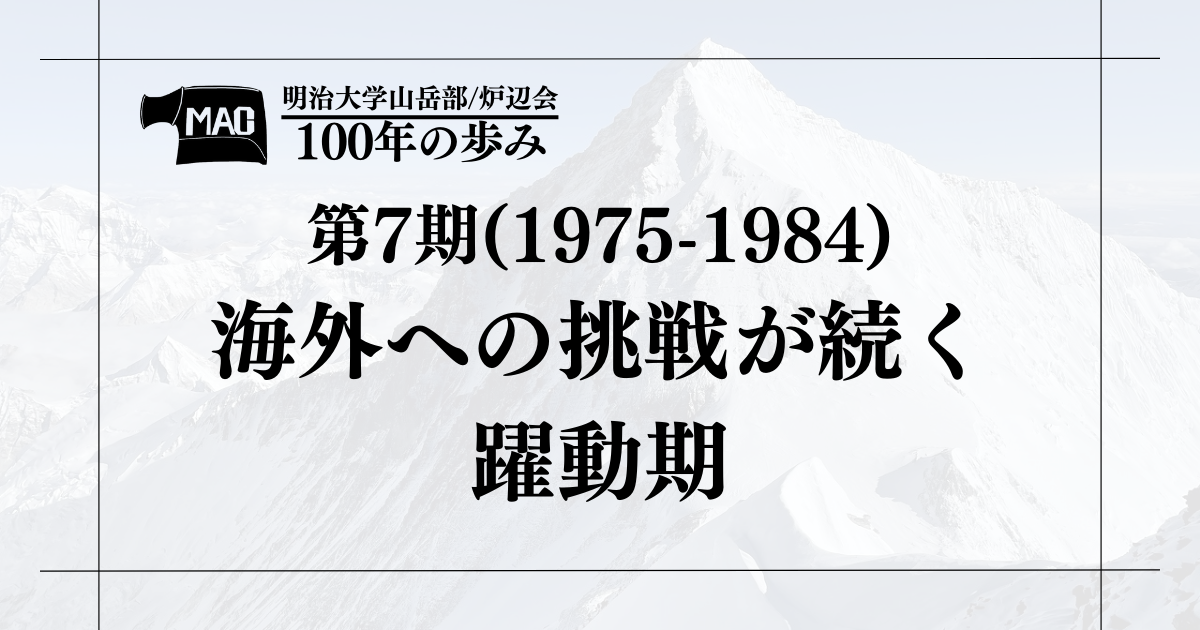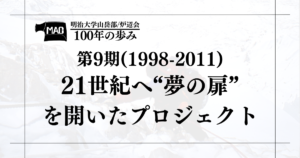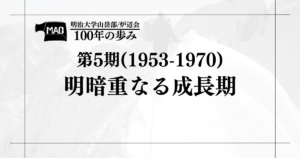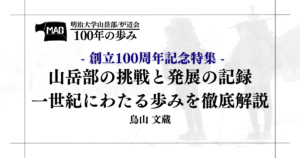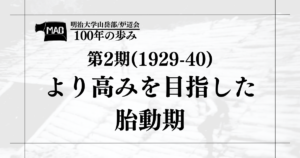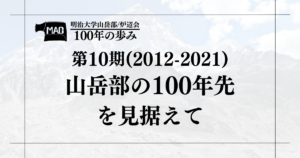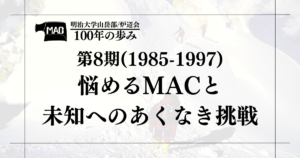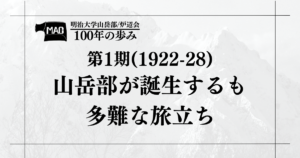大学創立100周年記念事業で「3M作戦」
1975(昭和50)年は、ゴジュンバ・カン遠征以来10年ぶりのヒマラヤ遠征で幕を開ける。それは世界最高峰のエベレストに向けての起点ともなった。
最大の鍵は、大学創立100周年事業となる世界最高峰エベレストの登山許可である。炉辺会はネパール政府に1980(昭和55)年のエベレスト登山許可を申請しようとしたところ、日本山岳会と競合になってしまう。
両者で話し合った結果、1980年の登山は日本山岳会に譲り、明大は1年遅れの1981年に申請することにした。
1975年春、チューレン・ヒマール登山隊が出発したころ、藤田佳宏は病を得て入院。彼はベッドの上で密かにエベレスト登山の基本プランを練った。
7月に外務省から公電が入り、1981年の登山許可が明治大学に下りる。これにより100周年記念事業は大きく前進することになった。
同年9月、検討会が開かれ、藤田は病院を抜け出し出席。彼自身がしたためた「エベレスト3M作戦」(3M:Mountain〈山=エベレスト南西壁〉、Money〈金=遠征資金〉、Man〈人=高所経験隊員〉)を発表した。
この“藤田ビジョン”は当時未踏ルートの南西壁から登頂を狙う計画であったが、この検討会から間もなく、イギリス隊が南西壁を初登攀してしまう。
エベレストへの前哨戦として7000m峰へ
世界最高峰に挑むには、6000~7000mの高所経験者を養成することが急務となった。
そこで若手OBに高所を経験させるべく、1975年に明治大学チューレン・ヒマール登山隊(中島信一隊長、隊員8名)を派遣し、長谷川良典と河野照行は未踏の西稜からチューレン・ヒマール(7371m)の頂を踏んだ。

翌1976年(昭和51年)春、第1次エベレスト偵察隊(橋本清隊長)に3名を派遣し、秋には次のヒマルチュリ登山隊に向け、節田重節隊長以下3名が偵察を行った。
1977年(昭和52年)、菅沢豊蔵隊長以下12名が、長大な東尾根からヒマルチュリ(7893m)に挑んだ。第2次アタック隊の近藤芳春と三谷統一郎の2人は、頂上に届かず引き返すこととなった。しかし、東壁を下降中に近藤隊員が雪庇の崩壊による氷のブロックを頭部に受け死亡し、登山活動は中止された(岳友たちの墓銘碑 – 近藤芳春)。
続く1978(昭和53)年秋、河野照行を隊長に4名がアンナプルナ南峰(7219m)に挑み、河野、宮川良雄、三谷統一郎、中西紀夫が未踏の南西稜から登頂に成功する。

こうして1975年から4年間に派遣された遠征隊は3隊、参加した隊員は23名(重複者除く)、そのうち全く初めての経験者は16名(偵察隊を除く)と、高所経験者を数多く養成した。ここに、世界の頂点を目指す態勢が整った。
単一大学チームとして初めて世界最高峰へ
この間に植村直己が厳冬期のエベレストに挑戦する計画が持ち上がり、本学創立100周年遠征とセットのプランとなる。
ところが、100周年記念事業のエベレスト計画は、登攀ルートを巡って紆余曲折があった。一度は南西壁で登山許可を取得したが、南西壁が英国隊に初登攀されたため、登頂優先という声が高まり南東稜に転進する。
その後、1981(昭和56)年春にブルガリア隊がローツェ(8516m)に挑むという知らせが入り、アイスフォールからサウス・コルまで同一ルートとなってしまった。
結局、一度決めた南東稜を諦め、日本人がまだ登っていないロー・ラからの西稜に決まる。一方、日本冬期エベレスト登山隊は翌1981年1月、早大OBの竹中昇隊員が滑落死亡する事故が起き、登山を断念する。
そして1981年春、満を持して明治大学エベレスト登山隊(中島信一隊長、隊員17名)が世界最高峰に向かった。第3次アタック隊の田中淳一と田口(後姓・齋藤)伸は、頂上まであと98mと迫ったが、体力の限界とともに時間切れとなり無念の撤退で幕を閉じる。
この一連の世界最高峰への登山で、1980年春のチョモランマ(日本山岳会)と冬のエベレスト、そして1981年春のエベレストと、わずか1年の間に3度も挑み、登頂はならなかったものの、大車輪の活躍を見せた三谷統一郎の奮闘を見逃すことはできない。
ヒマラヤへの飽くなき挑戦
世界最高峰に登頂できなかった悔しさをバネに、OBたちのヒマラヤ挑戦が本格的に始まった。とりわけエベレスト遠征以降の若い世代の台頭により、海外挑戦の流れは途切れることがなかった。
創部60周年を迎えた1982年(昭和57年)から、若手OBたちは次々とヒマラヤに挑んだ。卒業したばかりの山本宗彦は日本山岳会学生部登山隊に参加し、8月にボゴダⅡ峰(5362m)の南稜から登頂。
また、エベレストで涙を飲んだ田中淳一と三谷統一郎は高松勤労者登山隊に加わり、10月には世界第7位のダウラギリⅠ峰(8167m)に北東稜から登頂し、エベレストでの鬱憤を晴らした。
翌1983年(昭和58年)もOBたちの快進撃は続く。富山県山岳連盟隊に参加した中西紀夫は、世界第9位のナンガ・パルバット(8126m)の西壁ルートから日本人初登頂という快挙を成し遂げ、エベレストでの悔しさを晴らした。
また、日本山岳会青年部パミール登山隊に加わった山本宗彦は、7月にレーニン峰(7134m)、8月にはコミュニズム峰(現イスモイル・ソモニ峰、7495m)に連続登頂するという偉業を達成した。
さらに、カモシカ同人冬季チョモランマ・エベレスト登山隊に参加した高野剛と米山芳樹は、北壁の8100m地点まで固定ロープを延ばし、大きな貢献を果たした。
挑戦はさらに続く。1984年(昭和59年)春に派遣された日本山岳会カンチェンジュンガ登山隊には、三谷統一郎、北村貢、山本宗彦の3名が参加。アタック隊に選ばれた三谷は、カンチェンジュンガ南峰(8476m)と中央峰(8482m)を経て、世界第3位の主峰(8586m)に登頂。8000m稜線の縦走に成功するという偉業を成し遂げた。
1975年のチューレン・ヒマール遠征から、このカンチェンジュンガ登山までの10年間は、まさに「第1次ヒマラヤ黄金時代」と呼ぶにふさわしい活躍期であった。
部員減少が顕著になり、炉辺会は新体制で終身会費制を導入
軌道に乗り始めた山岳部に、部員減少という難題が浮上する。1976年度は唯一の部員となった松田研一が主将となり、部の改革に乗り出す。
彼は年7合宿制から5合宿制(春山、新人、夏山、冬富士、冬山とし、6月と秋山を廃止)とし、中身の充実を図った。この年の冬山合宿は、退部で部員数が減ったことから当初の極地法を断念した。
上級生は北仙人尾根から剱岳を経て早月尾根を下る縦走隊とし、1年部員パーティは赤谷尾根から赤谷山登頂に計画を変更した。ところが、思いも寄らぬ悪天候で救援隊を出す事態を招いてしまった(北仙人尾根~剱岳~早月尾根縦走)。
一方、76年度は炉辺会の執行部体制が従来の幹事会制度から理事会制度へ移行し、また、同年度から炉辺会の安定的な運営を図る目的で「終身会費制」が導入され、転換点となった。
77年度主将の伊藤彰則は、3年部員がいないため2年部員の強化を図った。その年の冬山合宿は、上級生隊が前穂高岳・北尾根から槍ヶ岳への縦走に向かったが、予定より日数を費やしたものの敗退に終わる。
続く78(同53)年度は4年部員がいないため、3年の中西紀夫が主将となる。中西主将が4年になった79年、1年生の松本明が夏山合宿で急死する事故が起きる(岳友たちの墓銘碑 – 松本明)。
コーチ会は7年ぶりに起きた死亡事故を受け、急遽9月合宿を行い、登山を基本からやり直した。しかし、冬山合宿を前に2年生と1年生の退部が相次ぎ、当初3つの尾根から剱岳に集中登山する冬山計画は、大幅に縮小せざるを得なくなる。このころから途中退部や入部ゼロが頻発し、変則的な学年構成が増えていく。
田口(後姓:斎藤)伸が主将となった1980年度の冬山合宿では、赤谷尾根から剱岳を経て早月尾根縦走と、早月尾根から極地法で剱岳登頂を成功させた。しかし、縦走隊の計画変更や凍傷などの問題を残して合宿を終える。
エベレスト本番となった1981年度には、新人4名が入部し、総勢11名でスタートした。学生2名(高野剛と松村定樹)が登山隊に選ばれた。また、コーチ5名のうち3名(中西紀夫、佐久間一嘉、田口伸)が参加するため、前年に卒業した若手OBが臨時コーチとなり、学生の指導に全力を挙げた。
この年は2年生1名が退部してゼロとなり、1年生3名も去り、結果として4年生5名、3年生1名、1年生1名という部員構成になってしまった。こうして部員減少という現実は、見逃すことのできない問題として重くのしかかってきた。
この年、11年にわたってお世話になった木村礎先生から小疇尚先生に山岳部長のバトンが手渡される。翌年に木村先生は第4代の炉辺会長に就任し、引き続きOB会のお世話をいただいた。この年開催の炉辺会定期総会で、理事会を統括する責任者として「理事長」職が設けられ、初代理事長に中尾正武が就く。
1982年度から1984年度までの3年間も、部員減少に歯止めは掛からなかった。1982年度の主将・米山芳樹は、新しいアイデアを駆使し新人獲得に乗り出す。まず統一したポスターでアピールし、さらにパンフレットを作成して山岳部のある高校に郵送した。入部者は6名にとどまったが、ビジュアルでアプローチした新たな試みは高く評価された。
翌1983年4月に入った新人部員は10名を数えたが、10月の積雪期を迎える前に4名に減ってしまった。主将の上田哲也は部員の歩留まりの悪さに頭を痛めた。それでも冬の決算合宿では前穂高岳・北尾根から前穂高岳に登頂し、実力向上に力を注いだ(北尾根から前穂高岳)。
翌1984年に入ると、信じられない悲報が届く。2月12日、デナリに冬期単独初登頂を果たした植村直己が、翌日、行方不明になったというニュースが飛び込んできた。
炉辺会は第1次、第2次と捜索隊を派遣した(岳友たちの墓銘碑 – 植村直己)。そのため監督はじめメンバーが現地に赴いたことから、部活動は年度の滑り出しから空白期間が生じてしまった。主将に就いた松尾英之は、冬山合宿で剱岳・小窓尾根からチンネ登攀を計画したが、合宿前に1年生全員が退部し、またチンネ登攀時に3年部員がスリップ事故を起こし、部の脆弱さを露呈してしまった。
このように、リーダー陣は部員が減少する山岳部の中で、ステップアップさせるべき部活動の難しさに悩み、監督とコーチ陣は部員たちをサポートする指導に苦慮した。具体的な部員確保策が講じられないまま平成を迎えると、ますます危機的な状況に追い込まれていった。

この記事を書いた人

鳥山 文蔵
- 昭和49年卒部
- 日本山岳会宮城支部 会報・編集出版委員会