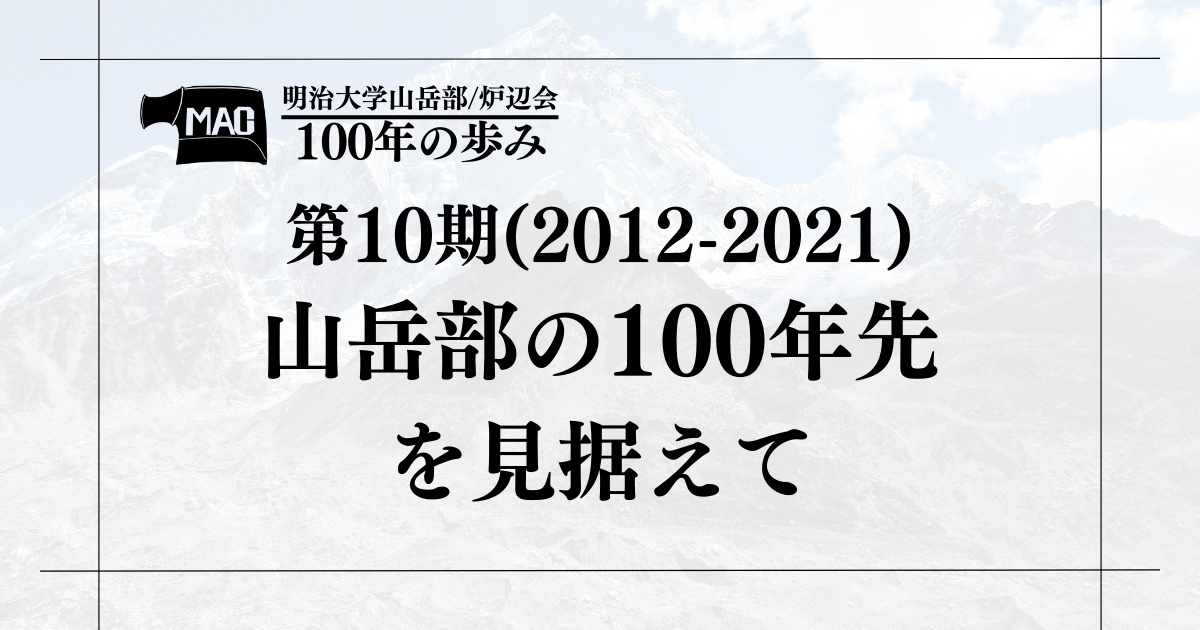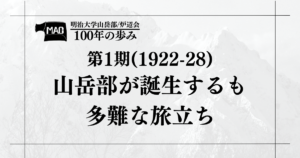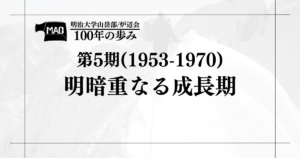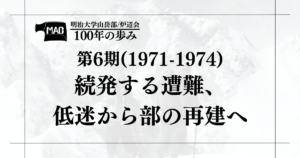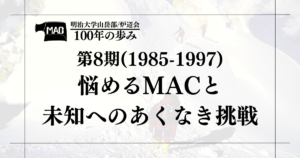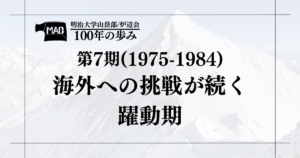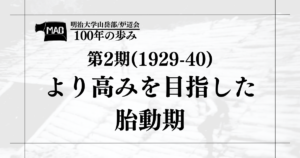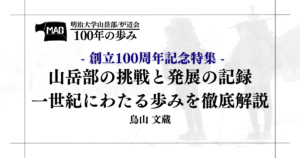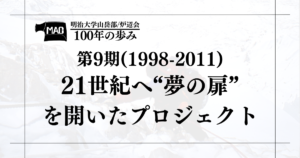少数精鋭で踏ん張る山岳部と炉辺会の世代交代
2012(平成24)年5月、駿河台リバティタワーで創部90周年記念祝賀会が開かれた。
この年、主将の宮津はスケジュール管理を徹底し、合宿の合間に“準合宿”を挟み、目的別のきめ細かい山行で集中力を切らさなかった。これが新人の残留につながる要因の一つとなった。
2013(平成25)年度は新人4名が入部し、4年1名、3年1名、2年5名と、久しぶりに10名態勢となった。
2012年度から3年間の冬山合宿はいずれも目標の山頂を踏めなかったが、2015(平成27)年度(主将・松本拓也)は、冬山決算合宿で東尾根から鹿島槍ヶ岳北峰に立ち、目的を完遂した。
2016(平成28)年度からの3年間は4学年が揃わず、各合宿に少なからず影響を与えた。スポーツ入試で入った学生の退部、怪我をするとすぐ辞めてしまう部員が続き、部員数は常に一桁という厳しい状況が続いた。
ここにきて、スポーツ入試による学生が減少する傾向が続き、スポーツ入試制度にある程度依存してきた部にとって、新たな課題が浮上した。
この年、山岳部と炉辺会ともにトップが交代し、新たなスタートを切ることとなる。
部員減少という逆風の中、13年間にわたり山岳部監督を務めてきた山本宗彦が退任し、中澤暢美にバトンが渡された。その中澤は就任早々、新入部員が1人も入らないという厳しい洗礼を受ける。
また、炉辺会は節田重節から戦後生まれの吉澤清に会長が引き継がれた。そうした矢先、MACの戦後復興を築き、日本山岳会の会長を務めた大塚博美が6月に逝去する。
この年の冬山決算合宿は、わずか3名(4年1名、3年1名、2年1名)で爺ヶ岳・東尾根から鹿島槍ヶ岳に立つ。OBの手助けを借りることなく学生のみで実施し、学生の意地を見せた。
この年の暮れ、嬉しいニュースが飛び込む。前山岳部長の小疇尚先生が、平成30年度の秩父宮記念山岳賞受賞の栄誉に輝いた。
時代が令和に移った2019(平成31)年4月、飯田年穂先生が退任し、加藤彰彦先生が山岳部長に就任する。
小田英生が主将となった春、新人4名(スポーツ入試1名、一般3名)が入部した。しかし、学年構成は小田1人に新人4名という厳しい変則状態となった。
創部100周年に向け、チャレンジは続く
「ドリーム・プロジェクト」以降、山岳部と炉辺会による海外遠征は、しばらく鳴りを潜めた。それでもOBたちは少人数の登山隊や公募隊に加わり、ヒマラヤを目指した。
とりわけ、スポーツ推薦で入部した三戸呂拓也と宮津洸太郎の活躍が目を引いた。
2012年夏、三戸呂は東海大OBの平出和也氏とペアを組み、パキスタンのフンザにあるシスパーレ(7611m)に未踏ルートの南西壁から挑んだ。しかし、核心部の雪壁で高度を稼げず5750m地点で断念する。
翌2013年春、三戸呂はテレビ番組のサポート隊に加わり、マナスル(8163m)に登頂。また、同年夏には栃木K2登山隊に参加した佐々木理人が、大規模な雪崩に遭遇し、登頂を断念する。
2015年秋、日本山岳会の2つの登山隊がヒマラヤに向かった。学生部ネパール東部登山隊に宮津が登攀隊長として参加し、未踏峰ジャネⅡ(6318m)に登頂する。日本アピ登山隊に加わった三戸呂は、転進した北面の初登ルートからアピ(7132m)に登頂する。
2018年も三戸呂と宮津の2人が活躍する。秋に三戸呂は友人とペアを組み、未踏の北壁からニルギリ北峰(7061m)に挑んだが、北壁のコンディションが悪く5900mで断念。
一方の宮津は日本山岳会青年部チャムラン登山隊に参加し、西稜からチャムラン(7319m)に向かったが、メンバー1人が体調を崩し6400m地点で撤退となる。
翌2019年、三戸呂はガッシャーブルムに挑み、Ⅰ峰は断念したものの、Ⅱ峰(8035m)に登頂し、久々に8000m峰の頂に立った。
2020(令和2)年になると、世界的な新型コロナウイルス感染症の流行で海外渡航が難しくなり、海外登山は自粛せざるを得ない状況になってしまった。
安定的な炉辺会運営と史料の電子化
創部90周年記念で出版された『炉辺』第10号(2012年6月発行)が、山岳雑誌『岳人』から2012年度岳人会報賞 準優秀賞を贈られ、90周年に花を添えた。
炉辺会は1978(昭和53)年に*終身会費制度」を導入し、基金の運用益をもって会の運営に当たってきた。
しかし、金利の低下で運用に限界が生じる事態となる。また、基金運用面で長年財務を担当してきた秋山光男の後継者がいないことも重なり、理事会で今後の基金運用について検討した。
その結果、リスクのある金融商品での運用をやめ、銀行預金に切り替え、安定的な運用を図ることにした。部員の少数化に伴い、OBの数も自然減少をたどる時代を迎え、安心・安全な炉辺会運営に舵を切った。
このころ、山岳部および炉辺会が所蔵する様々な史料の電子化(PDF化)に取り組んだ。
会報「炉辺通信」のアーカイブが完成した後、機関誌『炉辺』をはじめ、山岳部の年間計画書・報告書、書籍などの史料や記録が電子化された。
また、山岳部でも2016年から、部室の書棚にある図書のナンバーリングとデータ化を行った。
そうした中、炉辺会の諸会合で利用してきた「炉辺会ルーム」のあるビルが取り壊されることが決まり、2015(平成27)年11月開催の理事会が最後となった。
40年余りにわたり使用された、便利なクラブルームであった。
コロナ禍で山岳部、炉辺会の活動停滞
創部100周年を迎える2年前の2020年、新型コロナウイルスが猛威を振るい、東京オリンピックが延期される事態となった。
3月末に大学から「活動自粛要請」が出され、併せて学内立入禁止となり、リモート授業が続けられた。
そのため、恒例の新人勧誘は行えず、SNSを活用した勧誘方法が採られた。その結果、スポーツ推薦入学1名と一般から2名が入部した。
しかし、秋に一般からの2名が退部し、2年生2名、1年生1名の3名での部活動となった。
そうした中、山岳部の部室も入室が制限され、急遽、学外に仮部室を借りざるを得なくなった。
さらに緊急事態宣言が発出されると、体育会の活動は「全面活動禁止」となり、5月、6月に予定していた山行や合宿は中止となった。
6月中旬、大学より「体育会各部活動再開のガイドライン」が出されると、中澤監督は大学と相談し、新型コロナウイルス感染防止のガイドラインを作成し、活動再開を目指した。
7月に入ると、大学より「山行の実施については、宿泊を伴わず、負荷の小さい山行から徐々に強度を上げていく」という条件付きで許可され、徐々に活動が再開された。
この記事を書いた人

鳥山 文蔵
- 昭和49年卒部
- 日本山岳会宮城支部 会報・編集出版委員会