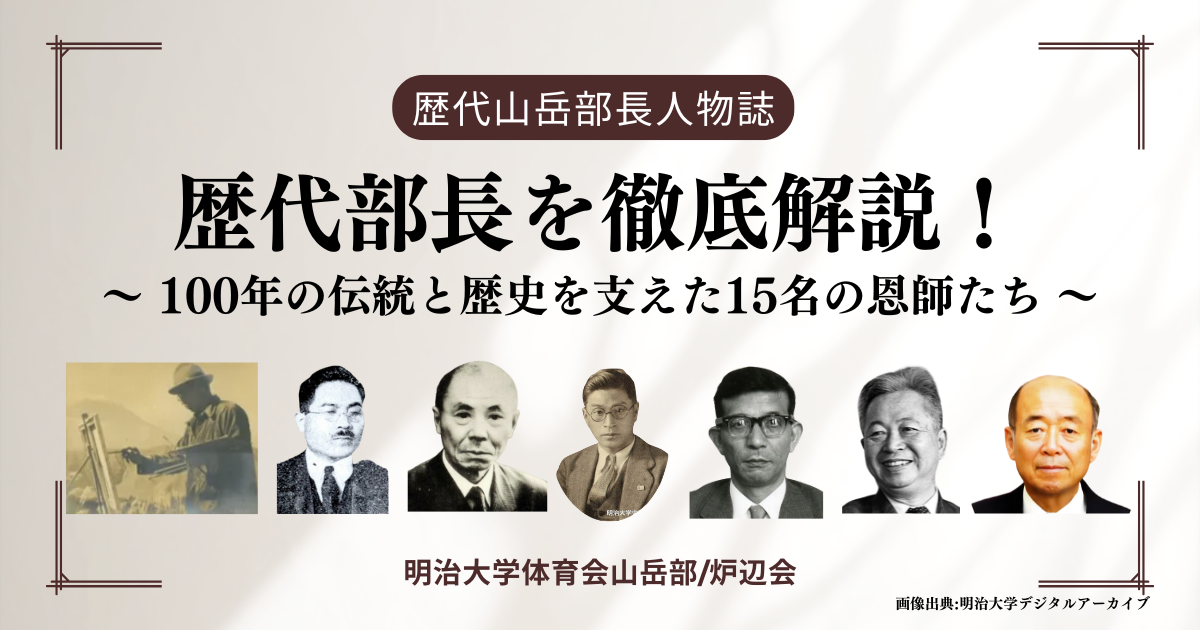本記事は、炉辺会の機関誌『炉辺11号』(発行日:2023年6月1日)に掲載された「歴代山岳部部長人物誌」を、ウェブ版として内容を調整のうえ再掲載したものです。
私たちは「山岳部の部長」になられた担当教授の皆様を、親しみを込め「部長先生」と呼んでいる。授業や教務でお忙しい中、部員会や合宿検討会、送別会をはじめ、炉辺会の各行事にもご出席いただき、助言や励ましの言葉をいただいてきた。
明大山岳部は時代の移り変わりのなかで多くの部長先生と出会い、その時々、厚い信頼の絆で固く結ばれてきた。あるときは教授と学生、またあるときは父と子、そして、部長と部員という普遍的な関係が存在した。身近に教わった担任教授を語るのではないが、100年にわたる部長先生、すなわち恩師群像を綴ることは、創部以来、部長先生たちが歩んでこられた足跡であり、我が山岳部と強固に重なり合う歴史でもある。
私たちは山岳部に入部し、その時々の部長先生と出会ってきた。まさに運命的な出会いと言える。山岳部100年の歴史で15名の部長先生と出会い、数々のご支援はもちろん叱咤と激励を受けてきた。これまでのご功労に感謝の言葉をささげ、ここに山岳部長先生の足跡を留めたい。
初代 大谷 美隆 (1922年8月~1924年3月)
明治大学山岳部の初代部長、大谷美隆氏は、スイス留学から帰国後に法学部教授として母校に復帰し、28歳で山岳部長に就任した。若々しく親しみやすい大谷氏は、スイス・アルプスでの体験を部員たちに語り、その魅力で多くの憧れを集めた。翌年、山岳部は正式なクラブとして認可されたが、関東大震災による母校の再建に尽力するため、大谷氏は部長職を辞任することとなる。それでも、彼は山岳部への支援を惜しまず、槇有恒氏の講演会を企画するなど、さまざまな形で貢献を続けた。辞任後も部員たちとの絆を大切にしたその姿勢は、山岳部の発展に大きく寄与した。
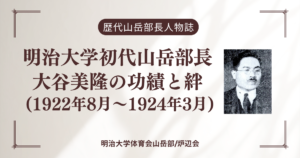
第2代 神宮 徳壽 (1924年4月~1926年5月)
神宮徳壽先生は、大正末期から昭和初期に明治大学山岳部の草創期を支えた人物で、部長を2度務めたほか、炉辺会初代会長も歴任した。父親が神社の神官だった影響で山岳宗教に興味を持ち、1921年に日本山岳会に入会。元学長で日本山岳会員の木下友三郎に推薦され、1924年に34歳で部長に就任。当時の山岳部は震災や創設者の急死など苦境にあったが、神宮の指導により部員たちは再建への希望を見出した。彼の個性的なあだ名「苦素」は、健康を重視するユーモラスなエピソードに由来し、部員との親しみや絆を象徴している。また、哲学的視点や山岳宗教の知識を共有し、登山を通じた人格形成を説いた。
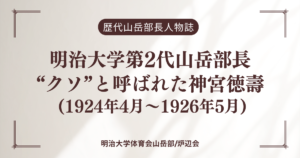
第3代 摺澤 真清 (1926年6月〜1928年8月)
1925年、「陸軍現役将校学校配属令」により、摺澤真清少佐が明治大学に赴任した。翌年には山岳部長に就任し、部員たちが懸念していた軍隊式の訓練を導入することはなく、親しみやすい態度で接した。摺澤は地図の活用法や測量技術の指導、陸地測量部の見学を通じて部員たちの技術向上に尽力した。また、スキー競技班の独立を速やかに実現させるなど、課題解決に向けた決断力を見せた。その人柄と行動力は部員に親しまれ、軍人としての厳格さを超えて誠実で実直な一面を示した。短い在任期間ながら、彼が山岳部に残した功績は大きい。
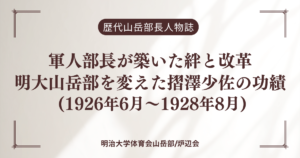
第4代 神宮 徳壽 (1928年9月~1932年4月)
– 二度にわたり山岳部を牽引してくれた岳人教授 –
神宮徳壽教授は、急な異動により二度目の山岳部長に就任した。当時38歳の神宮部長は、1928年以降、部の基盤作りや活動を支え、1930年には明大山岳部を日本山岳会に入会させた。部室の設立や部員の活躍も相まって、部は次世代へと進化。だが、1931年には南アルプスで案内人が増水した川で遭難死する初の事故が発生。神宮部長は弔問に赴き、責任を全うした。翌年、部長職を辞した神宮教授は家族との山行を楽しむが、1939年に48歳で急逝。その功績は山岳部と炉辺会の歴史に深く刻まれ、多くの人々がその死を悼んだ。
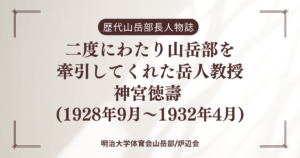
第5代 春日井 薫 (1932年5月~1933年5月)
春日井薫先生は1932年から1933年の1年間、第5代山岳部長を務めた。1923年に渡米し、イギリスでも留学経験を積んだ彼は、帰国後「明大体育会の父」と称されるほど学生スポーツに理解が深かった。山岳部では、自然への敬意を重んじる登山精神を提唱し、「駿台あるこう会」を設立。スキー訓練を教育の一環として取り入れ、社会での礼儀や精神性を学ばせる独自の教育方針を実践した。卒業条件にスキー訓練参加を課すほど徹底しており、スポーツを通じて人材育成に力を注いだ。部長退任後も部員との交流は続き、彼の教育理念や人柄は多くの学生に影響を与えた。短い在任期間ながら、山岳部の発展に大きく寄与した人物である。
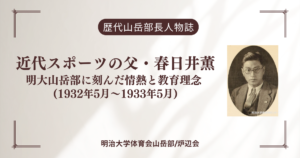
第6代 太田 直重 (1933年6月~1934年4月)
1933年、理数系出身の太田直重先生が山岳部長に就任した。前任の春日井薫先生がアメリカへ渡るため急遽指名されたが、在任期間はわずか10ヶ月と短命だった。前年には神宮徳壽先生の誘いで上高地を訪れており、この縁が関係した可能性がある。太田先生は排球部(現・バレーボール部)の部長も兼任し、こちらでは20年間尽力。一方、山岳部では山小屋建設という課題が話し合われたものの、進展の記録は残されていない。1950年に54歳で急逝し、山岳部との縁は浅かった。
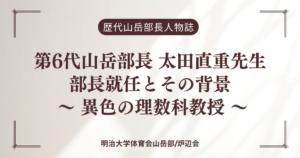
第7代 末光 績 (1934年5月~1943年5月)
第7代山岳部長の末光績先生は、戦前最長の9年間にわたり山岳部を率い、大きな功績を残した。札幌農学校で培った登山経験を活かし、就任直後に発生した遭難事故では、文部省の会議に出席して遭難防止に尽力するなど、積極的に問題解決に取り組んだ。1935年には、部員たちの念願だった八方尾根明大山寮の建設を実現し、スキー練習など活動の基盤を築いた。さらに、1940年の台湾遠征では部員たちとともに異国の山を踏破し、その姿勢は若い部員たちに深い感銘を与えた。また、趣味の山岳画を通じて、山への情熱を部員たちと共有した。末光の献身的な指導と情熱は、戦後の山岳部活動にも受け継がれている。
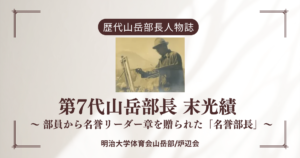
第8代 小島 憲 (1946年4月~1949年3月)
第8代山岳部長の小島憲先生(1946年~1949年)は、戦後の混乱期に山岳部を再建した人物。戦中に部員たちと出会い、その信頼を受けて戦後初の部長に就任。「気持ちで負けるな」という言葉で部員たちを励まし、その教えは再出発の原動力となった。小島部長のもと、新入部員が20名以上入部し、送別会では戦後の決起集会のような熱気があふれた。自身も登山経験を活かして「苦難に負けない精神」を説き、登山と人生の道しるべを示した。定年後には70歳で北アルプスを単独縦走するなど、山への情熱を生涯貫いた。1981年にはエベレスト隊の出陣式で隊員を激励。「気持ちで負けるな」という言葉は、戦後の再建期における山岳部の精神的な支柱となり、今も語り継がれている。
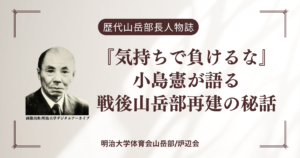
第9代 泉 靖一 (1949年4月~1953年3月)
泉靖一先生は、1949年から1953年にかけて明治大学山岳部長を務めた。京城帝国大学出身で、学生時代に朝鮮半島の多くの山々に登る経験を持ち、登山だけでなく民族調査にも熱心だった。戦後、本学に教員として迎えられた泉は、登山の知識と情熱を山岳部に注ぎ、部員たちと兄弟のような関係を築いた。彼の「伝統を継ぐ者は尊い」という言葉は、部員たちを励まし続けた。1951年には東京大学に移籍したが、名目上山岳部長を続け、1953年に正式に退任した。泉はユネスコの研究活動にも携わり、多忙な日々を送ったが、1970年に55歳で急逝した。彼の生涯は登山と学問、そして人々との深い絆に彩られている。
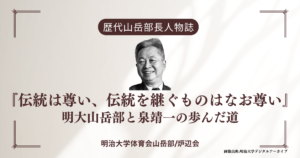
第10代 三潴 信吾 (1953年4月~1957年2月)
三潴信吾先生は、1953年に明治大学山岳部長に就任し、正義感と「人の和」を説く姿勢で部員たちを導いた人物だ。東京帝国大学を卒業後、戦争を経て明治大学の教員となり、37歳で山岳部長に就任。部員たちに「自然に帰れ」という哲学を語りかけ、登山の精神性を重んじた。1957年に教員ストライキ反対の立場から明大を去った後、高崎経済大学に赴任し、新たに山岳部を創設。明大で培った登山の精神を新しい世代に伝えるべく尽力した。その後も自ら登山を楽しみ、人生の教訓を後進に伝えた。2003年、86歳で逝去。登山ブームに流されることなく「原点に戻れ」と説いたその姿勢は、孤高のリーダーとして多くの人々に影響を与えた。
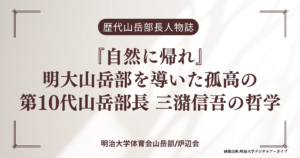
第11代 渡辺 操 (1957年3月~1970年2月)
渡辺操先生は、1957年に明治大学山岳部長に就任し、14年間にわたり部の発展に尽力した。着任直後、白馬鑓ヶ岳での二重遭難をはじめ、在任中に計3件の遭難事故で部員5名が命を落とす苦難に直面。しかし、部員と深い絆を築き、「ラッコさん」の愛称で親しまれた。渡辺の発案で実現したマッキンリー(現・デナリ)遠征では北米最高峰への登頂に成功し、ニュージーランド遠征やヒマラヤ学術調査隊も部の歴史に残る成果となった。晩年、膵臓癌で他界するも、教え子の植村直己がエベレスト登頂を果たし恩師への感謝を示した。渡辺部長の下で育った部員は100名を超え、その存在は山岳部の礎となった。
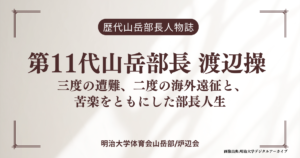
第12代 木村 礎 (1970年4月~1981年9月)
木村礎先生は1970年に第12代明治大学山岳部長に就任し、11年半にわたり部を支えた。着任早々、1971年と1972年に相次いで遭難事故が発生し、計3件の遭難で3名の部員を失う苦難に直面した。しかし、「遭難しない、退部しない、卒業する」という3つの心得を説き、部員たちと山男の約束を交わし、部の再建に尽力した。在任中には大学創立百周年記念エベレスト遠征計画を推進し、大学からの助成金を得るなど尽力。退任後も炉辺会会長や明大学長を務め、植村直己のマッキンリー遭難など最後まで山岳部との縁を深めた。木村礎のリーダーシップは、山岳部の再建と未来の発展の基礎を築いたと言える。
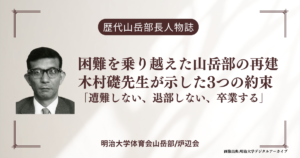
第13代 小疇 尚 (1981年10月~2005年3月)
小疇尚は1981年から23年半にわたり明治大学山岳部長を務め、部員減少という難題に直面しながらも部の発展に尽力した。地理学の専門家として学術調査に参加し、チョモランマやインド・ヒマラヤでの遠征を成功させ、部員に学術と登山の両面で影響を与えた。1991年には12年ぶりの遭難事故が発生するも、自ら捜索活動に携わり、部員や関係者を支えた。部員減少対策としてスポーツ推薦制度の導入を推進し、部の存続に貢献。晩年には「秩父宮記念山岳賞」を受賞するなど、研究者としても評価された。小疇部長時代の教え子たちは部の存続と発展の礎を築き、山岳部を新たな時代へと導いた。
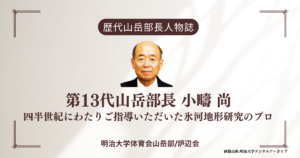
第14代 飯田 年穂 (2005年4月~2019年3月)
戦後生まれ初の明治大学山岳部長として、飯田年穂先生は2005年から14年間その職を務めた。フランス文化に精通し、「クライマー教授」として知られる飯田氏は、アルプスの名峰に挑むなど自身も登山を実践。就任中には加藤慶信のエベレスト無酸素登頂や8000m峰連続登頂といった快挙を支えた一方、部員減少や若手コーチの負担増という課題にも対応。2008年の加藤氏遭難後は追悼展を開催し、その偉業を称えた。また、創立130周年記念事業として学生のマッキンリー登山を成功に導くなど、部の発展に尽力。在任中の安全登山の維持と部員育成は、今も多くの登山者に影響を与えている。
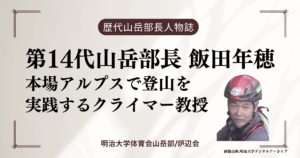
第15代 加藤 彰彦 (2019年4月~)
高校時代から登山に親しみ、植村直己に影響を受けた加藤彰彦氏が、2019年に第15代山岳部長に就任した。早稲田大学で学んだ後、銀行勤務を経て明治大学教授となった加藤氏は、社会学を専門としながらも登山に情熱を注ぐ。「時代遅れ」に見える山岳部の伝統的登山スタイルに感銘を受け、合理的判断力や精神力を育む価値を強調する一方、部員減少や学生の変化といった課題に向き合っている。学業との両立や活動の柔軟性を模索し、新たなMAC(山岳部)の形を構築するべく尽力。創部百周年を見据え、部の存続と発展に向けて監督や学生と共に改革に取り組んでいる。
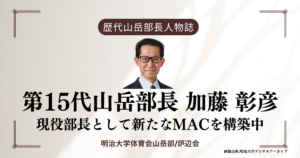
この記事を書いた人

鳥山 文蔵
- 昭和49年卒部
- 日本山岳会宮城支部 会報・編集出版委員会