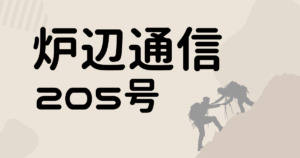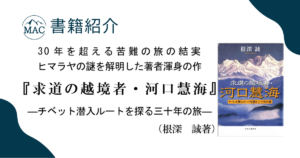懐かしい小野さんの思い出 – 根深誠(昭和44年卒)
四年間の山岳部現役生活を通じて、とくに強烈な印象として私の記憶に刻まれているのは、新人と呼ばれた一年生部員のときの夏山合宿だ。憧れの大学山岳部に入部して、すでに新人合宿、六月合宿を経験したけれど、まだまだ見習いの域を脱してはいなかった。それが理解できるのはOBになればこそである。
山好きな高校生にとって入部したての部生活は、何もかもが異質だった。汗の沁み込んだ部室の臭気にしても想像を絶していた。雪焼けしたOBが部室に出入りし、喧々諤々、山について議論するさまは異様に映った。そこは異次元世界であり、私自身がその一員になるとは、当時、手の届かない存在のヒマラヤを夢に描くようなもので現実感がなかった。
「ヒマラヤへ行きたいか」
「はい、行きたいです。そのため山岳部に来ました」
ヘッドコーチだった尾高さんとの会話の断片である。尾高さんはゴジュンバカン遠征を体験していた。部を全うすればヒマラヤに行けるとのことだったが、それは私にとって真実だった。
当時は七合宿制を採用し、年間の実働日数は100日を下回らないように設定されていた。この間に、準備会と称して合宿ごとに食糧買いつけやトレーンニング、各係による説明会や検討会、報告会。内容は濃密で、体力・気力・知力ともども、まだ不慣れな新人にとってはハードルが高く、そこでの規律ある部生活は厳しく徹底していた。
前置きはこれくらいにして、私がここで述べるのは私の現役時代、つまり一九六〇年代後半から七〇年代前半にかけてのことである。そうした、いまとは異なる時代にあって、耐え難いほどに厳しかったのが夏山合宿だった。当時は一次、二次と二回に亘って実施されていた。一次は南アルプス北部で全部員が一堂に会して行なうもの。二次は3隊に分かれての分散合宿だった。「団体から個人へ」のスローガンを掲げて団体志向から個人志向へと転換を図ろうとする空気が流れていた。時代の潮流を反映してのことかと思われる。大学紛争の最盛期でもあった。
分散合宿で私の参加した隊は、四年生の小野さんがリーダーで、二年生の長塩さん、それに一年生の私との三人から編成されていた。剣岳西面の白萩川を遡行して大窓を越え、黒部に下り、下ノ廊下をへて白馬岳に登り、雪倉岳、朝日岳をへて沢登りの定着合宿を行なったのち現在のJR平岩駅に下った。合宿実働日数23日。
雪渓の詰まった白萩川の遡行では、クレバスに行く手を阻まれ、ザイルを張り渡して荷を運び、空身になって確保されながらクレバスを対岸に渡った。上部の雪渓は急峻で、ガスが湧き立ち、落石がバウンドしながら落ちてくる。重荷の私は、跳ね落ちてくる落石から身をかわすのに難儀した。危ない、と鋭く叫んで小野さんが私の前に立ちはだかった。
小野さんは間一髪のところで身を反転させながら左腕を上げて落石をかわした。落石はキスリングのタッシュを直撃してズタズタに破った。かすり傷だったが、小野さんも左腕を負傷した。私は疲労困憊しながら、この瞬間、身を挺して私を庇った小野さんの態度に頭の下がる思いを禁じ得なかった。山岳部の絆というか、伝統的な精神性が身に沁みた瞬間だった。
その一方で、連日くたびれ果てて意識朦朧としながら歩かねばならない、当時の私の現実は、山の歌集に出てくる「新人哀歌」そのものだった。池の平山の、確か仙人峠と記憶しているのだが、小さな峠道の下りで、「峠から剣を眺めたか」と詰問されて「いえ」と答えると「眺めて来い」と言われた。口調は穏やかだが、小野さん独特の「あの凄み方、あの目線」で睨まれた。山々を眺めて愉しむ心の余裕など私には微塵もなかった。
いま思い返してもきつ過ぎる。一年生の私は連日の行動、食当に耐えきれず、黒部峡谷の阿曽原でついに失神。夕方、気がつくとテントの後室に寝かされて長塩さんが食当に当たっていた。想像するに、困惑したのはリーダーの小野さんではなかったかと思う。私を決して甘やかさないようにと自らに厳しい態度をとっていたものと思われる。
下ノ廊下では、バテててふらふらしながら歩く私を転落させてはいけない、との判断から、私のキスリングの背環にザイルを通して、安全確保しながら歩かされた。傍から見ると、さながらリードで繋がれて散歩する飼犬を連想させたかもしれない。これが大学山岳部のしごきの実態なのかと痛感しながら歩くしかなかった。
さらに白馬岳に至る百貫の登りでは、下ってきた他大学の集団と遭遇し、滅多には見られない陳腐な事態を体験した。十人ほどの集団で、「どけどけーっ」と怒鳴り散らしながら駆け下ってきたのだ。小野さんが「避けるな」と言ったにもかかわらず、その勢力に圧倒され、私たちは道を開けざるを得なかった。集団の最後尾にいるのがリーダーのようだ。頭に鉢巻きして、棒切れを片手に持ち、人相もよろしくない。まるで暴徒ではないか。
すれ違いざまに、小野さんが「おい、待て」と呼び止めたときは、乱闘でもはじまるのかと身の縮む思いがした。相手の鉢巻き男は殺気立ち、険悪な表情をむき出しにして「何―っ」と小さく叫んで詰め寄ってきた。と、突然、叱りつけられた仔犬のような従順な態度に豹変し、「失礼しました」と詫びたのだ。これには何がどうなっているのか、驚くしかなかった。「メイジさんですか」とへりくだっている。上級生部員になればキスリングの片隅に縫い込むわが部のロゴが目についたらしい。
小野さんは落ち着き払っていた。意気揚々たる態度で、例によって「あの凄み方、あの目線」の穏やかな口調でおもむろに「山はみんなのものだろ。気をつけろよ」と注意したのだ。なかなか大したもんではありませんか、やるもんだね、と私は新人の分際で内心ひどく感服した。
合宿後半の沢登りでは、ザイルを仕舞い込む私のもたつく姿に小野さん曰く。「だから日本人はザイルさばきが下手と言われるんだよ」いよッ、日本人とは大きく出たもんだね、さすがニュージーランド帰りの小野さんだ、と内心思ったが、もちろん口が裂けても言うわけにはいかない。精一杯の無益な抵抗を試みただけなのだ。
この年の春、私が入部する以前だが、小野さんは氷河を戴くニュージーランドの山々で合宿山行を体験していた。当時としては、おそらく数少ない、氷河の山の経験者だったのではあるまいか。それだけに自信を持って私の指導に当たっていたようなのだ。
小野さんは口煩い性分で、つねに私から目を放さなかった。一日の行動を済ませて、夜、私がシュラフに潜り込むのを見ながらこう言った。「お前、日記をつけているのか」「はい、つけています」「つけてるところを見たことがないぞ」「シュラフの中でつけてます」「バキャヤロ、嘘つくんじゃない。見せろ」
小野さんは独特の「あの凄み方、あの目線」で睨みつけて、私の日記を見た。すると途端に、拍子抜けしたようで顔の表情が弛緩し、何だこれは、と笑い出した。「ひと口カツなら聞いたこともあるが、お前のこれはひと口日記ではないか」×月×日バテタ。×月×日明日もがんばるぞ。×月×日失神。
この追悼文を書きだしたら、いろいろ思い出されてキリがなくなってくる。規定の枚数を大幅に超えている。締めくくりとして、どうしても伝えておきたい思い出を述べておこう。私たちの伝統ある山岳部の当時の若い力を結集した1977年のヒマルチュリ登山である。
個人的にも私はいろいろな山を登ってきたが、その中でもっとも壮絶な内容の登山だった。往路のキャラバン中に山から木を切り倒して橋を架設したり、ベースキャンプでのポーターの反乱、登山活動に入ってからもたび重なる降雪に悩まされ、ラッセルの苦労が尽きなかった。
第五キャンプの雪崩による埋没、そして脱出。ようやく第六キャンプを建設し、登頂態勢が整い、アタック時、山頂まぢかに引き返す途中の氷壁下降中、小野さんと同期の近藤さんが、崩壊した雪庇の直撃を受けて即死。夜、各キャンプに小野さんのすすり泣きがトランシーバから流れ出た。「気をしっかり持て」と叱咤激励する菅沢隊長の声がいまも耳朶にこびりついている。
登山活動を開始して前半、後半を併せて50日以上に及ぶ長期戦の悲惨な結末だった。遺体を搬出し荼毘に付した。帰路のキャラバンも雨にたたられ辛かった。私は登山中に第三キャンプで落雷を受けてすっかり体調を崩し、キャラバン中に下血した。遭難で近藤さんを失った悲しみや、自身の不甲斐なさがない交ぜになって私を責め立てていた。痛恨の極みだった。そこには辛かった新人時代の夏山合宿とは比べものにならない異質の、人間の存在意義にかかわるような重々しさが秘められていた。
同期の近藤さんを失った小野さんの胸の内はどんなに辛らかったか。とは思いつつも、ネパールを出国するときの小野さんの姿に、救われたような思いを私は感じだ。その日、空港には、世話になったAP通信のビナヤさんをはじめ多数の関係者が見送りにきていた。ロイヤルネパール航空機のタラップを上り詰めて機内に入る間際に、小野さんは乗降口から振り返り、虚空に向かって大きく両手を振りかざした。
鳥山隊員が撮影したヒマルチュリ登山の記録映像にその姿が映し出されている。見送りに詰めかけていた人たちの遥か後方彼方に聳え立つ、私たちの白き墓標の山ヒマルチュリに辛い別れの挨拶を送ったのだと思う。悲しみの向こうにある、浄化された魂のしづもりと清々しさ、そこに安らぎの境地を垣間見た気がした。
小野さんの訃報に接したいま、あのときの神聖な気持を呼び覚まし、小野さんに感謝をこめて別れの挨拶をしなければならない。小野さん、ありがとうございました。生前の恩義は決して忘れません。合掌。