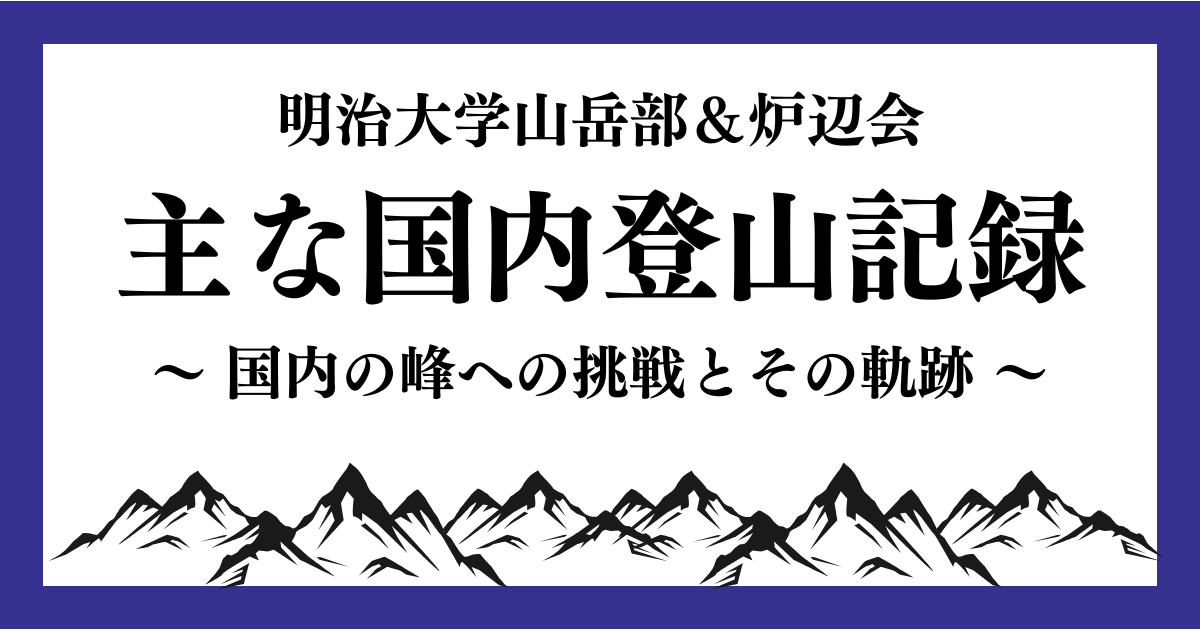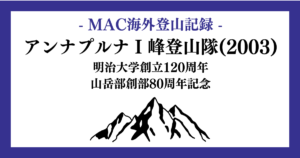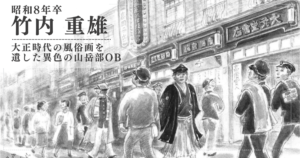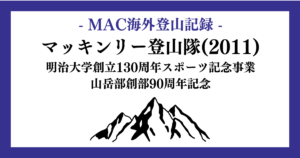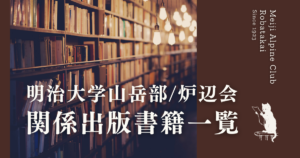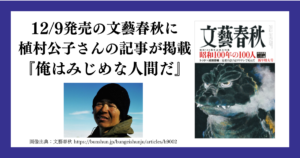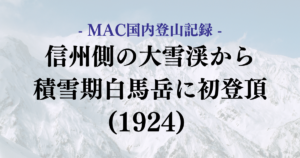明治大学山岳部100年の歴史は、厳しい合宿と苛酷な山行の日々に彩られている。その根底には険しい山、厳しい自然と対峙できる体力と持久力を蓄え、さらに逞しい精神力をみなぎらせ、たゆまぬ精進を続けてきたスピリッツが宿っている。
振り返れば、若き日の記憶の一頁に記された想い出には、泥臭く愚直に、そして一途に、山に向き合ってきた魂が共鳴している――
照り返す真夏の太陽の下、重荷を背負って喘ぎ喘ぎ登る仲間の姿、雪降りしきる中、胸を超すラッセルの先陣を切る友、岩壁にザイルを延ばし果敢に攀じ登る頼もしい奴、そして、長い闇の道を黙々と歩いた君の足音 。
あの気高い峰、あの急峻な尾根、あのそそり立つ岩壁に、たぎる闘志を燃やして挑んできた踏み跡には、厳しい登高や壮絶な闘いの日々が刻まれている。
時は過ぎ今、創部100周年を迎えた。時代を超え、世紀をまたぎ、積み重ねられてきた数々の山行から激闘の記録を蘇らせ、ここに再録する。
山岳部及び炉辺会による主な国内登山記録
期間:1924年4月16日~ 20日〈実動 4 日、停滞 1 日、計5 日間〉
概要:新井長平ら3名と人夫2名が、信州側の大雪渓から積雪期の白馬岳に初登頂。悪天候のため停滞しながらも、雪崩の危険がある斜面を慎重に進み、葱平を経て山頂に達し、無事に下山した。この登山ではスキーが使用された。
期間:1924年7月5日~11日〈6泊5日:実動3日〉
概要:馬場忠三郎、佐伯宗作らが剱岳・八ッ峰の末端からの初完登に成功した。7月10日に第1峰から登攀を開始し、翌11日に第8峰を踏破。また、この登攀中に「クレオパトラニードル」と呼ばれる特徴的な岩塔の初登にも成功した。
期間:1930年3月17日~ 26日〈実動5日、停滞5日、計0日間〉
概要:交野武一と宍戸文太郎らが、積雪期の白馬岳から唐松岳への初縦走に挑んだ。3月17日に猿倉小屋を出発し、悪天候のため何度も停滞しながら、21日に白馬岳頂上小屋に到着。その後も天候の回復を待ち、25日に再出発。杓子岳、鑓ヶ岳、不帰ノ嶮を越え、同日18時25分に唐松岳頂上の八方小屋へ到着した。途中、立教大学山岳部のパーティとすれ違う場面もあった。この縦走は、当時としては画期的な冬季登山の試みだった。
期間:
初登時:1936(昭和11)年8月12日~22日 奥又白池生活
積雪期:1936(昭和11)年11月1日~12日 奥又白池生活
概要:小国達雄と人見卯八郎は、前穂高岳北尾根第4峰東南壁に新ルート「明大ルート」を開拓した。彼らは奥又白池にキャンプを設営し、当初は3・4ルンゼを登る予定だったが、仲間の登攀の様子を見て急遽新ルートに挑戦。1時間強で4峰頂上に到達した。同年11月、彼らは後藤大策を加えた3人で積雪期登攀に挑み、悪天候と困難を乗り越えて2日がかりで成功を収めた。
期間:1947年12月10日~26日〈実働14日、停滞2日、休養1日、計17日間〉
概要:畳岩尾根から奥穂高岳への冬季登山に挑戦した。12月10日に上高地に入り、前明神沢上部の標高1800m地点にベースキャンプを設営。悪天候の中、キャンプ1(C1)を標高2500mに、キャンプ2(C2)を標高2800mに設営し、極地法を用いて登頂を目指した。12月23日、C2から出発した隊員たちは、厳しい天候と困難なルートを克服し、奥穂高岳の頂上に到達した。この登山は、戦後の困難な状況下での極地法登山の成功例として、明治大学山岳部の歴史に刻まれている。
期間:1953年12月8日~27日〈実働17日、停滞3日、計20日間〉
概要:槍ヶ岳の滝谷における冬季登攀に挑戦した。12月23日に新穂高温泉から入山し、白出沢出合にベースキャンプを設営。24日、滝谷出合にアタックキャンプを設置し、25日早朝、Dフェース右ルートの登攀を開始。厳しい寒さと困難な岩場に直面しながらも、午後2時30分に登攀を完了し、槍ヶ岳山頂に到達した。その後、槍沢を下山し、26日に上高地に無事帰着した。
期間:1965年3月7日~24日〈実動17日、停滞1日 計18日間〉
概要:「剱岳長期計画」の最終年として、八ッ峰の完全縦走を目指した。3月7日に信濃大町から黒四ダムの扇沢事務所に入り、間組の協力で大町トンネルを抜け、黒部川左岸の飯場をベースハウス(BH)とした。その後、丸山頂上付近に中継キャンプ地(RC)を設営し、真砂尾根稜線上のジャンクション・ピーク(JP)肩にベースキャンプ(BC)を建設した。3月16日、縦走隊は三稜末端から登攀を開始し、Ⅰ峰に到達。翌日、悪天候のため停滞し、18日にⅡ峰からⅤ峰を経て5・6のコルに到達した。
期間:
《上級生縦走隊》
1976年12月16日~1977年1月7日〈実動12日 停滞11日 計23日間〉
《赤谷尾根隊》
1976年12月25日~1977年1月7日〈実動12日、停滞2日 計14日間〉
概要:上級生4名は、北仙人尾根から剱岳を経て早月尾根への縦走を実施した。入山後、悪天候により予備日を超える停滞を余儀なくされ、OB救援隊の出動を招いた。12月21日には、五十嵐隊員が雪庇とともに転落する事故が発生したが、幸い軽傷で済んだ。その後も吹雪や深いラッセルに苦しみながらも、1月5日に剱岳頂上に到達。翌日、早月尾根を下山中にサポート隊と合流し、1月7日に全員無事に下山を完了した。
期間:1983年12月15日~1984年1月4日〈実動20日、停滞1日、計21日間〉
概要:前穂高岳北尾根からの登頂を目指す冬山合宿を実施。当初10名いた新入部員は、部内の不統一などの影響で4名に減少したが、主将の上田哲也は「登山活力の向上」を掲げ、9月合宿を経て部の士気を高めた。冬山合宿では、徳沢にベースハウスを設営し、リレーキャンプを経て8峰にベースキャンプを構築。悪天候や困難な岩稜に直面しながらも、12月30日に第1次アタック隊が前穂高岳頂上に到達し、翌1月1日には第2次アタック隊も登頂に成功した。この合宿を通じて、部員間の意思統一と登山意欲の向上が図られ、明治大学山岳部の復活を遂げたと評価されている。
期間:1987年8月2日~25日〈実動22日、休養2日、計24日間〉
概要:南アルプス縦走と北岳バットレス登攀を目的とした夏山合宿を実施。当時、4年生と3年生の部員が不在で、2年生の佐野哲也が主将として指揮を執った。合宿には2年生6名と新人3名が参加し、さらにOB7名が交代で同行しサポートを行った。合宿は、甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳、北岳、間ノ岳、農鳥岳、塩見岳、荒川三山、赤石岳、聖岳、光岳など南アルプスの主要な山々を縦走し、途中で北岳バットレスの1尾根、4尾根、シュバルツ・カンテなどの登攀を行うという内容であった。悪天候や困難なルートに直面しながらも、全員が協力し、計画を遂行した。この合宿は、部員の体力強化、技術向上、チームワークの醸成に大きく寄与した。
期間:1996年12月15日~12月31日〈実動16日、停滞1日、計17日間〉
概要:剱岳登頂とチンネ登攀を目的に冬山合宿を実施した。当初の小窓尾根からの計画を早月尾根経由に変更し、総勢10名で入山。悪天候の中、BCとC1を順に設営しながら前進し、12月24日には3名が剱岳登頂に成功。さらに29日にはチンネ北条・新村ルートの登攀を行い、約7時間で完登。全員が無事下山し、厳冬期の困難な登山をやり遂げた。
期間:2000年2月22日~3月5日〈実動10日、停滞3日、計13日間〉
概要:日本海の親不知海岸から白馬岳を目指す春山合宿を実施。主将の天野和明は「未知なる山域での全員縦走」を掲げ、栂海新道を選定。9名の学生とOB1名が参加し、事前の偵察と食料デポを行い、安全対策を徹底した。行程中、悪天候や深雪、視界不良によるルートミス、雪庇の崩壊など困難に直面しながらも、全員の協力で乗り越え、3月4日に白馬岳(標高2,932m)登頂を果たした。この合宿は、未知の領域への挑戦とチームワークの重要性を再認識させるものとなった。
大学スポーツは 4 年間という制約の中で、毎年部員が入れ替わる宿命を負っている。しかし、一方でメンバーが入れ替わっても、継続して活動しなければならないという使命を帯びている。
これからの100年、時代とともに社会環境や登山スタイルが変わろうとも、山と真摯に向き合い、地道に一合宿、一山行を積み重ねていってもらいたい。
この記事を書いた人

鳥山 文蔵
- 昭和49年卒部
- 日本山岳会宮城支部 会報・編集出版委員会