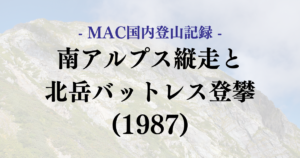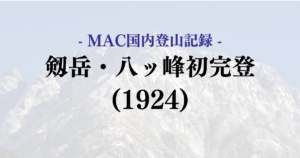目次
明治大学ゴジュンバ・カンⅡ峰登山隊
スクロールできます
| 活動期間 | 1965(昭和40)年3月〜4月 |
|---|
| 目的 | 未踏峰ゴジュンバ・カンⅡ峰(7646m)の初登頂。 |
|---|
| 隊の構成 | 調査隊長=渡辺操(53歳、山岳部部長、文学部教授)
登山隊長=高橋進(昭和28年卒、34歳)
副隊長=藤田佳宏(同30年卒、31歳)
隊員=平野眞市(同36年卒、26歳)、尾高剛夫、(同37年卒、24歳)、小林正尚(同39年卒、23歳)、植村直己(同39年卒、23歳)、入沢勝(4年、22歳、同41年卒)、医師=長尾悌夫(32歳、慈恵医大山岳部OB) |
|---|