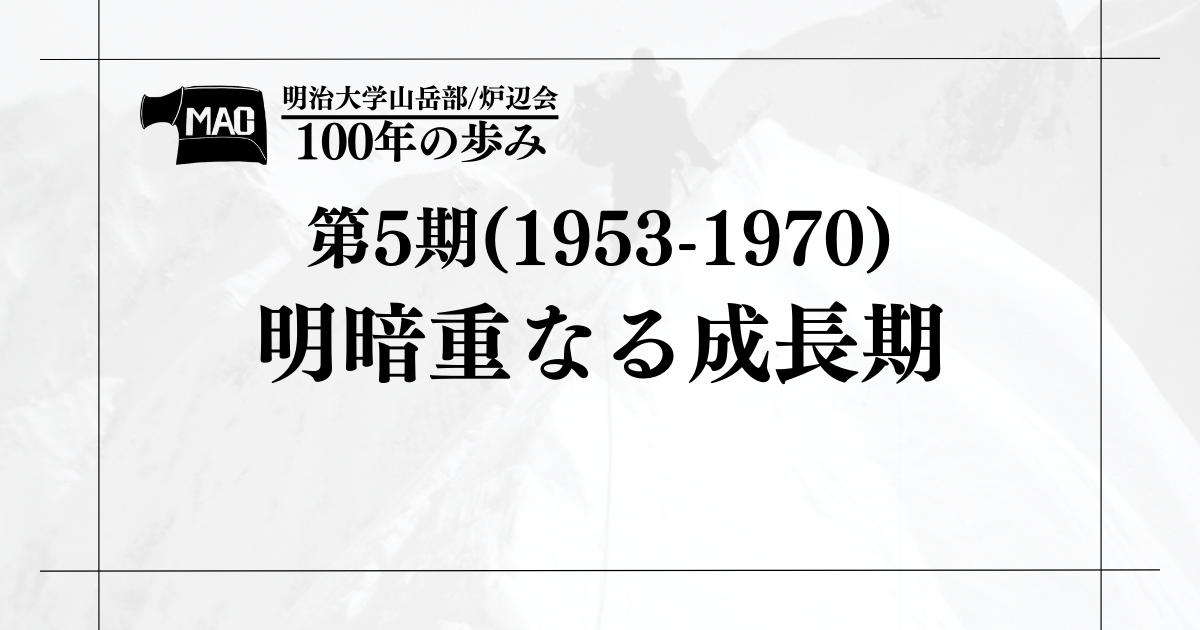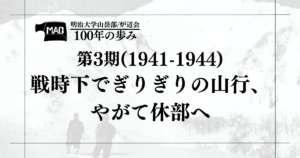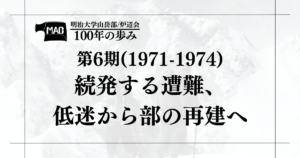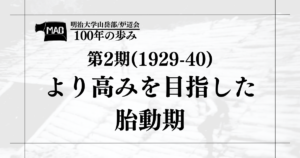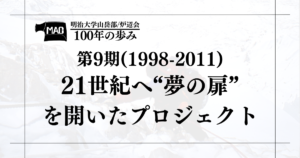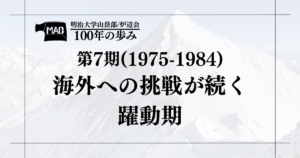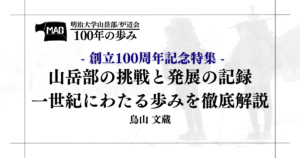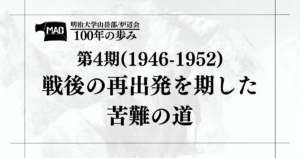未曾有の白馬二重遭難、続く1年生の死亡事故
世の中が落ち着きを見せ始めた1953(昭和28)年4月、第10代の山岳部長として三潴信吾先生が着任する。この年の主将・中村雅保は極地法一辺倒から新たな目標を模索する。冬山合宿は横尾尾根からの極地法に加え、滝谷はじめ北鎌尾根・独標往復など岩稜登攀に挑んだ。
そのころ、日本人の目は世界第8位の高峰マナスル(8163m)に注がれていた。日本山岳会マナスル登山隊の第2次、第3次隊に大塚博美が選ばれ、山岳部と炉辺会は大いなる期待感で盛り上がる。大塚はアタック隊を登頂に導くルートを切り拓く活躍を見せ、期待に応えた。このマナスル初登頂は、その後の“登山ブーム”を生み、山岳部に大勢の学生が入部することになる。

1957(同32)年2月末、白馬連峰での春山合宿が始まった。ところが、白馬鑓ヶ岳・北稜を3年部員の荒井賢太郎とザイルを組んで登攀した2年部員の佐藤潔和が滑落、負傷する。救援隊が現地に入り、必死の捜索が続けられた。その最中、杓子沢を下降していた捜索隊を大規模な雪崩が襲った。
コーチの五十嵐弘と3年部員の荒井賢太郎、さらに捜索に協力してくれた千葉大学山岳部2年部員の清水淳男君と伊藤康寿君を含め4名が埋没、佐藤を含め5名が死亡する二重遭難となってしまった(白馬鑓ヶ岳・二重遭難)。
翌年1月、「コーチング・スタッフ制」が設けられ、中堅・若手コーチが学生の指導に当たる。この後、炉辺会は学生とOBで構成する「遭難対策委員会」を立ち上げ、遭難防止の一助にしようと「遭難実態調査」に踏み切る。
また、1959年度から二重遭難の追悼を兼ね、新人合宿は毎年、白馬岳東面で実施される。ところが、この年の夏山合宿で1年部員の右川俊雄が病死する事故が起き、さらに12月24日、冬山合宿で立山・雷鳥沢で幕営中のテントが雪崩に襲われ、1年生の矢沢剛が亡くなる遭難が続けて起きてしまった。
戦後初の海外遠征でマッキンリーへ
遭難者を捜索している1957年4月、渡辺操先生が第11代の山岳部長に就任する。そのころ本学が1960年に創立80周年を迎えることから、学内で記念事業が検討された。渡辺部長の計らいで「アラスカ地域総合学術調査」が認められ、この中にマッキンリー(現・デナリ)登山が組み込まれた。
1960年4月11日、カヒルトナ氷河上の2440mにベースキャンプを建設、5月5日、高橋進、藤田佳宏、三室喜義、土肥正毅の4名がマッキンリー最高点、南峰(6190m)に登頂する。
この後、13日には高橋と小林孝次の2名が北峰(5934m)に登頂、14日には高橋、金澤恒雄、東真人、小林、三室、土肥の6名が再び南峰に登頂する。そのうち高橋と小林は南峰の頂上にテントを設営、頂上に1泊するという大胆な試みを成し遂げた。
このマッキンリーの成功で、山岳部と炉辺会は一気にヒマラヤへと突き進む。炉辺会は「ヒマラヤ研究会」を立ち上げ、7000m峰の研究に着手する。

改築前の駿河台本校校舎でアプザイレンの練習をする部員たち。1960年代の写真と思われる。
「剱岳長期計画」と「槍・穂高長期計画」
この当時、決算合宿をどこの山域で行うかがリーダー陣の頭を悩ませる課題であった。1961年度の主将に就いた木村敏之は、これまで個別に山域を設定する方式から、ある山域を特定し、様々なルートから毎年チャレンジする方式に切り替えた。こうして剱岳周辺を活動エリアに展開する「剱岳長期計画」が生まれた。

この計画初年度の冬山合宿は、小窓尾根と早月尾根から剱岳に登頂。年明けの春山合宿は弥陀ヶ原から剱岳と立山に挑んだ。
1962(昭和37)年度は創部40周年の節目を迎え、戦前からの懸案事項であった『炉辺』第7号が3月に発刊され、また、9月には日本青年館で記念の映画会が催された。
この年(主将・高橋登美夫)の冬山合宿は立山中央稜から立山と剱岳、続く春山合宿は大日岳主稜線から剱岳に立った。翌1963年2月には、創部40周年を記念し「炉辺通信」を発行、現在の会報につながっている。

小林正尚と植村直己がリーダーとなった1963年度の冬山合宿は北仙人尾根から剱岳へ、年明けの春山合宿は真砂尾根から剱岳への登頂が行われた。そして、4ヶ年計画の締め括りとなる1964年度を迎える。
主将に就任した菅澤豊蔵は、節田重節と姚正雄の2名が第1次ニュージーランド遠征に参加するため、冬山合宿は極地法ではなく、赤谷尾根から毛勝三山を経由し剱岳に登り、早月尾根を下る縦走に変更した。
また、「剱岳長期計画」の総決算となる春山合宿は、黒部ダムから内蔵助平を経て念願の八ツ峰を末端から縦走し、剱岳に登頂して長期計画の幕を閉じた(八ッ峰を完全縦走し剱岳へ)。


1965(昭和40)年度の主将になった久保山道夫は、部活動に長期ビジョンが必要と「剱岳長期計画」を先例に「槍・穂高長期計画」を掲げた。
この年は齋藤郷太郎、坂本文男、小野勝昭の上級生3名が第2次ニュージーランド遠征に参加、そのため冬山合宿の規模を縮小せざるを得なくなる。
久保山は残る部員と横尾尾根から槍ヶ岳に挑み、「槍・穂高長期計画」の初陣を飾る。1966(昭和41)年度の主将・坂本文男はニュージーランド海外合宿での経験から「団体から個人へ」をスローガンに掲げた。
冬山合宿は合戦尾根から大天井岳、赤岩岳と縦走し、東鎌尾根から槍ヶ岳に全員登頂する。この年は学費闘争で大学紛争が吹き荒れ、全学バリケード封鎖の中で合宿準備を強いられる事態となる。

続く1967(昭和42)年度は吉澤清がリーダーとなり、冬山合宿は北鎌尾根から槍ヶ岳を経て奥穂高岳までの縦走隊と、新人隊は中崎尾根から西鎌尾根を経て槍ヶ岳に挑んだ。最終の奥穂までは届かなかったが、厳冬期の北鎌尾根登攀を成功させ、槍ヶ岳に達した。
最終年度となる1968(昭和43)年度の冬山合宿は、長谷川良典がリーダーとなり、明神岳主稜線から前穂高岳を経て奥穂高岳に登頂、4年にわたる「槍・穂高長期計画」にピリオドを打った。
1969(昭和44)年に入ると学生運動はピークに達する。本校にバリケードが築かれロックアウトとなり、部活動に支障をきたした。主将の根深誠は再三にわたり計画変更と縮小を余儀なくされ、冬山合宿は当初の北アルプスを変更し、上越国境で実施した。
翌1970(昭和45)年度は、久しぶりに10名を超す新入部員を迎えた。しかし10月、駿河台に機動隊が突入、大学紛争と相まって部活動は混迷を続ける事態となる。このころ渡辺操部長は病に伏し、1970(昭和45)年2月20日、他界する。その2か月後、文学部教授で、後輩に当たる木村礎先生が第12代の部長に就く。
初のNZ海外合宿、そしてヒマラヤの高峰へ
1963年に入ると「ヒマラヤ研究会」は、具体的に登山隊を派遣する「遠征研究会」に格上げし、目標とする山をエベレストの西側にそびえるギャチュン・カン(7952m)とした。
ところが翌1964年のプレ・モンスーンに全岳隊が北西稜から初登頂に成功し、計画は白紙に戻ってしまう。1964年東京オリンピックが迫る中、高橋進たちは急遽、次の目標とする山の検討に入った。その結果、ギャチュン・カンの西隣にあるゴジュンバ・カン(7743m)と決め、登山許可の取得に動く。
ところが9月、ネパール政府は翌1965年3月からヒマラヤでの登山を禁止すると発表した。そのころ田村宏明がペンタン・カルポ・リ(ドーム・ブラン、6865m)の登頂を終え、カトマンズに滞在していた。そこで田村を介しネパール政府と交渉を重ね、12月、ようやく登山許可を得る。早速、遠征に向け準備作業に取り掛かった。
そうした最中、ニュージーランド海外合宿が急浮上する。「明治大学体育会山岳部ニュージーランド親善登山隊」の第1次遠征は、佐藤大吉が隊長となり、卒業したばかりの高橋登美夫と4年部員の節田重節と姚正雄が選ばれ、1964年12月から登山活動に入ったが、初の氷河を体験するマウント・クック(3764m)のルートに悩まされ、無念の撤退で終わる。
明大山岳部として初めてのヒマラヤ遠征は、1965年春に未踏峰ゴジュンバ・カンを目指した。隊長は高橋進、副隊長に藤田佳宏とマッキンリー・コンビが務め、隊員に平野眞市、尾高剛夫、卒業間もない小林正尚と植村直己、さらに学生の入澤勝の7名で編成された。
4月23日、第2次アタック隊の植村とシェルパのペンバ・テンジンは激闘12時間の末、ゴジュンバ・カン(7743m)の頂に立つ。ところが、登ったのは主峰ではなくⅡ峰と後で判明するなど、初めてのヒマラヤ挑戦は試練の連続で、詳しい山岳地図もない当時の苦労が偲ばれる(ゴジュンバ・カンⅡ峰登山隊)。

画像出典:高橋進編『登頂ゴジュンバ・カン』
続いて11月、橋本清隊長、4年部員の齋藤郷太郎、3年部員の坂本文男と小野勝昭の4名は、第2次隊として再びニュージーランドに向かった。年が明けた1966年1月6日に齋藤と坂本、8日に橋本と小野が最高峰クックに登頂する(ニュージーランド親善登山隊 – 第2次)。
1969年春、日本山岳会はエベレスト遠征の偵察隊派遣を決めた。1次隊は藤田佳宏を隊長に植村直己と菅澤豊蔵という“明大トリオ”が、キャンプ地などを偵察した。
秋の2次偵察隊にも植村は参加、山学同志会の小西政継氏とペアを組み南西壁を8000m地点まで試登する。そして1970年春、オールジャパンのエベレスト登山隊に、明大から6名(大塚博美、藤田佳宏、田村宏明、平野眞市、土肥正毅、植村直己)が選ばれる。
登山隊は5月11日、植村と早大山岳部OBの松浦輝夫氏の2人が南東稜から挑み、日本人として初めて世界の最高峰に立った。
エベレスト(8848m)に登頂した植村は、その勢いを駆ってアラスカへと飛び立つ。8月、北米大陸最高峰マッキンリー(6191m)に単独登頂を果たし、世界で初めて五大陸最高峰の登頂者となった。
日本山岳会のエベレスト遠征が終わると、炉辺会では“オール明治”で再びヒマラヤに挑もうという気運が高まる。そこで海外登山委員会が1970年秋から定期的に開かれ、遠征プランの検討に入った。
ところが、計画を中断させる連続遭難が待ち受けていた。
この記事を書いた人

鳥山 文蔵
- 昭和49年卒部
- 日本山岳会宮城支部 会報・編集出版委員会