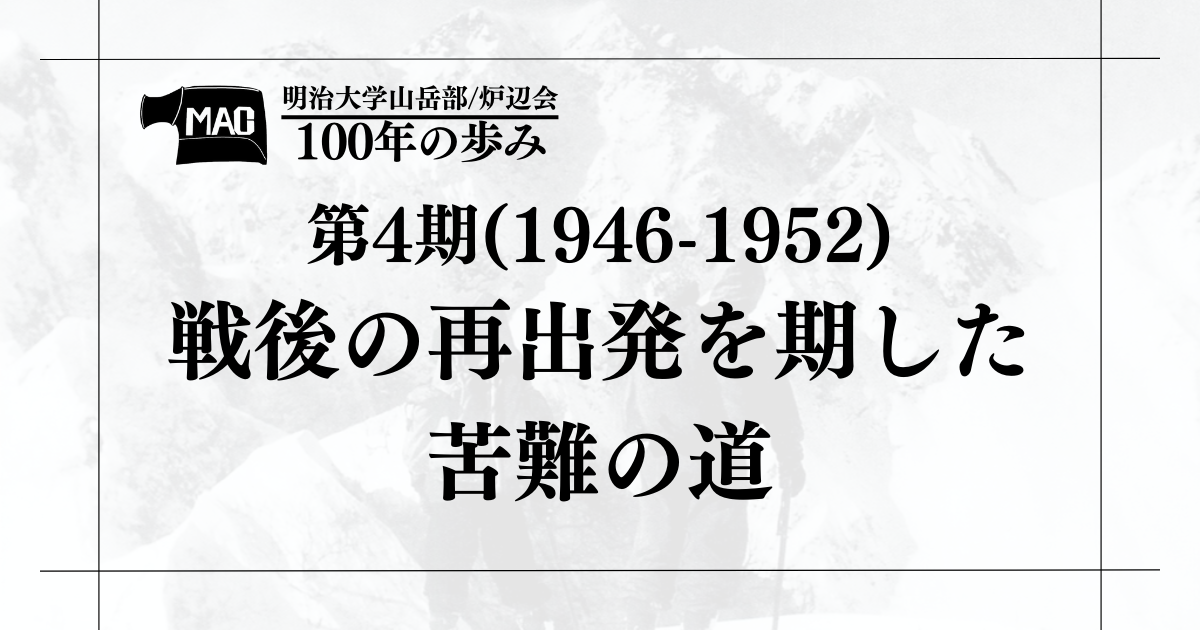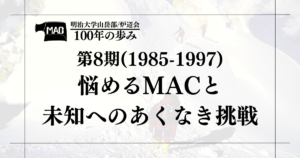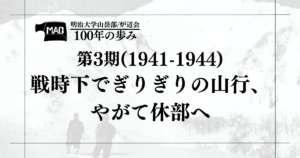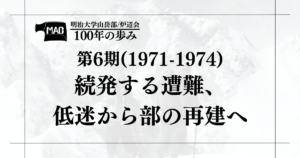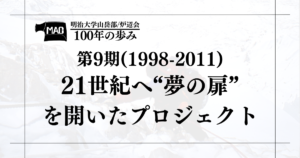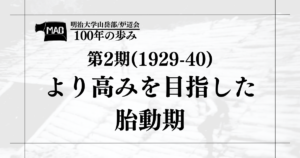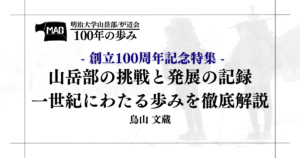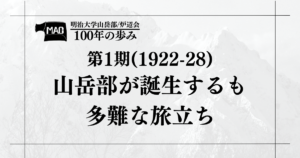終戦を経て山岳部再建へ
1945(昭和20)年8月15日、長い戦争がようやく終わった。しかし、授業は再開できる状態ではなく、戦地から、また勤労動員先から軍服姿の学生が戻ってくるだけだった。在京部員の中には空襲で家もなくなり、ひと握りの米とひと袋のイモを求めて生活するのが精一杯という有り様だった。やがて少しずつ部員が部室に集まりだし、部室の整理や装備類の手入れなどから手をつけた。年明けの新年度から新入生が入ることになり、在京部員たちで部活動の再開に向け、準備作業に追われていった。
翌46(同21)年新学期から授業が再開され、戦前の学生と戦後に入学する学生が入り混じる校内風景となる。4月、戦後初めての山岳部長となる小島憲先生が着任する。先生は食糧難、物資不足の中、「気持ちで負けるな」と部員たちを励まし続けた。
このとき本学体育会は、男女同権の建て前から女子学生にも門戸を開くよう各クラブに指示、山岳部でも「女子を入れるか、入れないか」で賛否両論が起こる。結果、「冬山合宿は無理だが、夏山は大丈夫だろう」と入部させる方向に傾く。その一方、再開する山岳部の主将を誰にするか大きな問題となった。助川の根回しが功を奏し、大塚博美に戦後の舵取りを任せることで落ち着く。そして、再スタートとなる夏山合宿が穂高の涸沢で実施された。
この合宿には総勢14名のうち女子新入部員5名が参加、主将を担う大塚にとって初心者が多く、何かと気苦労が絶えない再出発となる。同年10月12日、戦前の部員たちが繰り上げ卒業することになり、送別会が本校の師弟食堂で開かれた。小島部長とともに前部長の末光績先生も同席、部員13名に21名ものOBが駆けつけ、まるで決起大会のような雰囲気となった。

同年12月17日から、戦後初めての冬山合宿が行われる。テントなどの装備が整わず、場所は八方尾根明大山寮をベースに唐松岳と鹿島槍ヶ岳を目指した。参加者は12名に留まり、家庭の事情で参加できない部員が多かった。

様々な試練を乗り越え、極地法登山に挑戦
主将の大塚は、戦前からの宿題であった極地法による積雪期登山を決意する。次の冬山合宿は、戦前の計画にあった畳岩尾根から奥穂高岳を目指すことにした。
その訓練として47(同22)年3月の春山合宿は、杓子尾根から極地法で杓子岳に挑んだ。当初、参加者は13名の予定であったが、家庭の事情などで参加できない部員が続出、結果8名に減ってしまう。松川・二股から杓子尾根にキャンプ3つを設け、極地法を学んだ。4月を迎えると登山に興味を持つ新人が数多く入部、部活動もいくらか活況を呈してきた。7月に第1次夏山合宿を穂高周辺で、続く第2次合宿は剱岳周辺で20日間という長丁場の合宿を行い、部員たちの結束を高めた。
そして、リーダーの大塚と広羽は学生時代最後の総仕上げとして、戦前に助川先輩が挑んで失敗した、畳岩尾根から極地法による奥穂高岳登頂を目指した。複数のキャンプを設けるため、乏しい予算から中古テント1張をなんとか手に入れたが、合宿費の工面ができず、出発を1日延期せざるを得なかった。冬山合宿の参加者は大塚を含め8名に減った。
12月8日、大塚と広羽をリーダーに佐藤大吉、大嶽隆治、櫻井(後姓・平野)清茂、永井拓治、児島弘昌、飯田貞夫の8名が出発、畳岩尾根に2つのキャンプを建設、23日大嶽、永井、佐藤のアタック隊が苦闘の末、奥穂の頂に立った(極地法で畳岩尾根から奥穂高岳へ)。

48(同23)年度は大塚、広羽が卒業し、戦後世代がバトンを受け継ぎ、主将に永井拓治が就く。冬山合宿で西穂高岳から奥穂高岳を目指したが、出発を前に再び資金面の大きな壁が立ちはだかった。当初の15名編成から10名に減り、結果、新人4名を含め9名と戦力ダウンする。
なんとか合宿費の目処がつき出発できたのは、予定から17日も遅れてしまった。永井、佐藤、大嶽のリーダー陣に児島、愛、それに新人の服部稠、金澤恒雄、細田公男、榎本三郎の9名に、大塚OBが加わるメンバーとなる。一行は貧弱な装備で極寒に耐えながら雪まみれとなって奮闘、年明けの1月14日、連続9時間に及ぶ激闘を乗り越え、永井、佐藤とOBの大塚は、奥穂の頂で感無量の握手を交わした。
戦後の混乱も少し落ち着き始めた49(同24)年春、小島憲部長に代わり京城大学山岳部で活躍した泉靖一先生が第9代の山岳部長に着任する。
冬山合宿は再び永井と櫻井がリーダーとなり、明神東稜から極地法で奥穂高岳に登頂する。3年にわたる極地法登山は、戦前のレベルを超える実力が備わり、部活動にも勢いが増していった。

翌50(同25)年度は新制高校から第1期の卒業生が入学、新時代の到来を予感させた。この年の主将・服部稠は、前穂高岳・北尾根から極地法による奥穂高岳登頂を目標にした。
迎えた冬山合宿は、服部、児島、星野登のリーダー陣に、飯田、金澤、細田、榎本、清水(後姓・長崎)稔、高橋進、鵜野悟郎、中尾正武、古谷二郎、新人の中村雅保、田辺史、相蘇良正、岡本啓造、須藤、鈴木、松田に大塚OBが加わる総勢20名という大パーティとなる。
年が明けた51(同26)年1月、3日間にわたる風雪に耐え、児島、清水、鵜野の3名が奥穂の頂に立つ。戦後から続けてきた極地法の総決算とも言うべき冬山合宿を終えた。

1950(昭和25)年12月~51年1月、前穂高岳・北尾根~奥穂高岳の冬山合宿にて。正面は奥穂高岳。
一転して昭和26年度は振るわない一年となる。年明けの春山合宿で、戦後初めての遭難事故が起きてしまう。家庭の事情により遅れて入山した3年部員の飯田貞夫が、3月12日、剱岳・早月尾根上で疲労凍死するという悲しい遭難だった。
52(昭和27)年に主将となった高橋は、飯田の遭難を踏まえ精力的な合宿を展開する。夏山合宿の前半は剱岳から槍ヶ岳まで縦走、その後、涸沢をベースに穂高の岩稜や稜線を登攀する。後半は3班に分け後立山連峰や南アルプスを縦走、中身の濃い合宿となる。
冬山合宿は穂高から槍ヶ岳まで縦走する班、前穂での高所幕営班、さらに新人訓練を兼ね両パーティをサポートする班の3隊に分けた。縦走班は天狗沢の雪崩が危険になったうえ、サポート班の荷揚げが届かず、計画を変更し南岳から下山する。高所幕営班は奥穂と北尾根を登攀したが、様々な課題を残して終わる。
こうして終戦後から52年までの7年間を振り返ると、当時の部員たちの溢れんばかりの凄まじいエネルギーに驚かされる。苦難の時代をものともせず、戦争によるブランクを埋め、極地法で厳冬期の穂高に挑んだ不屈の闘志は、万感胸に迫るものがある。
初代監督の多難なスタート
1951年になると本学体育会は、各運動部に指導と管理を担当する「監督制度」を導入、各クラブのレベルアップを図ることにした。山岳部の初代監督に藤井運平が就任する。
彼は戦後の大学山岳部の復興を支えるため、日本山岳会が主導した「関東学生山岳連盟」の理事に就き、慶大OBの谷口現吉氏と各校の山岳部員を引率し、東京近郊の山や富士山で指導する役割を担った。そうした経歴を持つ藤井が母校の山岳部の初代監督に就くことは、まさにうってつけの人材であった。
ところが、部員たちは初めての「山岳部監督」に馴染めず、OBが日参して何かと指導したが、学生の自主性が損なわれると反発を露わにした。これに対し、藤井監督をはじめ戦前のOBたちは寛容に受け止め、学生の考えや運営方法を尊重することにした。
“監督”に就いた藤井の心情を思うと、初年度に戦後初めての遭難が起き、また新制高校から入学した新世代の学生たちとの意思疎通に苦慮するなど、“初代監督”の船出は前途多難となった。
こうして戦後からの再建を果たした山岳部は、新たな高みに向かって邁進していった。
この記事を書いた人

鳥山 文蔵
- 昭和49年卒部
- 日本山岳会宮城支部 会報・編集出版委員会