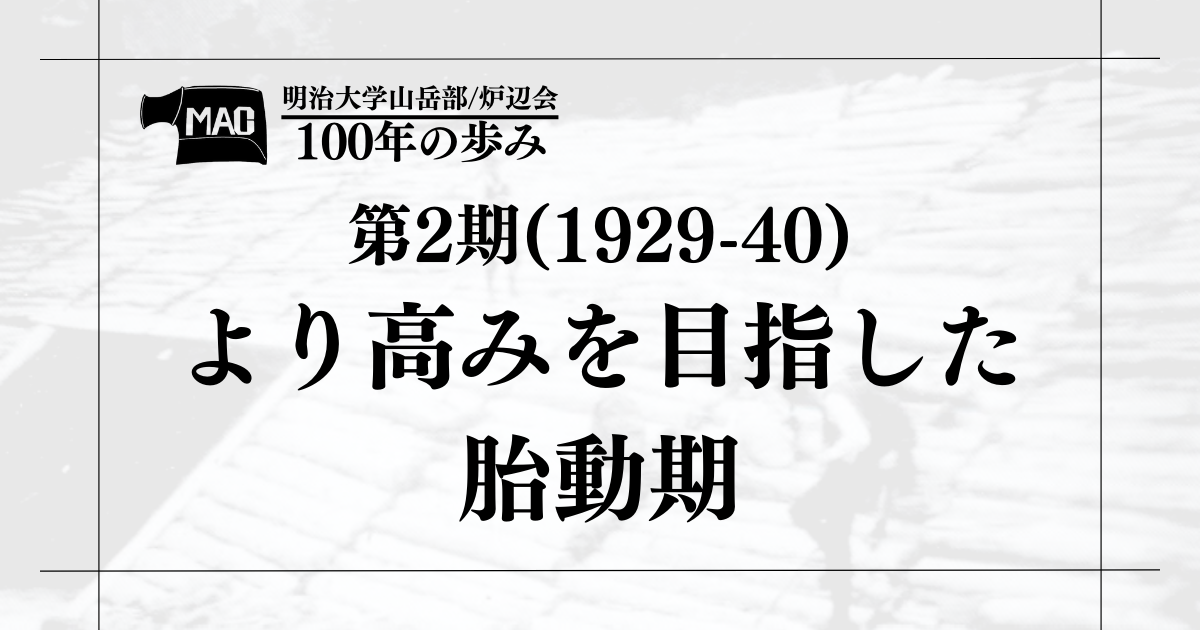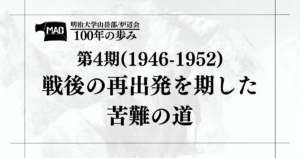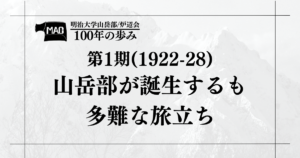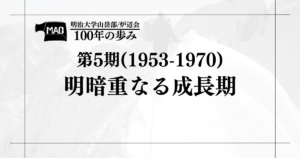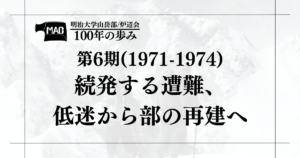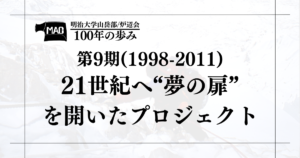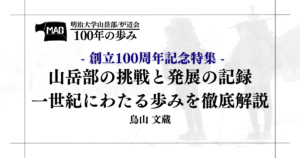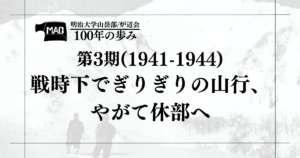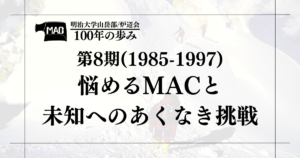第2世代の登場で新たな挑戦
昭和初期までに北アルプスの主な峰々は踏破され、各大学山岳部はより厳しい積雪期および厳冬期登頂にしのぎを削り、さらに困難な縦走の挑戦へと切磋琢磨する時代に入った。こうした最中の1929(昭和4)年11月、明大、早大、法大、日大など29校が加盟する関東学生登山連盟が結成され、大学山岳部同士の連携が図られた。
30(昭和5)年はMACに大きな動きがあった。一つは3月、交野武一、宍戸文太郎、岩崎厳の3名が白馬岳から唐松岳までの積雪期縦走に成功する。二つ目は日本山岳会への入会である。5月に入会し会員番号は「1180」。代表は当時の山岳部長・神吉徳壽先生の名前で登録された。
最後は部室の移転である。関東大震災後、本学の再建工事に伴い部室は転々と移動を余儀なくされた。体育館が竣工されると6月に体育館地下一階に山岳部の部室が割り当てられ、それから68年間にわたり利用され、ここから巣立った部員は数知れない。

山岳部は31(同6)年4月から、リーダー的手腕、技量がそなわった部員に「正部員章」とし、正部員が活動の中心を担った。それから4年後35(同10)年4月から「正部員章」が「リーダー章」に変わり、それに伴いリーダー会となる。
そうした状況下で初めての遭難が起こる。31年の夏期山行で藤井運平一行が南アルプスの上河内岳に向かったとき、雨天で増水した小渋川で人夫の牛田佐市が転倒、水死するという悲運な事故だった。
この年の11月、炉辺会長が初代の神宮徳壽先生からOBの北畠義郎に引き継がれる。また、3年ぶりに「炉辺」第5号が12月に発行され、これまでの年報スタイルから複数年まとめて発行する形に変わった。
32(同7)年になると、南アルプスでの沢登りにも挑んでいく。夏山山行第9班の太田保、桜木省吾、海老根真雄の3名は赤石沢の完全遡行を成し遂げる。
神宮徳壽先生が山岳部長を退くと、部長先生が1年で交代する不遇な時代を迎える。創部10周年を迎えた32年、春日井薫先生が就任するもわずか1年で退任。その後に就いた太田直重先生も1年で代わり、部員たちにとってはやるせない時代となった。

1931(昭和6)年7月、南アルプスの聖岳・赤石岳山行で聖沢の「テッポウ」(伐り出した材木を一気に川流しする施設)を通過する部員たち。
このころ山岳部では、積雪期縦走が盛んに行われるようになる。33年3月、村井栄一と大坪藤麿はOBの石本省吾とともに、今田由勝を人夫に槍・穂高縦走に向かう。また、南アルプスでも34(同9)年3月末から4月にかけ、針ヶ谷宗次が人夫の小椋八十八伴い両俣小屋から北俣岳を経て塩見岳に登り、三伏峠まで積雪期縦走を果たす。
34(同9)年5月、登山やスキーを実践する末光績先生が第7代の部長に着任する。期待を持って先生を迎えたのも束の間、8月、創部後初めて部員が死亡する遭難事故が起きてしまう。悪天候で穂高合宿を取り止め上高地へ下山中、針ヶ谷宗次が横尾本谷に架かる丸太橋を渡っているとき、バランスを崩して増水した濁流に転落、遺体で発見される。主将の死は山岳部員たちに大きな衝撃を与えた(岳友たちの墓銘録 – 針ヶ谷宗次)。
八方尾根に明大山寮が完成
登山界は厳冬期の山々に挑む時代となり、各大学山岳部は登山訓練の拠点となり、専用の山小屋を持つようになる。当然、当時の部員たちの間でも専用小屋を持ちたいという願望が募っていった。
34(同9)年、登山に詳しい末光績先生が部長に就くと、早速、主将の針ヶ谷宗次たち上級生は、末光部長に山小屋の建設を嘆願する。部員から山小屋の必要性を聞いた末光部長は大学側へ働き掛けてくれた。その結果、35(同10)年10月5日、待望の「八方尾根明大山寮」が誕生する。
この山寮から年末、2班の縦走隊が出発する。1班は合木武夫をリーダーに木目田至、新人の小寺孝一は唐松岳から鹿島槍ヶ岳まで、2班は宇野(後姓・木谷)六郎をリーダーに石井丈夫、石原(後姓・久保)信恕、神田國彦は唐松岳から不帰岳を経て五竜岳を目指した。とりわけ合木隊はキレット小屋に8日間も閉じ込められる苦闘の末、厳冬期縦走を成功させた。
こうして八方尾根に完成した明大山寮は、部員たちの大きな活動拠点となった。
穂高に「明大ルート」開拓と初めての台湾遠征
1931(同6)年に入ると北穂高岳・滝谷はじめ前穂高岳東面の岩壁で新ルートの開拓が盛んになる。MACは29(同4)年から三ツ峠などの岩場で岩登りの練習を重ねた。
35(同10)年に入部した小国達雄と人見卯八郎の2人は、翌36(同11)年8月、前穂高岳・北尾根第4峰東南面に登れそうなルートを見つけ、途中にあるオーバーハングを乗り越え、新ルートの登攀に成功する。のちに「明大ルート」と命名されるという、金字塔を打ち立てた。11月に2人は再び「明大ルート」に挑み、苦戦を強いられながらも途中の岩場で一晩ビバークした後、積雪期の初登攀に成功する(前穂高岳・北尾根第 4 峰東南面「明大ルート」開拓)。
ところが、ザイル・パートナーを組んだ人見卯八郎は、2年後の38(同13)年9月、谷川岳・マチガ沢で墜落死する。戦前における2人目の遭難犠牲者となり、岩壁登攀のエキスパートを失う、大きな痛手となった(岳友たちの墓銘録 – 人見卯八郎)。
このころ大学山岳部は、海外の山へ挑む動きが活発化する。小国たち上級生は、部室でヒマラヤの写真を眺めながら異国の高峰に熱い視線を注いでいた。そこで小国は、ヒマラヤの前哨戦として台湾遠征を計画する。
39(同14)年7月、奇萊主山連峰へ偵察隊を派遣、山崎善郎をリーダーに山下格也、小島孝夫の3名が出発する。このとき山崎と小島は新高山(3950m)に、小倉は単独で合歓東山(3394m)に登り、手応えを感じ帰国する。
翌40(同15)年3月、小国達雄隊長、山崎善郎、寺島鉄夫、松永豊、北脇通男の5名は、本学創立60周年記念事業をかねた台湾遠征に向かう。渡台したメンバーは3月下旬、積雪期の合歓主山と東山に登り、4月上旬に奇萊主山連峰を縦走した(明治大学台湾遠征)。
この後、小国は遠征で初めて使用したカマボコ型テントをはじめ雪洞による露営など、ヒマラヤの峰々を目指して雪上訓練に励んだ。しかし、日本は戦争への道をひた走る時代となって山岳部にも暗雲が忍び寄り、次第に山から遠ざけられる運命が待ち構えていた。
この記事を書いた人

鳥山 文蔵
- 昭和49年卒部
- 日本山岳会宮城支部 会報・編集出版委員会