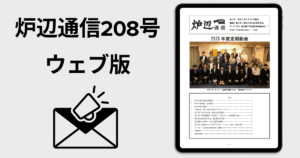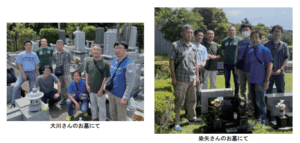3~7月の山行一覧
- 春山決算合宿
3月1日~10日 場所:大日主稜~大日岳往復 - 個人山行
4月12日 場所:富士山御殿場口 参加者:4年川嶋、3年菅野、中澤OB - 新歓山行1
4月12日 場所:陣馬山、生藤山 参加者:2年木村、関、1年早川、鈴木OB - 新歓山行2
4月20日 場所:奥多摩、高水三山 参加者:3年福澤、2年木村、関、1年斎藤、下津浦、鈴木、武田、前島 - 上級生山行
4月19~20日 場所:中央アルプス宝剣岳 参加者:4年川嶋、3年菅野、川嵜OB - 2年生個人山行
5月1~3日 場所:北アルプス爺ケ岳、鹿島槍 参加者:2年木村、関、高柳監督 - 上級生山行
5月2~5日 場所:北アルプス白馬岳 参加者:4年川嶋、3年菅野、福澤、宮津OB - トレーニング山行
5月5日 場所:奥多摩、川乗山から赤杭尾根 参加者:2年木村、関、1年玉山、下津浦、鈴木、武田 - 一年生強化山行
5月11日 場所:丹沢縦走 参加者:4年川嶋、3年菅野、福澤、2年木村、関、1年玉山、下津浦、鈴木、武田 - 一年生強化山行
5月17~18日 場所:奥多摩、丹波~飛龍山~雲取山~鴨沢下山 参加者:4年川嶋、3年菅野、福澤、2年木村、関、1年玉山、下津浦、鈴木、武田 - ゲレンデ山行
6月1日 場所:幕岩 参加者:4年川嶋、3年菅野、福澤、2年関、1年下津浦 - 一年生強化山行
6月6~8日 場所:奥多摩(三峰神社~雲取山~長沢背稜~一杯水~鳩の巣駅下山) 参加者:4年川嶋、3年菅野、福澤、2年木村、関、1年玉山、下津浦、鈴木 - 上級生山行
6月14日 場所:富士西湖十二ケ岳(クライミング講習) 参加者:3年福澤、2年木村、天野コーチ、川嵜コーチ - 岩登り個人山行
6月15日 場所:奥多摩(氷川屏風岩) 参加者:3年菅野、2年関、1年下津浦、鈴木 - 岩登り個人山行
6月21日(全員)、22日(2年以上の上級生) 場所:奥多摩(氷川屏風岩) 参加者:4年川嶋、3年菅野、2年関、1年玉山、下津浦 - 上級生山行
6月22日 場所:北アルプス錫杖岳(左方カンテ~注文の多い料理店下降) 参加者:3年福澤、2年木村、川嵜コーチ - 日本山岳会学生部クライミングレスキュー講習会
6月28日 場所:丹沢 広沢寺 参加者:3年福澤 他大学メンバー
2024年度春山決算合宿行動概要
メンバー:川嶋 管野 福澤 木村 関 中澤
監督 宮津 OB
3月1日(土)
先発隊は赤旗や官物を持って新幹線で富山へ移動。後発隊は夜行バスで富山へ向かう。
3月2日(日) 入山 晴
富山で先発隊と後発隊が合流して立山駅まで移動。立山駅から順調に歩き七姫平に到着する。テント設営後、立山駅に戻り、残りの官物を持って七姫平に向かう。
CT) 電鉄富山駅 (6:057:11) ~ 立山駅 (8:169:10) ~ 七姫平 BH (9:55) ~ 立山駅 (11:30) ~ 七姫平 BH(12:30)
<上部偵察隊> メンバー:川嶋 管野 福澤 宮津 OB
歩荷を終えた後、偵察へ出発する。尾根取り付きから急登ではあるがしっかりキックステップを決めていけば問題ない。膝程のラッセルである。740m付近から徐々に傾斜が緩む。800mまで偵察して引き返し、BHに到着する。
CT) BH (13:02) ~ 800m地点(14:00)~ BH (14:34)
3月3日(月) 停滞 雨後雪
朝から雨が続いているためテント内にて待機する。徐々に雪に変わったが雪崩や低体温症の危険があるため予備日を使い停滞とする。
3月4日(火) BC荷揚げ 雪
取り付きから急斜面が続く。800m地点からは脛から膝程のラッセルとなる。BCまでは尾根が広いためルートファインディングに注意しながら進む。特に丸山は尾根が広く、先のコルまでの道筋が分かりづらい。ピークをトラバースするようにコルに降りる。コル上部の1000m付近からまた尾根が広くなる。1080mの立派な杉の木の付近をBCとする。BC到着後官物をデポする。
CT) BH (5:55) ~ BC (9:01)
<荷上げ隊> メンバー:関 木村 中澤監督
官物をデポした後順調に下っていく。休憩をはさみながら進む。900m付近でアイゼンとロープを装着する。急斜面が続くため慎重に進みBHに到着する。
CT) BC (9:30) ~ BH (10:40)
<上部偵察隊> メンバー:川嶋 管野 福澤 宮津 OB
官物デポ後、出発。急斜面となる1170m地点までは脛程のラッセルが続く。1170mから1300mまでは急斜面となる。急斜面で積雪状況によっては雪崩のリスクがある。傾斜の緩む1330m地点まで上がる。1330mからP1400mまでは尾根が広く平坦である。P1400mからコルに下った後P1566まで尾根が細くなり急斜面となる。1400mから1450mまでの急斜面に1ピッチFix工作を行う。支点はすべて灌木で取る。1480mから1500mまでは尾根が細く、両雪庇となっている。しっかりと雪庇の発達状況を見ながらトレースを付ければ問題なかったためFix工作は行わない。赤テープを付けながら下っていく。1330m地点で休憩を取る。そこで実3でのBC入り後、1200mから1300m間に50m2ピッチFix工作を行うことに決める。順調に下りBHに到着する。
CT) BC (9:30) ~ 1300m地点 (10:54) ~ 1480m地点(12:39)~ BC(14:10)~ BH (14:50)
3月5日(水) BC入り 曇り後雨
雪が締まっており、わかんは使わずに登る。徐々にツボ足では踏み抜きが多くなってきたので、わかんをつける。気合いを入れて登り切りBCに到着する。
CT) BH (5:50) ~ BC (8:40)
<上部偵察隊> メンバー:川嶋 管野 福澤 宮津 OB
急登が始まる1170m地点まで順調に進む。一旦上部まで上がり、再度Fix箇所と支点の確認を行った後下りながら工作を行うこととする。1200m~1300m間50m2ピッチFix工作を行う。支点はすべて灌木で取る。工作終了後BCまで下る。
CT) BC (9:20) ~ Fix工作終了時(10:50) ~ BC (11:20)
3月6日(木) FC荷上げ 雪
わかん装着して出発。赤テープをつけながら順調に登っていく。P1566m付近は尾根が広く、また顕著な尾根が派生している為悪天時にルートを見失わないよう標識を充実させる。P1566mから先は緩やかな傾斜が続く。この辺りは脛から膝程のラッセルである。1600m付近で徐々に森林限界に近づいていき、1600m地点から先は急斜面が所々に出てくる。順調に進み前大日岳FCに到着する。官物をデポし、赤テープ、旗を充実させながら慎重に下る。
CT) BC (6:05) ~ FC (11:00) ~ BC (12:55)
3月7日(金) 停滞 雪
後日晴れる予報であること、朝の時点で雪が多く降っていることから予備日を使い停滞する。各テント暖房して物を乾かしたりし、また睡眠をとることで体力回復に努める。
3月8日(土) FC入り 晴
わかんを装着して出発する。一部トレースは見えにくくなっているが赤テープ等を目印に順調に標高を上げる。途中休憩を挟みながらFIX箇所もスムーズに通過し、FC予定地に着く。強風の中整地を行い、風よけを作りながら並行してテントを設営する。
CT) BC (5:55) ~ FC (11:14)
<上部偵察隊> メンバー:川嶋 管野 福澤 宮津 OB
テント設営後、出発。前大日岳からコルまで下っていく。コルから先急斜面のナイフリッジで雪庇が発達していたためロープを装着し、スタカットで50mロープを伸ばす。中間支点はスノーバー、終了点は灌木で取る。所々に灌木が出ている。メインFixを張り、川嶋と宮津OBが通過した後管野が福澤を引き上げる。その後50m程上がり先のルート状況を確認する。この先の尾根は細いものの、雪庇はそれほど発達していない様子であることを確認する。偵察はここまでとし引き返す。
CT) FC(13:07) ~ 1850m地点(14:33) ~ FC (15:00)
3月9日(日) 頂上往復 晴
ロープメンバー:管野―福澤 木村―宮津 OB 川嶋―関―中澤監督
わかん装着後、出発。ナイフリッジ手前でロープを着け、ロングロープで中間支点を取りながら慎重に進む。中間支点は3パーティで併用する。トップの管野が中間支点を取り、最後尾の中澤監督が回収する。リッジ、斜面共に緩くなる1870m地点でコンテに切り替えて気合いを入れて登っていく。P1920mから先は傾斜が緩くなり雪庇が大日平側に発達していたため、北側斜面を巻くように進む。ここまでは膝程のラッセルである。P2011mから痩せ尾根が終わり、尾根がとても広くなる。雪が締まっていて歩きやすい。ここから先は北側に雪庇が発達している。大きく南側を巻くように進む。早乙女岳、大日岳の肩を過ぎ2200~2350m付近まで急登となる。そこから徐々に傾斜が緩んでいく。山頂付近は大きく雪庇が発達しているため特に注意しながら進む。剱岳の山頂は見えないが、それ以上北東側によると雪庇の上に乗ると判断し高度計2501mの地点を大日岳山頂とする。休憩を取った後、行き同様に雪庇に注意しながらコンテで順調に下っていく。ナイフリッジの箇所はそのままコンテで通過する。FCでロープを外す。
CT) FC (5:56) ~ P2011(8:11)~ 大日岳山頂 (10:34) ~ FC(13:09)


3月10日(月) 下山 晴
わかんを装着して出発。雪質、スリップに注意しながら順調に降っていく。FIX通過後の回収もスムーズに行う。最後の急降まで気を抜かずに下山する。BHにてデポを回収し、立山駅に無事到着する。
CT) FC (5:55) ~ BC (9:23) ~ BH (10:29) ~ 立山駅 (11:36)