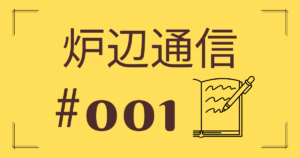この記事は 炉辺通信 №204 (令和6年4月10日発行) に掲載されたものを電子版として再公開したものです。
全く赤の他人同士が、同郷とか同窓という絆が分かると、旧知の間柄のように親しみが一挙に深まることがある。
ここに同郷、同窓のふたりがいる。けれども年の差があり、片や会社社長、片や大学生という立場から、出会うことも、ましてや話をする機会もなく、ふたりは黄泉の国へと旅立ってしまった。
しかし、生前ふたりには時間差を置いて、自ら歩いた共通のトンネルがあった。社長にとっては“苦闘・不屈のトンネル”、1人の大学生にとっては“夢に向かう青春のトンネル”であった。
これらについて、年の差離れたふたりに“なんら関係性もなく、設定自体に無理がある”と見捨てるには忍びず、ここに敢えて書いてみることにした。
ふたりの生い立ち
植村直己(昭和39年卒)は、1941(昭和16)年2月12日、兵庫県城崎郡国府村上郷(現在の兵庫県豊岡市日高町上郷)に7人姉弟の末っ子として生まれた。
彼は余り目立つこともなく地味な存在であったが、小学校の友人によると、“負けず嫌いで意地っ張りだった”と言う。その後、地元の県立豊岡高校を卒業、1年置いて明治大学に進学、体育会山岳部に入部する。それからの活躍はご承知のとおりである。
一方、同じ但馬の生まれで47歳も離れた高校の大先輩がいた。その人はのちに黒部ダムを建設する太田垣志郎氏である(以降、敬称を略させていただきます)。
太田垣は1894(明治27)年2月1日、兵庫県城崎町湯島(現在の兵庫県豊岡市城崎町湯島)に5人姉弟の長男として生まれた。彼はやんちゃだったのか、小学生のとき誤って鋲を飲み込んでしまう。医者であった父は、当時の医術ではどうすることもできず見守るしかなかった。そのため太田垣は運動を控え、休学するなど病弱となり、同級生より2年遅れて1908(明治41)年、旧制豊岡中学校(現在の県立豊岡高校)に入学する。休学中の1911(明治44)年、咳き込んだ拍子に鋲を吐き出すと次第に健康を取り戻したが、生涯、血痰などで苦しんだという。
ふたりの生い立ちを見ると、植村は農家の末っ子、太田垣は医者の長男と、家庭の境遇は違えど共通するものあった。まず生まれた場所は、太田垣が今の豊岡市北部の海寄りで、植村は同市南部の山間部で、それぞれ産声を上げている。また、ふたりは2月生まれの水瓶座であった。この星座は太田垣にとって黒部ダムにつながり、植村にとっては冒険へのデビューとなるアマゾン河6000㎞イカダ下りに表れている。こじつけかもしれないが、単なる偶然とも思えない。さらに時代は大きく違うが、ふたりは現在の県立豊岡高校の大先輩と後輩という間柄でもあった。
ふたりは47歳も年の差が違うので、お互い顔を合わせることはなかったが、同郷の縁なのか、はたまた運命なのか、ふたりを結びつける場所があった。それは秘境に造られた「黒四ダム」である。それはまた、植村が入部した我が山岳部の「剱岳長期計画」とも深く結びつくことになる。
ふたりを結ぶ黒四ダム完成までの茨の道
元気を取り戻した太田垣は、熊本の旧制五高から京都帝国大学に学び、1920(大正9)年、友人より数年遅れの27歳で卒業する。銀行に一度就職したが、25(同14)年、阪急電鉄に移る。ここで創業者の小林一三氏(1873~1957)から会社の経営などを学ぶ。
長い戦争が終わった46(昭和21)年、20年にわたる仕事ぶりや実績が評価され、彼は阪急電鉄6代目の社長に就く。ところが、当時の関西は戦後の混乱期で計画停電が続き、電力の大飢饉時代にあった。とりわけ電車を運行する私鉄にとっては、死活問題となる。
関西経済界は、戦前の発電・電送会社を束ね、新たな電力会社の設立に動く。51(同26)年5月、関西電力(以降、「関電」と表記)が設立されると、その初代社長に太田垣志郎が就任する(1959年11月まで)。おそらく関西経済界の重鎮・小林一三氏が、太田垣の手腕を見込んで推挙したのではないだろうか—-。
57歳になった太田垣社長は、早速、新たな電源立地に取り組む。戦前の計画にあった黒部峡谷に着目、関電の土木技術陣は9月より現地調査を開始、ダム建設候補地などを調べた。その結果、事業プランは約500億円の資金をあて、7年の工事期間で完成させるというものだった。
当時、「資本金135億2000万円の会社が、資本金の3倍強を投じて大発電所を建設するのは無謀だ、冒険だ」と社内からも、世間からも危ぶまれたという。それでも太田垣社長は「関西の消費電力を一気に賄うには、黒部しかない。工期が7年遅れれば、関西の電力は破綻する」と、秘境の地でのダム建設を決断する。 この黒部ダムと黒部川第4発電所を建設するに当たり、太田垣社長の有名な言葉がある。
「経営者が十割の自信をもって取りかかる事業、そんなものは仕事のうちには入らない。七割成功の見通しがあったら勇断をもって実行する。それでなければ本当の事業はやれるもんじゃない。黒部は是非とも開発しなけりゃならん山だ」と言って決断したという。
この太田垣のコメントにある「事業・仕事」という言葉を「冒険」に、「経営者」を「冒険者」に言葉を置き換えてみると、植村の数々の海外チャレンジに通じる言葉のように聞こえてくる。まさしく太田垣は、経済界における“冒険者”の1人であったとも言える。
植村が日高町立国府小学校を卒業した2年後の55(同30)年、黒部第4発電所建設計画は国と県から承認を受ける。そして、植村が県立豊岡高校に入学した翌56(同31)年6月、建設事務所が開設、5つの工区に分かれ7月に着工、10月からは資材や工事機械、工事従事者を運ぶ大町トンネル(現・関電トンネル)の掘削工事が始まった。
ところが、翌57(同32)年5月、信濃大町側入り口から1690mの地点で、掘削工事が破砕帯に遭遇、中断に追い込まれる。掘削の全面ストップは関電、とりわけ太田垣社長にとっては、成否を分ける最大の試練となる。
この事態に直面した太田垣社長は長靴を履いてトンネル掘削現場に出向き、破砕帯による出水状況を視察しながら工事従事者を労い、励ましと不退転の決意を語り続けたという。
7ヶ月を要して、ようやく破砕帯の突破に成功、掘削から1年半が過ぎた58(同33)年2月、大町トンネルは貫通。翌59(同34)年2月には黒部トンネルも貫通し、“世紀の大工事”は最大のヤマ場を乗り越えた。
同年3月、植村が県立豊岡高校を卒業するころ、工事現場は遅れを取り戻し、工事は順調に進んだ。こうした状況を確認した太田垣は11月、社長を辞し会長に退いた。
植村参加の「剱岳長期計画」と黒四ダム
日本経済が高度成長期を迎えた1960(昭和35)年4月、植村は明治大学に入学、同時に体育会山岳部に入部する。そのころ山岳部は決算合宿をどの地域で実施するか悩みの種のときだった。主将に就いた木村敏之(昭和38年卒)は、61(同36)年度から剱岳周辺を活動エリアにする「剱岳長期計画」を立て、実行に移す。この計画合宿での入山、下山のコースによって、工事中の黒部ダム工事事務所に大変お世話をいただくことになる。
黒四ダムが送電を開始したころ、同年12月の冬山合宿は小窓尾根と早月尾根から剱岳を目指した。2年部員の植村は早月尾根隊として登頂する。年が明けての春山合宿は立山・弥陀ヶ原から剱岳に登る。
62(同37)年の立山・中央山稜より立山・剱岳を目指す冬山合宿(CL高橋登美夫)から、間組・扇沢事務所の便宜を受ける。先発隊は間組の車で扇沢事務所に挨拶に出向き、大町トンネル通過の手続きを行う。この後、本隊と一緒に事務所の車で大町トンネルを抜け、さらにダムサイトのエレベーター(間組が管理)を使わせてもらい、トンネル出口から200m下の黒部川の川底に下り、従業員の寄宿舎をベースハウス(BH)として借用する。
これまで山岳部員たちは、無積雪期の山行や合宿で遠くから黒部ダム工事の様子を眺めたことはあったろうが、実際トンネルを抜け間近に巨大なアーチ式ダムを初めて見たときは、目を見張ったに違いない。このとき植村は、同郷の人がダムを造ったことなど知る由もなかった。
当時、間組はダム両岸の岩盤強化のため薬剤とコンクリートで固める工事や仕上げ工事に従事していたが、積雪期になると危険が伴うので大きな工事は控えていた。そこで冬山や春山の合宿で入山する学生のため、間組はいろいろと便宜を図ってくれたようだ。合宿終了後も建設事務所に下山報告と協力御礼に訪ねると、事務所のトラックやバスで信濃大町駅までわざわざ送ってくれたという。まさに至れり尽くせりの協力があった。
翌63(同38)年1月、3年部員の植村はサブリーダーに推挙される。同年3月の春山合宿は、大日主稜線から剱岳に挑み、植村は登頂に成功する。この後、彼は合宿で残った食糧と燃料を譲ってもらい、積雪期の単独行に出発する。自著『青春を山に賭けて』(毎日新聞社刊)に次のような下りがある――
「最上級生でサブリーダーになったとき、私は単独山行を試みた。黒四ダムから黒部峡谷の阿曽原峠を経て、北仙人尾根の頭に出、剱岳の北側にある池ノ平から剱沢をめがけて下り、黒部別山にのびるハシゴ谷乗越しに出て真砂尾根をつめ、そのピークから地獄谷をめがけて下り、弥陀ヶ原を経て、千寿ヶ原に下った。奥大日から剱岳をやった合宿山行の帰りのことで、食糧は合宿の残りものでやっつけた。テントなし、スコップひとつでの雪洞生活5日の行程だった。この山行は、自分がリーダーとして人の上に立つための試練と考えた」
リーダーという重責を担うため自らに課した単独行は、その後の植村の生き方を決定づけたと言っても過言ではない。それも黒部ダムからスタートしたことを思うと、そのダムを造った同郷の太田垣とは、目に見えない絆で結ばれていたような気がしてならない。まるで太田垣が高校の後輩に―「植村よ、ここから世界に羽ばたけ!」と、背中を押してくれたのではないだろうか—-。
この年(同38年)6月、7年の歳月と513億円の工費、延べ1000万人の人手、そして171名の尊い犠牲により、黒部ダムと黒部川第4発電所は竣工する。太田垣にとって自ら決断したダムと発電所が完成し、ようやく肩の荷が下り、ほっとしたに違いない。
その年の冬、植村にとって学生最後の冬山合宿として北仙人尾根から剱岳を目指した。植村以下7名の先発隊は、発送済みの荷物を宇奈月駅で受け取り、関電専用軌道で小黒部谷出合のBHとなる名和館へ運ぶ。一方、主将の小林正尚が率いる本隊は、信濃大町から扇沢事務所に出向き挨拶。大町、黒部両トンネルの利用許可をもらい、阿曽原上部軌道を経て名和館に入った。
そして大晦日の下山では、関電の好意で上部軌道を乗り継ぎ、また大町トンネルでは間組のトラックが出迎え、扇沢事務所では昼食までご馳走になる歓待を受けた。
年が明けた64(同39)年3月、菅沢豊蔵主将は、八ツ峰完登の偵察を兼ね春山合宿を真砂尾根から剱岳に向かった。このときも大町トンネルを通過している。
「剱岳長期計画」と黒部ダムとのつながりは植村卒業後の翌年で終わる。65(昭和40)年3月の春山合宿(主将:菅沢豊蔵)は、「剱岳長期計画」の締めくくりにふさわしく内藏助平から八ツ峰を登攀し剱岳を目指した。このときも入山で間組にお世話になる。間組の好意により約1t余りの荷物と12名の部員たちは、車で大町トンネルを抜け、冬の装いの黒部峡谷に飛び出す。そして黒部川左岸の飯場をBHとして使わせていただいた。下山日も飯場を整理、掃除した後、ダブルボッカで荷物をダム側トンネル入り口に集結。間組の車で入山同様、信濃大町側まで乗せてもらい終了した。
このように4年間にわたる「剱岳長期計画」は、冬山、春山の計8回の合宿のうち、半分の4回の合宿で黒四ダム関連施設を利用させていただいた。この陰には間組事務所の微に入り細に入りの協力があった。
但馬人気質のふたり
1964(昭和39)年3月、植村直己は学生最後の合宿を終え、明治大学を卒業するが、学生時代、3度も黒四ダム扇沢事務所にお世話になっている。
期せずして同年3月16日、太田垣志郎は逝去してしまう。70歳の生涯であった。このタイミングを思うと、明大を卒業したばかりの植村に、今度は太田垣が―「これからの人生、苦難に負けず、但馬魂で頑張れ!」と、惜別のエールを送ったような気がしてならない。そして植村は2ヶ月後の5月、移民船で横浜を出港、世界へと羽ばたいていった。結果としてふたりは最後まで顔を合わせることなく、植村は自らの夢に向かって旅立ち、太田垣は後輩のその後の活躍を知ることなく黄泉の国へと旅立っていった。
同郷の植村直己と太田垣志郎――。ふたりに共通するのは、なんと言っても“但馬人気質”であろう。但馬地方の気候風土から、但馬人は素朴で実直、粘り強く、忍耐力があるとされてきた。まず太田垣の言動から見ると、剛毅にして朴訥、芯の強そうな、逞しい但馬人の姿が見える。
一方、植村については彼自身の著書並びに数々の追悼文からも人柄を知ることができる。とにかくふたりの諦めない強固な意志と粘り強さには、つくづく感心させられる。
もう1つ共通するのは“人間愛”ではないかと思う。太田垣が社長を辞して会長のとき―「私は黒四の工事で1人でも殉職者の出たときには、身を切られるように辛かった」と語っている。太田垣の心痛を察すれば余りある。結果として殉職者は171名にのぼり、慰霊碑に刻む殉職者名を太田垣は自ら筆を執ったと言われている。
一方の植村も、今さら言うまでもないが、
持って生まれた誠実さと人間愛に満ちている。
1970(昭和45)年5月、日本人として初めて世界最高峰エベレストに登頂したとき、登れなかった隊員のために頂上の石をたくさん拾って来たという逸話がある。また翌71(同46)年、国際エベレスト南壁登山隊で遭難死したインド代表隊員の遺品をインドに立ち寄り、遺族に渡してくるという逸聞が残っている。さらにイヌイットをはじめ海外で出会った地元の人たちとの触れ合いからもよく分かる。
同郷の先輩である太田垣志郎が旅立ってから20年後の1984(昭和59)2月13日(推定)、植村直己はマッキンリー(現・デナリ)で消息を絶ってしまう。明大卒業後、世界に飛び出すパワーをもらった“黒四ダム”。まさにここは植村の原点であり、出発点であった。ふたりの足跡を振り返ると、特別な感情を持たずにはいられない。
太田垣が亡くなって60年、そして植村が亡くなって40年が過ぎ去ろうとしているが、但馬人のふたりが黒部トンネルに響かせた足音は消えることはない。
生まれ育った境遇、時代は違っていたが、「但馬」という故郷を持つふたりの間には、どこか重なり合う部分があったように思えてならない。今も“但馬気質”の山気が匂い立っている—-。