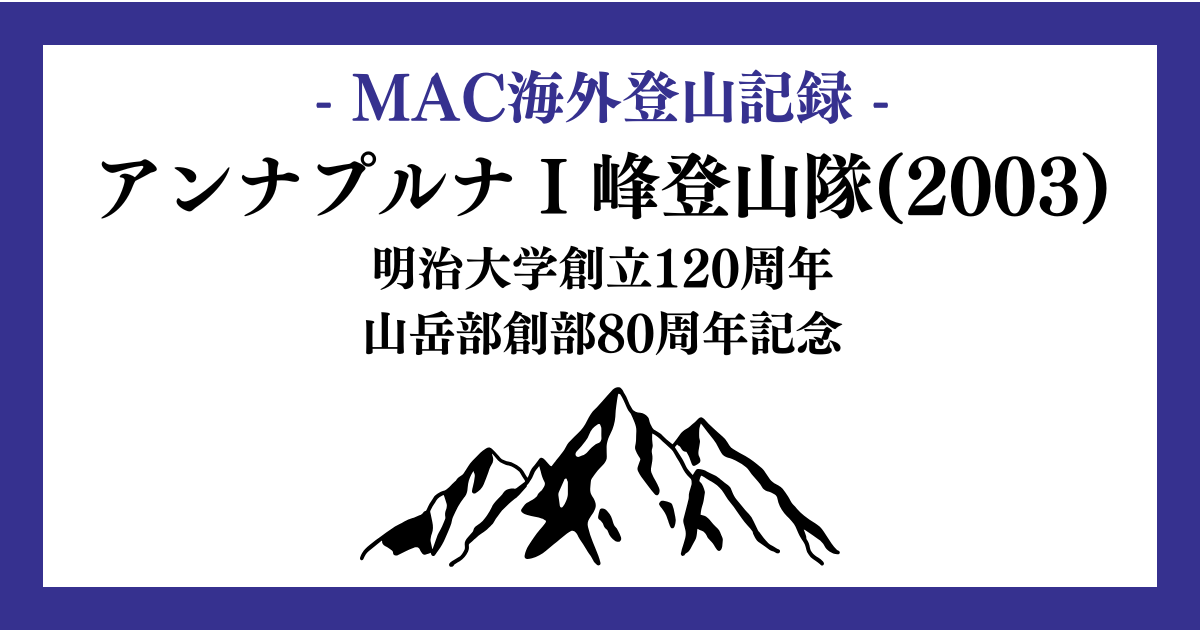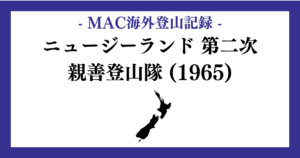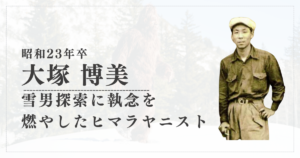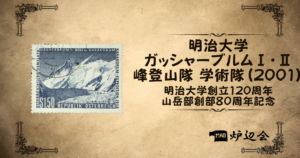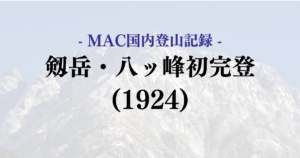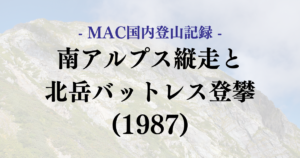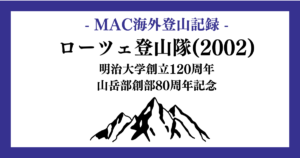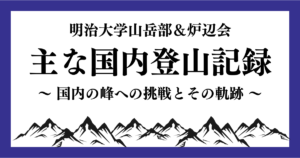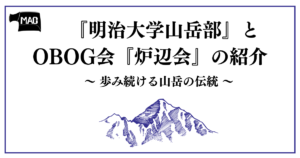アンナプルナⅠ峰登山隊
| 活動期間 | 1997(平成9)年11月〜12月 |
|---|---|
| 目的 | 北面「鎌ルート」からのアンナプルナⅠ峰(8091m)登頂。 |
| 隊の構成 | 隊長=山本篤(昭和61年卒、34歳) 隊員=高橋和弘(平成8年卒、23歳)、豊嶋匡明(同9年卒、22歳) |
行動概要
空路で北アンナプルナ氷河末端に入り、BC(4000)建設。
隊員3名とシェルパ2名の5名で出発。苦しいラッセルが続き、ときには腰までの深さで苦しい登高となる。フィックス2ピッチを張り、C1予定地に装備品をデポし下降。翌日は全員で荷揚げ。
悪天の合間を衝いて標高5000mにC1建設、装備を整理、デポし下降。翌10月1日は風雪で休養日。
深いラッセルを乗り越えC1に到着するとテント1張が埋まり、掘り起こす。10時半ごろ北東バットレス左方の大きなルンゼで大規模な雪崩が発生、爆風を受けたが大事に至らなかった。この後、全員で上部の新しいテントサイトにC1を移動、シェルパ2名はBCに下る。
アンザイレンしてC2予定地に向かう。C2まで続く雪原と急登にラッセルを強いられる。「鎌」へと続く急登手前の懸垂氷河をC2とし、装備をデポし下降。翌5日は3名で荷揚げを行う。
C2(6000m)建設、装備を整理し下降。
C2入りのため3人がアンザイレンし上部へ登高すると、高橋が体調を崩したため全員BCまで下降。翌日から10日まで雪に閉じ込められ停滞。
数日の降雪で2m積もり、翌日は全員で隊荷の掘り出し。
天候が回復し、最後のチャンスと上部を目指す。C1到着後、天候は安定せず、また高橋の体調が悪く登山中止を決定、BCへ下山。
ヘリコプターでBCを離れ、登山活動を終える。
8000m峰の連続登頂を目指す野心的なプラン
明治大学マナスル登山隊で登攀隊長を務めた山本篤は、8000m峰のマナスルで高度順化した体調を有効活用し、アンナプルナⅠ峰に引き続き挑むことにした。山本篤は少数パーティで、シンプルかつスピーディに行動するセミ・アルパイン・スタイルとし、さらに氷河ルートの6500mまで2名のシェルパを使う“セミ・シェルパレス”で臨んだ。40日を登山期間とし、ヒマラヤの8000m峰に秋・冬連続して挑むことにした。
アンナプルナ北面の最も大きなネックは、雪崩の危険性であった。当時、その脅威を避けるオランダ・ルート(ダッチ・リブ)が注目され、最も多く登られていた。しかし、山本は未踏のルートに執着する。北面「鎌ルート」はほとんど登られておらず、敢えてこのルートで目指すとすれば、季節は初冬しかないと考えた。
ところが、その年は例年を上回る降雪に見舞われてしまう。苦しいラッセルを強いられたものの、悪天候の合間を衝いて11月30日、第1キャンプ(C1)を建設する。さらに一時期好天が続き、12月6日、メンバー3人はスピードを上げ、一気に6000mに第2キャンプ(C2)を設営した。このころは全てが順調に進んでいるかのように見え、いよいよ核心部の北面「鎌」へのルート工作と頂上アタックに向け、3人は希望を膨らませたていた。ところが、好天は期待に反し長くは続かなかった。
そこに追い打ちを掛けるようなアクシデントが起きる。12月7日、3人はC2入りのため上部へと向かった。その途中で高橋和弘が肺水腫に罹ってしまう。すぐに3人はBCまで下降する。翌日から再び雪に閉じ込められ停滞となるが、その間も高橋の体調は戻らなかった。天候が回復した12月13日、3人はこれがラストチャンスと上部を目指したが、高橋の気持ちの中では、すでにアンナプルナは終っていたという。
この悔しさをドリーム・プロジェクトにC1到着後、3人で今後の活動を話し合った。C1に入っても天候が安定しないこと、また、このまま無理に突っ込むと雪崩の危険に曝されるだけだと判断、隊長の山本篤は登山続行を諦め、中止を決断する。3人の最高到達地点は6000mのC2となり、野心的な試みは厳冬のアンナプルナの悪天候に打ち砕かれてしまった。
12月16日、隊員たちはヘリコプターでBCを後にした。3人は徐々に視界から遠ざかっていくアンナプルナⅠ峰をいつまでも眺めていた。ファイナル・ピークまで2000m余りを残す撤退となり、特に高橋和弘の心の奥底に深い傷跡を残した。本人は「もう二度とこの山には来ないだろう」と心の中で思っていたが、来る21世紀の初頭を飾る「ドリーム・プロジェクト」で、再びアンナプルナⅠ峰と相まみえることになる。
- 報告書『明治大学マナスル・アンナプルナⅠ峰登山隊報告書』(1999年4月発行)
- 谷山宏典著『登頂8000メートル』(山と溪谷社、2005年8月発行)
この記事を書いた人

鳥山 文蔵
- 昭和49年卒部
- 日本山岳会宮城支部 会報・編集出版委員会